このページは、ホーム![]() ソリューション・技術
ソリューション・技術![]() 技術一覧
技術一覧![]() 土木技術
土木技術![]() 地盤改良 質問箱 データベース
地盤改良 質問箱 データベース![]() 施工上の問題に関する質問のページです。
施工上の問題に関する質問のページです。
施工上の問題に関する質問
- 土・土壌に関する質問
- 液状化・地盤沈下に関する質問
- 環境に関する質問
- 住宅建設に関する質問
- 施工上の問題に関する質問
セメント固化改良に関する質問
小規模取水堰基礎地盤の改良工法
小規模な取水堰(川幅7m程度)の基礎地盤ですが、床付面より2〜3mの深さで軟弱層があり、これを地盤改良するに当たって置換工法を採用したいと思います。小範囲かつ簡素な浅層での地盤改良工法がありましたらお教え下さい。
一般的には置換工法が最も安くて確実ですが、残土処分費用によっては、費用が高くなるかも知れません。この様な場合、深層混合処理などのセメント固化系の処理が一番でしょう。ただし、陸上からの施工となりますので河川上に足場を確保する必要があると思います。この場合、足場はH綱製か盛土になるでしょうか。
また、この状況では、バックホウによる混合が、機械も一般的かと思います。この場合、処理手順として、以下のような流れになります。
施工範囲のドライアップ → パワーショベルによる粘土層の掘削撤去 → 粘土へのセメントの添加・混合 → 混合処理土の埋め戻し
ただし、2つの施工上の制約があります。
1)掘削域が矢板などで締め切られて、ドライアップ状態であること。
2)パワーショベルで掘削した土砂を仮置きして、セメント混合・撹拌する場所があること。
上記の条件が合えば、表層混合ではパワーショベルによる方法が一番安価であると思います。なお、セメント添加量は、土や目標改良強度によって異なります。有機分の多い(強熱減量の多い)粘土ほど、添加量は多くなります。
また、改良する深さ、数量などの条件にもよりますが、施工重機が施工位置まで入ることができれば、置換工法よりも、パワーブレンダー工法などによる現位置での固化処理工法の方が安価な場合もあります。(参考:パワーブレンダー工法協会:http://www.power-blender.com/)
粉体攪拌工法(DJM)による地盤内空洞発生原因
現在DJMを施工中ですが 改良後にチェックボーリングを行ったところ、GL−6m付近で長さ1mにおよぶ空洞を確認しました。軽石では比較的良好な杭が造成されるのですが、ロームでは改良ムラが多く見られます。原因は攪拌不足と思うのですが、大きな空洞の生じた理由が分かりません。(対象土質:軽石およびローム/地下水位:GL−1m程度、地下水の流動はない/固化材:一般軟弱用、添加量 180kg/m3 室内強度の3倍を目安とする)
可能性としてあるのは2つです。
- DJM(粉体噴射攪拌工法)では空気圧で粉体を地盤内部へ送ります。この時の高圧空気は回転軸に沿って排気されます。これが何かの原因で地盤内に残ったもの。
- 過去に近接して建てられたビルや土中構造物はありませんでしょうか?建設時に横矢板などの山留めを用いていた場合、パイピングなどの現象で砂が山留め内部に流れ出し、土中に空洞が発生することがあります。
また、回転ムラに関しては、改良土のサンプルでセメント分含有量を測定できます。強度が出ていなくて、セメント量が少なければ撹拌不足だと思われます。ローム土ですから、有機分含有量は少ないと思いますが、有機分が多いとセメント量が多くても強度が出ない場合があります。
(DJM工法研究会のHP: http://www.djm.gr.jp/J/what.htm)
建物底盤の半分が軟弱地盤に浮いた状態となる場合の沈下対策
ある地盤に建物を建てる際、表層から数メートルは軟弱地盤でその下層に支持地盤があるとします。建物は長辺方向で数十メートルの規模です。支持地盤は建物底盤に平行でなく、傾いています。施設の底盤はその長辺方向の距離で約半分は支持地盤に岩着するのですが、約半分は浮いた形となります。このとき、浮いた部分の置換や改良が考えられると思いますが、どのような手法がありますか。
この様な比較的浅い部分の改良ですから、何らかの材料による置換工法が最適だと思います。
置換する場合、以下の3つの方法があります。
- 良質土による置換:安価ですが、締め固めの管理が必要です。良質土の購入と掘削土の残土処分が必要となります。
- セメント混合処理土による置換:現位置土にセメント添加をすることにより堅固な地盤をつくります。均質なセメント添加を行う必要があります。セメント材料は10円/1kg程度ですので、m3当たり100-200kg
- コンクリート置換:最も堅固な地盤となります。コンクリート購入と残土処分が必要になります。施工価格に関しては、現地の物価(材料や残土搬出処分)と必要な強度によって大きく異なります。
盛土法尻の深層混合における留意点
全体的に地盤が非常に軟弱な斜面(N値が3以下)で高盛土の端部に地盤改良の計画があるのですが、深層混合処理工法を行うための施工機械の搬入や、斜面上での施工ヤ−ドの確保といった内容が検討事項として考えられるのですが、その他留意事項があれば教えて下さい。
ご質問から、盛土地盤の法尻の軟弱粘土にCDM(深層混合処理工法)を施工するということだと思います。
まず、法尻からの施工では足場の確保が重要な課題です。機械を選定した後、盛土に小段を設けた場合の円弧すべりの検討が必要です。小段上に重機を載せて安定が確保できない場合、H綱などによる仮設足場を設置してそこからの施工となります。
弊社とライト工業で開発したオープンウィング工法があります。この工法は機械撹拌工法ですが、地盤に開ける孔は、直径20cmですが、拡翼式の回転軸を用いることで、地中に直径120cmの固化体を造成できます。N値15以下の地盤を対象として0.4m3の小型のバックホークラスでφ1.2m固化体を造成できます。
河川を埋め立てる際のヘドロに必要な試験内容と処理方法
現河川を埋め立てて道路利用する場合、ヘドロそのものに必要な試験内容および1試料当たりの金額はいくら位ですか。有害な重金属類が含まれているヘドロの処理方法にはどんなものがありますか。またヘドロを原位置で固化改良する時に必要な試験内容と、その単価について教えてください。
1.ヘドロそのものに必要な試験内容および1試料当たりの金額
| 土粒子の密度試験 | 7,130 |
|---|---|
| 含水比試験 | 1,890 |
| 粒度試験 | 15,200 |
| 液性限界試験 | 8,820 |
| 塑性限界試験 | 4,200 |
| 強熱減量試験 | 9,600 |
| 合計 | 46,840 |
直接費
ヘドロに限らず、土壌の特性を確認するためには物理特性試験を実施する必要があります。主な内容と金額は、右表のようです。
また重金属が含まれている場合は、環境省告示46号の溶出試験が必要です。土壌環境基準のうち重金属に相当するのは、カドミウム、シアン、鉛、六価クロム、ヒ素、水銀、セレン、フッ素、ホウ素であり、試験費用は1金属当たり5,000円程度です。ですから5種類試験した場合には、1試料当たり 25,000円となります。土壌中の重金属の含有量は場所により大きく異なるため、詳しく調査するためには25,000円×採取箇所が必要です。
2.有害な重金属類が含まれているヘドロの処理方法
汚染土壌の修復は、汚染物質を取り除く「浄化」が原則ですが、重金属汚染されたヘドロを安価に浄化する手段は今のところありません。そこで通常は、汚染物質を物理化学的に封じ込める「固化・不溶化」が採用されることが多いようです。固化不溶化処理方法は、重金属の種類により異なりますが、弊社では、カドミウム、鉛、水銀などはセメント系固化材による固化処理、ヒ素、六価クロムなどにはキレート剤、あるいは固化材と薬品を併用しています。また改良土を有効利用することを目的に、ヘドロの造粒固化不溶化処理することもあります。本工法によればヘドロが数分で砂状に改良できますので有効利用が容易になります。ただし汚染土壌を有効利用するためには、役所などの承認が必要となります。
3.ヘドロを原位置で固化改良する時に必要な試験内容、単価
ヘドロを原位置で固化処理する場合には、配合試験が必要となります。配合試験では、固化材の量を3種類程度変化し、それぞれの強度と不溶化効果を確認します。
- 配合試験
- 一軸圧縮試験(7日、28日)
- 溶出試験(7日材齢)
- pH試験
配合試験は一式でおよそ100万円程度になります。また固化処理土の利用用途に応じて、三軸圧縮試験、CBR試験などが必要になることもあります。
土地の道路境界から5mの範囲で地耐力が不足しているのですが
先日、ある土地について地盤調査を行いましたが、道路から5m辺りまでの地盤が弱い事が判明しました。土地は、道路より1.5m高く、道路を造った段階で(購入した)土地側にも深く掘り込む事があるので、それが原因では無いか?との事です。「硬化剤を混ぜた土を弱い部分にだけ混ぜて強度を持たせる方法でも、大丈夫だとは思うが、工学的保証が無く、長年の感でやるので、出来れば、筒を打ち、中に硬化剤を混ぜた土を入れる方法(鋼管工打設工法?)が、10年保証が付いているので良いでしょう」と勧められましたが、価格的には大きく違うと言われました。周りは30年近く前から開けてきた住宅街で、購入した場所は長い間空き地になっていた所です。基礎はベタ基礎の予定なのですが、勧められている方法の方が、確実なのでしょうか?土地は40坪、1階建坪は22坪(駐車場含む)ですが、改良工法の値段はどれくらいの格差があるものなのでしょうか?また工法としてはこの2種類しか無いのでしょうか?
ご質問の件、お困りだろうと思います。
ご質問の内容は、道路境界から5mの範囲で、地盤の支持力が足りないことだと考えております。対策工法として、以下の二つをお考えなのですね。
1)砂と硬化剤の混合土による埋め戻し
2)鋼管工打設工法
お話から考えると、比較的安価な方法として、以下のことが考えられます。
地面から2〜3m程度の土が悪いのならば、
1)緩い土が砂のように粒状ならば、もう一度緩い部分を掘ってローラーで締め固める。
2)緩い土が粘土の場合、土を掘って、敷地の外に捨てて、再生砕石などの良質な石で置き換える。
3)土の処分費用が高価な場合、土にセメントを混ぜて重機を使って埋め戻す。
これらの方法でも、新築の家が2階建て程度でしたら、比較的安価に頑丈な地盤にすることができ、1立方m当たり1万円前後の費用ですむと思います。
もう少し情報を頂ければと思います。
- 支持力が足りない深さは地面からどのくらい下までか?
- 軟弱な土は、砂・粘土・ローム(オレンジ色の土)のいずれでしょうか?
- 建物は、平屋2階建て程度でしょうか?
また、業者の方とよく話し合うことをお勧めします。
1m厚さの表層地盤改良工事として適切な方法は
1mの厚さの表層地盤改良工事の施工方法として適切な工事方法を教えてください。また、施工後の固まり具合の確認はどのようにしたら良いかもお教えください。
1m厚さの表層地盤改良工事(固化処理)の適切な施工方法についてのご質問ですが、これは改良する面積と現地盤強度によって、施工方法が異なります。
大きく分けると、施工法で「原位置混合方式」と「事前混合方式」に、固化材の添加方式によって粉体添加方式」と「スラリー添加方式」とに分けられます。ここでは、原位置混合方式と事前混合方式に分けて簡単に説明します。
1.原位置混合方式
改良地盤に直接セメントや石灰などの固化材を粉体又はスラリーで添加して、機械で撹拌する方式です。機械の走行・作業帯が確保できることが原則となります。
最も簡単な方法は、セメントや石灰を撒き出しながらバックホウで撹拌するというもので、面積がそれほど広くない場合には最も安価な方法ですが、規模が大きい場合は撹拌効率(スピード)は専用の機械と比べると落ちます。
対象面積がある程度広くて施工スピードを確保したい場合は、専用の処理機械を用います。バックホウの先にロータリー撹拌方式やトレンチャーと呼ばれる撹拌用(撹拌翼)のアタッチメントを取り付ける方法や、耕耘機に似た形のスタビライザという機械などを用いて撹拌する方法が代表的です。
バックホウが走行できないような軟弱地盤、水面下の埋立地の改良の場合、泥上車やフロート台船に攪拌翼を取り付けた機械で施工します。
固化材の撒出し方法は粉体添加の場合、人力、バックホウ、不整地運搬車、専用撒出機などを規模に応じて利用します。スラリーの場合は、混合プラント(貯留サイロ、ミキサー、ポンプ)から配管圧送して添加する方式となります。
2.事前混合方式
事前混合方式は、改良したい軟弱土と固化材をプラントや仮置き場などで事前に混合してから現地に搬入、撒き出す方法です。原位置混合が不可能や場所(狭小で重機の作業性が悪い、機械の設置・進入が困難)や、大規模な埋立地に土砂を投入しながら改良を同時に行いたい場合などに用いられます。
3.強度の調査方法について
宅地地盤の強度(支持力)ということであれば、「スウェーデン式サウンディング」という方法が一般的です。この結果より、N値もしくは一軸圧縮強度quと呼ばれる強度の指標値を換算式で求めてから地盤の支持力算定式を用いて許容支持力(その地盤が支えきれる単位面積当たりの重さ)を算定し、上に載る建物の設計支持力(建物の単位面積当たりの重さ)以上になっているかどうかを比較することになります。
根入れ不足の親杭横矢板の親杭周り地盤改良方法
アンカー付きの親杭横矢板による垂直土留め壁(永久構造物)を工事しております。設計では親杭の下端を基岩へ1.5m貫入することになっていましたが、想定していた深度から基岩が出現せず、軟弱層への貫入で工事が完成してしまいました。親杭下端に支点を与えておかなければアンカーを支点とする片持ち梁の状態となるため、親杭(H-300)の剛性が満足できません。そこで、軟弱層を地盤改良しようと思うのですが、親杭の安全性を確保しながらの工法としてどのようなものがあるでしょうか。土地は40坪、1階建坪は22坪(駐車場含む)ですが、改良工法の値段はどれくらいの格差があるものなのでしょうか?また工法としてはこの2種類しか無いのでしょうか?
「想定していた深度から基岩が出現せず、軟弱層への貫入で工事が完成してしまいました。」ということですが、一般には「想定していた深度から基岩が出現せず」という段階で発注者に現場条件の違いを報告し、設計変更を行う必要があったものと考えられます。
ここで、取られる対策としては、以下の3つでしょう。
- 親杭を継ぎ足して深部の基岩まで打ち込む。
- アンカーを増やすなど土留め壁の構造変更を行う。
- 軟弱層を基岩相当の強度もしくは設計上安定が保てる強度まで地盤改良する。
ご質問の状況は工事が完了してしまったということなので、おそらく3.地盤改良のみが対策可能なのでしょう。
親杭に近接して地盤改良を行う際のポイントは以下の通りです。
- 軟弱層を基岩相当の強度もしくは設計上安定が保てる強度まで地盤改良する。
- 親杭の変形を拘束するためには親杭外周に密着した地盤改良が必要。
- 地盤が軟弱な場合には、地盤改良施工中に親杭が変形しないように側方変位の少ない地盤改良工法を選定することが重要。
ご質問の現場状況に合った“特殊な”地盤改良工法は無いと思われるので、一般的な地盤改良工法を紹介して回答を進めます。上記条件123を満足するためには、サンドコンパクションなどの密度増大締固め工法ではなく、セメントを高圧で噴射攪拌する固結工法が良いでしょう。高圧噴射攪拌工法は、ロッド先端吐出口からセメントスラリーを水平方向に高圧噴射して、地盤を切削しながら地盤改良するため親杭と改良体が密着します。また、排泥を行うため、比較的周辺地盤側方変位の影響が少ないと思われます。
詳しくは、高圧噴射攪拌工法メーカーに相談してみてはいかがでしょうか。
河川頭首工基礎地盤のセメント系地盤改良について
河川の頭首工を主に設計しているのですが、支持力が得られない時は杭か接地面積を広げる等して行ってきたのですが、これからは、地盤改良で行おうと思います。セメント系の改良方法、改良後の地耐力、改良深、工法などがわかる資料はどのようなものを参考にすれば良いのでしょうか?・置き換えは、占用の問題があるため出来ません。・浸透路長の関係で頭首工上下流に止水矢板を打っております。
河川頭首工基礎地盤のセメント系地盤改良についてのご質問ですが、設計を行う際には、まず、どの設計基準書に準拠して設計を行うべきかを明確にする必要があります。これは、発注者の違いによって、同じようなセメント系地盤改良であっても、設計条件、設計手法、安全率などの考え方に違いがある可能性があるからです。
さて、ご質問の頭首工(水を堰き止め、頭の高さまで押し上げるという意味が語源)についてですが、頭首工とは農業用水の取水堰であることから、発注者は農林水産省の地方農政局や、県市町村の農林課ということになります。準拠すべき設計基準書は「設計基準 頭首工 (社)農業土木学会」などでしょうか?
セメント系地盤改良を施工方法で大分類すると以下の3つになります。
| 1.事前混合固化処理工法 | : | 土とセメントをプラントで混合してから埋め立てる。 |
| 2.浅層混合処理工法 | : | 原位置混合、一般に施工深度3m程度まで。 |
| 3.深層混合処理工法 | : | 原位置混合、一般に施工深度30m程度まで。 |
河川頭首工基礎地盤の改良には『深層混合処理工法』が採用されるケースが多いと考えられるので、深層混合処理工法に関して簡単に紹介します。
【深層混合処理工法】
(1)施工方法分類
- 機械攪拌式:地盤を攪拌翼で攪拌しながら固化材(セメントスラリーや粉体)を吐出して改良柱体を造成する工法。スラリー系(CDM工法など)、粉体系(DJM工法など)
- 高圧噴射式:薬液注入から発展した工法で、ロッド先端吐出口からセメントスラリーを水平方向に高圧噴射して、地盤を切削しながら改良柱体を造成する工法
(2)改良形式と設計方法
- ブロック式:接円式、ラップ式、壁式、格子状などの平面配置で改良柱体を造成し、改良地盤全体を1つのブロック(重力式構造物)として設計する。滑動、転倒、支持力、端趾圧、円弧すべり、沈下量などを検討する
- 杭式:改良柱体1本1本をまばらに分散して配置し、改良部と未改良部の改良面積比率に応じて複合地盤の平均せん断強さを設定して、円弧すべりなどの検討をする。建築分野では、改良柱体を低強度の群杭として設計する手法もある
(3)改良深さ
- 支持層が浅い場合:着底型
- 支持層が深い場合:浮き型・・・軟弱層が傾斜している場合には不同沈下に注意
参考資料は以下の通りです。
| 1.セメント系固化材による地盤改良マニュアル[第二版] | (社)セメント協会 |
|---|---|
| 2.陸上工事における深層混合処理工法 設計・施工マニュアル | (財)土木研究センター |
| 3.海上工事における深層混合処理工法 技術マニュアル | (財)沿岸開発技術研究センター |
| 4.セメント系深層混合処理工法CDM 設計と施工マニュアル | CDM研究会 |
| 5.粉体噴射攪拌工法(DJM工法) 技術マニュアル | DJM工法研究会 |
| 6.建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針 | (財)日本建築センター |
| 7.最新の地盤改良工法の現状と設計・施工のポイント | (社)土木学会「新しい材料・工法・機械講習会」 |
高含水比地盤の掘削運搬に適した地盤改良方法
切土工事なのですが、地盤が高含水比で運搬する為に地盤改良をしなければならないのですが、今現在では表層混合処理工法を行ってから搬出する計画になっています。また、搬出後の運搬土は再利用する予定です(時期未定)。表層混合処理工法以外の工法を教えて下さい。
高含水比粘土の運搬は、環境的にも問題ですね。対策工法としては以下のような方法があります。
(1)石灰などの吸水材を混ぜ込む
比較的安価な改良工法です。石灰を混ぜると吸水により、粘土が安定化するため、ダンプによる運搬が可能になります。また、含水比が下がるだけで固化しませんので再利用も可能です。処理土のpHが高くなるのが難点です。
(2)天日乾燥
天日乾燥も良い工法です。ただし、時間と場所があればと言う条件付きです。しきならべた粘土に溝を掘り、排水させます。簡単に搬出可能です。
(3)粒状化
最も面白いのが、高含水比粘土の粒状化処理です。セメントと粒状化剤を使えば、簡単に粘土が砂になります。この方法を用いれば、砂としての再利用が可能になります。pHは11程度です。加工単価は、処理土の量によりますが、5,000円/m3〜10,000円/m3程度です。
宅地造成地擁壁背面の地盤改良必要性
5mの高さの無筋コンクリート擁壁(傾斜あり)の上の土地に、木造2階建てを新築しようとしています。もともと小高い丘だったところを造成した住宅団地の端にあります。擁壁に接する位置まで建物が来ます。住宅メーカー2社がスウェーデン式サウンディングで調査した結果、1社は補強の必要あり、他社は必要なしでした。N値は前者で擁壁側のいくつかの深さのところに2.8-3.0の部分がありますが、概ね4-5以上の値です。後者ではN値はすべてのポイントで5以上でした。非常に硬い層は擁壁側で深さ約7メートルにあり、道側(擁壁と反対側)では深さ1-2メートルにあります。以下について教えてください。
- スウェーデン式サウンディングの信頼性
- 本当に補強の必要がないのか
- もし地盤補強をするなら表層のみで効果があるのか
宅地造成を行う際に、盛土高さが1mを越える場合は、”宅地造成等規制法”の定めに従って擁壁を設計し、都道府県知事または市長の許可を得る必要があります。この検査に合格しているなら、住宅程度の建物が載っても大丈夫なように擁壁は設計されています。また、平成7年の兵庫県南部地震における斜面崩壊の教訓から、擁壁の耐震性についても十分照査することを推奨するようになっています。
ご質問の土地のように、高さ5mの擁壁上の土地であっても、住宅程度の建物が載っても大丈夫なように設計されているものと考えられます。いかがでしょうか、少しは不安が解消されたでしょうか?
さて、ご質問の回答をいたします。
1.スウェーデン式サウンディングの信頼性
スウェーデン式サウンディングは現在使用されている土質調査法の中で最も歴史が古く、小規模住宅では最も多く使われている調査法であり、この調査結果を基に多くの住宅が建てられ、問題が発生していないことから、実用上ある程度の信頼性があるものと考えています。
2.地盤補強の必要はないのか
●盛土全体の安定と擁壁の安定
擁壁から道路までを20mとすると、基盤層の傾斜角は15°(勾配1:4)です。傾斜角が30°近い急斜面なら建物が盛土ごと滑ることも考えられますが、傾斜角15°では盛土崩壊の危険はまずないでしょう。
擁壁近くまで建物が来るとのことですが、前述の通り宅地造成の検査に合格しているなら擁壁崩壊の危険もないと考えられます。
●地耐力と不同沈下
「常識的に考えれば擁壁側に傾く可能性は否定できないのではないか」とお考えですが、締固め不足の地盤なら層が厚い擁壁側ほど沈下が多く発生し、建物が擁壁側へ傾くことも考えられます。
地盤調査のN値が概ね5以上であるとのことですが、このN値はスウェーデン式サウンディングから得られるNswとWswから、"N=0.02Wsw+ 0.067Nsw"などで換算した標準貫入試験のN値と考えて良いのでしょうか?もしN値が5以上であるなら、締固め不足による不同沈下の心配はないと思います。ただし、擁壁のすぐ背面は他の場所より締固めにくいので、この場所に独立基礎などの小さな基礎が配置された設計となっているなら、沈下に問題がないか再度ハウスメーカーに確認すると良いでしょう。
また、簡単な経験式から、砂層の許容地耐力qa=N=5tf/m2であり、木造2階建ての重量1tf/m2程度なら十分支持できます。
3.表層の地盤のみで効果があるのか
表層のみの改良でも、建物荷重を均等分散し不同沈下を抑制する効果と、擁壁への土圧を低減し擁壁の安定性を高める効果があります。しかし、現状でも安全だとしたら、過剰に安全にすることになるだけです。
地盤改良必要性の判断は、地盤調査結果だけを見て判断できるものではなく、土地造成方法や放置期間(降雨により地盤は締まる)、同種建物の基礎構造、地域性(地震、豪雨)などを考慮して総合判断するものです。経験豊富な大手住宅メーカーの設計士が判断したことなら十分信頼できると思います。さらに、地盤が問題で家屋にトラブルが発生した場合に20年間の保証があるなら何も心配する必要はないのではないでしょうか。
セメント系地盤改良の設計法について
セメント系地盤改良については、以下6つの質問です。
- 支持力について、「地盤改良マニュアル」(セメント協会)P109では、許容支持力を一軸圧縮強度から求めて、P262では、必要粘着力から一軸圧縮強度を求めているように思えます。セメント配合量は後者の考え方でよいのでしょうか?
- 砂質土に支持力は無視して1tfの粘着力をもたせたいとき、単にC=qu/2 、 qu=2kgf/cm2として配合量を決めればよいのですか?
- 薬注のように注入率(セメント配合量)による、原地盤の粘着力増加は考慮しないのでしょうか?(原地盤の粘着力は無視してしまうのですか?)
- 支持力公式のDfの考え方について、改良体の基礎底面下の支持力の検討では、本体工の根入れも含めて改良体深さをDfとし、本体工の基礎底面下の支持力の検討では、Dfを本体工の根入れとするのですか?
- 改良柱の径を決める際、土質、透水係数、一軸強度、N値、施工深度等から留意すべきことはあるのでしょうか?
- 地すべり防止に固化材による改良を行う際、その範囲は強度と範囲の2つを試行錯誤して決めるのでしょうか?
1.前者:Pmax ≦ qa(許容支持力度) = qu(一軸圧縮強度)・後者:Pmax ≦ qa(許容支持力度) = (1/3)αcNc(支持力公式)、qu=2c
「地盤改良マニュアル」(セメント協会)の支持力公式は、「建築基礎構造設計指針」に準じているので、後者の式で算定します。ただし、連続基礎(帯状基礎)では形状係数α=1、改良地盤の内部摩擦角φ=0°では支持力係数Nc=5.3、この場合、後者はqa=(1/3)・1・(1/2)qu・5.3= 0.88quであり、前者のqa=quとあまり差がありません。一般に、セメント系改良地盤はφ=0°として扱うので、概略設計の場合には前者のqa=quを用いても問題はないと考えられます。なお、支持力公式(テルツァーギ、プラントル、マイヤーホフなど、およびこれらの修正)や安全率の考え方は設計基準毎に若干異なるので、まず、どの設計基準書に準拠して設計を行うべきかを明確にする必要があります。私の知っている範囲では以下の通りです。
- 港湾基準:支持力公式;テルツァーギ修正 安全率;Fs≧2.5(重要構造物)
- 建築基礎設計指針:支持力公式;テルツァーギ修正 安全率;Fs=3(長期),1.5(短期)
- 道路橋示方書:支持力公式;プラントル,ソコロフスキー 安全率;Fs=3(常時),2(地震時)
2.通常の設計では地盤をc材(φ=0)またはφ材(c=0)のどちらかに分けて考えます。原地盤砂層が摩擦材料φ材(τf=σtanφ)でも、これにセメントを混ぜると拘束圧によって強度が変化しない粘性材料c材(τf=c)の特性になると考えます。この場合、前述1.後者の支持力公式を用いて改良強度qu(=2c)を求めます。
3.薬液注入の設計における改良地盤のせん断強度τfは、原地盤のc、φに薬液注入による粘着力Δcが付加されたと考えて算出します。改良強度が小さいため、改良地盤としてのせん断強度特性は、原地盤の強度特性に大きく依存しているという考えであり、算出式は以下の通りです。
τf = c+Δc+σtanφ = (1/2)qu・tan(45°-φ/2) +σtanφ
ここで、Δcは薬液注入による粘着力増加であり、ゲル強度と非排水せん断時の土骨格膨張に伴う負圧発生による見かけの粘着力の合計値です。
一方、セメント系地盤改良の設計における改良地盤のせん断強度τfは、原地盤のc、φによらず、セメント混合後の一軸圧縮強度quの1/2としています。 τf=(1/2)qu
セメント系地盤改良のせん断強度に、原地盤のc、φが関係しないのは、モルタルを練る場合に、使用している砂の内部摩擦角φを考慮しないのと同様です。
4.根入れDfは、常に地表面から検討面までの深さですが、Dfが大きくなるほど支持力が大きくなるので、より危険側の検討をするためにDfを考慮しない場合もあります(設計者判断)。
5.機械攪拌式混合の場合の改良柱の径は、現有施工機械の仕様から0.8〜1mが一般的です。高圧噴射式混合の場合の改良柱の径は、薬液注入の場合の改良径の考え方と同様に、ご質問の通り、原地盤の土質特性、施工深度などの他、使用する固化材、吐出圧、貫入・引抜き速度などによって異なります。
6.ご質問の項目の他、改良率(改良断面積/工事面積)も変化させて試行錯誤して決定します。土地の制約、配合試験結果(強度が出ない土質もある)、施工機械の特性、過去の工事実績などを参考にして、制約条件の厳しい項目から決定していきます。
地盤改良後の強度確認について
木造3階建てのロ-ム層の上の盤について、セメント系の地盤改良剤を現場の土に対し200kg/m3混ぜ合わせ支持地盤を造りました。その時点で地盤支持力の試験を忘れ、コンクリ-ト耐圧版を打ってしまいました。後日役所より改良地盤強度を確認し、資料提出を求められています。
耐圧版(t=200)に3カ所大き目の穴をあけ、それぞれ下の改良地盤をコアリングして試験体50φ*100を取り一軸圧縮試験にて3本の平均強度を求めようと考えています。この場合、実際の地盤に置き換えるには、試験結果にどの程度の低減率が必要ですか?
結論から申し上げると、地盤改良後の現地コアサンプリングから得られる一軸圧縮強度は現場強度であり、現場強度=設計基準強度と考えるため、圧縮試験結果に低減率を乗じる必要はありません。現場強度≧設計基準強度であることが確認できれば良いわけです。
低減率(=現場/室内強度比)が必要となる場合とは、設計基準強度(=現場強度)から目標室内配合強度を決定する場合です。低減率は1/3〜2/3程度が一般的であり、施工方法、施工規模、養生条件、過去の実績などを考慮した上で決定します。
施工前調査〜施工後強度確認までの流れは以下の手順で行います。
- 施工前調査および土質試験
- 地盤改良の設計基準強度の決定
- 低減率(現場/室内強度比)を考慮した目標室内配合強度の決定
- 室内配合試験
- 固化材添加量決定
- 試験施工
- 現地コアサンプリングで設計基準強度を満足しない場合は固化材添加量見直し
- 本施工
- 現地コアサンプリングで設計基準強度を満足していることを確認
ご質問のケースは、9.施工後強度確認に当たります。
粘性土のセメント改良でセメント系固化材(一般品)を用いるメリット
粘性土のセメント改良でセメント系固化材(一般品)を使用しました。後に役所から安価な高炉セメントでは無理なの?と聞かれ、実際に配合試験を行った結果、高炉セメントのほうが強度が出てしまいました。一般的に、バラツキのある発生土においてはセメント系固化材の方が有効であると認識していたため、対応に困っています。ただ、高炉セメントは、バラもしくは25kg袋の販売となり、実際の現場での使用には不向きであると思うのですが、ほかにセメント系固化材が有効となる要素があれば教えてください。
ご質問の件については、「地盤改良材のセメント系一般用とセメント系特殊品の違い」も参照して下さい。
高炉セメントはバラもしくは25kg袋の販売しかないとお考えのようですが、フレコン(通常1t入り)もあり、土木工事では、安価な普通ポルトランドセメントや高炉セメントの方が地盤改良材の主流となっています。
軟弱地盤の含水比が大きく、土粒子が細かく、有機物含有量が大きいというセメントの強度発現を阻害する要因と、発生土にバラツキが大きく安定した強度を得にくいということを考慮して、品質を確保するために、最も強度が出にくい発生土に合わせてセメント系固化材を使用したというのであれば多少は使用理由がつきますが、明らかに高含水有機質土でない限り、配合試験なしに固化材を決定するのは危険であると考えています。
軟弱地盤は、砂→シルト→粘土→火山灰質粘性土→有機質土の順に、後者ほど一般のセメントでは固まりにくく、セメント系固化材の適用を検討する必要があります。
一般には下記条件に該当する地盤ではセメント系固化材の適用を検討した方がよいと考えます。
- 含水比w>液性限界wL (一般にw>80%程度)
- 有機物含有量C0≧5% (特にC0>10%程度)
事前混合処理土の土質定数評価方法
発生土(軟弱)を擁壁背面土及び盛土として流用するため、事前混合固化処理を行う事を考えていますが、処理前の土質定数(単重、C、φ)に対して、処理後の土質定数を評価する方法について教えて下さい。
セメント系固化材によって事前混合処理を行った場合、処理土の強度特性(c、φ)を評価するとき、原料土が粘性土である場合と砂質土である場合では大きく異なります。
【原料土が粘性土】
原料土に粘性土を用いた場合の処理土地盤は、設計においては、硬質な粘性土地盤と同様にして取り扱うことができます。よってφ=0であるc−材として評価します。
また、改良地盤の粘着力cは、原材料のc,φによらず、セメント混合後の処理土の一軸圧縮強度quの1/2としています。 c=(1/2)qu
【原料土が砂質土】
一方、砂を原材料とする処理土の場合、セメント改良による粘着力増加が原材料の粘着力に付加されるとともに、原材料が有していたせん断抵抗角も併せ持っている材料と評価します。(c-φ材)
なお、処理土のせん断抵抗角については、セメント改良後に増加する説とほとんど増加しない説とがあり、評価が分かれているのが現状です。
・参考文献
善功企・笠間清伸(1999):「地盤改良技術の変遷と今後の展望−特に固化処理工法について−」、第8回新しい材料・工法機械講習会講演概要−最新の地盤改良工法の現状と設計・施工のポイント−、土木学会、pp47-71
深層混合処理地盤上に直接海洋構造物を設置する際のグラウト材について
深層混合処理をおこなった地盤上に捨石マウンドを設けず、直接ケーソンを据え付ける構造を考えた場合、不陸等に対しグラウト材を充填する必要があるものと考えております。
その材料として、モルタルや高流動コンクリートあるいはベントナイトを混ぜたような材料を使えればと考えております。
どの様な材料が適当であり、その材料強度、透水係数等に関しても併せて教えて頂ければと思います。
捨石マウンドの機能につ、次のように考える事が出来ます。
<必要な理由>
- ケーソン接地圧の均等化、分散化。
- 原地盤の不陸、不等沈下の吸収、なじみの役割。
→支持地盤とケーソン間の緩衝材としての機能。 - 滑動抵抗(摩擦抵抗力)の安定的確保。
- 波浪等による洗堀防止。
<逆にマウンド材がない場合の不具合>
- 接地圧の不均等が生じ、改良地盤への応力集中、およびケーソン底版への応力集中が危惧される。
- 滑動抵抗の確保に不安が残る。
→CDM改良による盛り上がり土、スライムがサンドイッチ状に残り、弱点を形成する。 - ケーソン前面の地盤改良部の洗堀の可能性。
以上のような理由により、捨石マウンドの厚さは防波堤(混成堤)では1.5m以上、重力式護岸では水深に応じて0.5〜1m以上を確保するのが原則となっています。
また、捨石マウンドを設けない場合としては、地盤が岩盤の場合です。基礎岩盤を水平に掘削したり、袋詰めコンクリートなどで凹凸をならします。袋詰めコンクリートの場合は、単位セメント量を300kgf/m3以上とする事になっています。(港湾の施設の技術上の基準・同解説)
ご質問はCDM改良を行なう場合を想定されておりますが、CDMは軟弱地盤の改良工法です。
CDMで改良すると、
- 高改良率の場合は、盛り上がりが生じ、盛り上がり土を撤去する必要があります。
- 表層部は拘束圧が少ないために、相対的に強度が低下することがあります。
CDM改良を岩盤とみなす事は難しいと思いますので、一般的には捨石マウンドを設けるのがよいと思います。どうしても、捨石マウンドが困難な場合は、上記の袋詰めコンクリートと同等のものを適用する必要があると思いますが、こうした構造が成り立つかどうかについては十分な検討が必要であると思います。
詳細な条件が不明のため、一般論での回答になることをご了承ください。
スラリー系深層混合処理工法の未改良部の強度増加について
軟弱な粘土地盤に対し、スラリー系深層混合処理工法を低改良率(ap=20〜30%)で改良した場合、未改良部も若干の強度増加が見込めると思うのですが、何か手がかりになる資料はありませんか。
一般に深層混合処理工法の改良率apは、30〜50%以上が多く用いられています。ご質問のケースは改良率ap=20〜30%ということなのでかなりの低改良です。深層混合処理改良柱体を用いた地盤改良杭としての利用なのでしょうか?
さて、ご質問の回答ですが、未改良部は施工による乱れで強度低下する可能性はあっても、強度増加が見込める可能性は全くないと考えています。
これは、スラリー混合、粉体混合、高圧噴射等の深層混合処理施工方法によらず言えることです。
未改良地盤の強度を増加させる方法は、粘土地盤内の水を圧密工法や載荷盛土などを利用して排水し、含水比を低下させることにつきると考えています。もっとも、人為的に圧密排水を行うこと自体、既に未改良地盤とは呼べず、圧密改良地盤といえます。
深層混合処理工法は、粘土地盤に対して圧密荷重としての応力増加を付与したり、サンドドレーンのように圧密を促進するための排水層(ドレーン材)として働く効果はありません。
ある有効増加応力ΔPにより一次圧密が終了した粘土地盤の強度増加(粘着力増加)ΔCは、強度増加率ΔC/ΔPより算出でき、一般にΔC/ΔP=0.2〜0.3程度と言われています。
なお、港湾基準『港湾の施設の技術上の基準・同解説』ではΔC/ΔP=0.28〜0.30とされています。
路床セメント改良の1層当たり仕上がり厚さ上限値について
路上混合による路床改良を施工し、タイヤローラーなどで締め固め作業を行う場合、その締め固め厚さに上限はないのでしょうか。道路土工指針等によりますと、路床盛土の場合、1層の仕上がり厚さを20cm以下となるように定められていますが、路上混合による改良の場合は適用されないのですか?また、これに対する国交省等からの通達等あれば教えていただきたいのですが。
路床1層当たりの仕上がり厚さを厚くすることは、工期短縮とコスト縮減につながるため、特に大規模舗装工事では常に議論に上がってくる事項です。
参考になるかわかりませんが、1992年6月から施工された関西国際空港滑走路舗装工事では、スタビライザーを用いたマサ土セメント安定処理による路床厚40cmの施工に、
- 8t級振動ローラでは、1層当たり仕上がり厚さ20cm×2層転圧
- 18t級振動ローラでは、1層当たり仕上がり厚さ40cm×1層転圧
という施工実績もあります。
つまり、締固め能力の高い振動ローラを用いれば、道路土工指針等による「路床盛土の場合、1層の仕上がり厚さを20cm以下とする」という定めを遵守しなくてもよいのではないかと考られます。ただし、路床仕上がり厚さを厚くしても、仕上がり厚さ20cmの場合と同等の締固め効果が得られることを立証しておく必要があります。
締固め能力の高い大型振動ローラ(30t級)を用いることで、通常は1層当たり30cm厚で仕上げている盛土を、1層当たり60cm厚で仕上げることが可能となり、工期短縮とコスト縮減を謀った施工例もあり、弊社が施工している「第二東名高速道路加瀬沢工事」でも採用されています。
上記工法は、第二東名高速道路を2010年までに開通するためには、締固め層厚60〜90cmを締固めできる強力な振動ローラが必要ということで、日本道路公団とゼネコン16社及び機械メーカー2社による共同研究「大型締固め機械による厚層締め試験」の成果であり、1998年以降の発注工事では、盛土1層当たりの締固め厚さを60cm以上とする施工指針が採用されています。
バックホウ混練によるセメント処理施工厚さについて
バックホウを使用しセメント処理を行いたいのですがバックホウで施工できる範囲を教えて下さい。
バックホウ混練によるセメント処理(表層固化)を行う場合の施工最低厚さについてとのことですが、一般にバックホウによる混練は最も表層改良の簡易な方法として、小規模改良の場合によく使用されています。が、非常に簡易な施工であるため、逆に混練効率(回数)や一層当りの施工厚さ等に、きちんとした管理基準が無いという状況です。
過去の事例では、舗装下部の路床の安定処理としてバックホウ混練+10tマカダムローラ転圧による表層改良を行って、20cm+13cmの2層で改良された事例があります。
この事例では時間20m3を基準歩掛かりとして、土および固化材の色が単独で認められない程度まで撹拌を行うということを施工管理基準としています。(参考文献:セメント系固化材による地盤改良マニュアル(第二版)、(社)セメント協会、技報堂出版)
施工厚さについては、バックホウによる混練の場合、一般的にはバケットの高さ程度以内の深さで施工される場合が多いのではないかと思います。
特殊な事例として、流動状の泥土の場合、ピットや土運船内で固化材を投入してバックホウによる混練を行う場合がありますが、この場合はアームの油圧部が泥土に入らない範囲で数m程度の深さまで撹拌する場合があります。
バックホウによる混練は、あくまでも簡易的な手法であって、専用の機械、例えばスタビライザなどに比べると混練効率、品質が劣ります。一般的に室内試験で配合設計を行う際に、(現場/室内)強度比(室内の理想的な配合試験に比べて現場の施工のバラツキにより強度が低下する割合)は0.5程度(0.3〜 0.7)の値が取られる場合が多いようです。
路床の一層当たりの転圧厚さは、20cmですか、30cmですか
石灰処理と石粉を建設発生土に混ぜて路床に使おうと思っているのですが、Fe石灰のように弾性理論で多層構造として設計するのか、又は、セメント系安定処理のようにスラブとして設計するのか教えて下さい。また、石灰安定処理は転圧1層当たり 20cmか、30cmかも、教えて下さい。
路庄の締め固めに関して、いくつか文献を調べてみましたが、石粉等を用いた場合に関する記述は見つけられませんでした。
このため、根拠のあるものではありません。一つの意見としてお考えください。
セメントや自硬性のあるスラグなどの材料でしたら、スラブ的な考え方ができると思います。
自硬性の無い材料では、弾性理論で多層構造として設計するのではないでしょうか?
『道路土工』の記述では安定処理した材料に関しても一層の仕上がり厚さが20cm以下になるようにするという記述がありますので、ご質問に対しては、20cmが一般的だと考えます。
なお、『JHの設計要領』には、締め固め層厚に関して、以下のような記述があります。
粘土地盤に石灰を混ぜた安定処理土に関しては、遅硬性があること、このような安定処理土に関しては、十分な性能が得られることを確認した上で、20cm以上の仕上がり層厚をとってもよいこと(2-42項)
浅層混合処理工法における施工後強度確認は何ヶ所行うべきでしょうか
RC2階建てを建設するために、100m3程度(W9m×L6m×H2m)の攪拌地盤改良を計画しています。施工後の強度確認を行うにあたりどの程度試験をすれば適切か、苦慮しております。
- 今回の場合、施工後強度確認は何ヶ所行うべきでしょうか?(3本/ヶ所)
- 個所数を決めるにあたり、施工規模(m3・m2当り)等による目安は無いのでしょうか。
- 1ヶ所当り3本のコア採取位置について取り決めは無いのでしょうか(上層、中層、下層等)
建築工事におけるセメント系地盤改良の設計及び品質管理は、国土交通省より、『建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針 −セメント系固化材を用いた深層・浅層混合処理工法− (財)日本建築センター』を参照することが勧められています(以下、指針)
ご質問の地盤改良は、改良層厚2mであり浅層混合処理工法にあたります。上記指針には小規模建築物(地上階3階以下、建物高さ13m以下、軒高9m以下、延べ面積500m2以下の全てを満足する建築物)における浅層混合処理工法の品質管理について以下ように記載されています。
『採取コアによる一軸圧縮試験で品質検査を行う場合、1検査区から3箇所コアを採取(供試体数9本)し、9本の供試体の全てが設計基準強度Fcを上回れば、築造された改良地盤は、90%以上の確立で不良率が20%以下であることを保証できる。1検査区当りのコア採取は3箇所程度とし、供試体の全てが設計基準強度Fcを上回れば、1検査区の品質を合格とする。検査区は建物規模、改良規模、地盤条件、施工条件等を考慮し適切に決定する。』
さて、ご質問の回答ですが、
Q1.今回の場合、施工後強度確認は何ヶ所行うべきでしょうか。
A1.ご質問の建築物は小規模建築物であり、1改良範囲を1検査区とし、1検査区当り3箇所(供試体数9本)または4箇所(供試体数12本)のコア採取を行うべきと考えます。
なお、指針には以下の品質管理例が紹介されています。
- 改良範囲:W 6m×L12m×H1.5m ⇒ 1検査区とし建物の4隅でコア採取
- 改良範囲:W13m×L16m×H1.0m ⇒ 1検査区とし建物の4隅でコア採取
Q2.個所数を決めるにあたり、施工規模(m3・m2当り)等による目安は無いのでしょうか。
A2.浅層混合処理工法における品質検査数量の規定については、『改良面積○m2を1検査区とし、1検査区当り○箇所のコア採取を行い・・・』というような明確な記述はないようです。
ただし、指針には『延べ面積500m2以下の小規模建築物の深層混合処理工法における品質検査数量は、3箇所以上のコア採取、1箇所当り3供試体以上採取』という旨が記述されています。浅層混合処理工法の場合も、この規定に従って良いものと考えています。
Q3.1ヶ所当り3本のコア採取位置について取り決めは無いのでしょうか(上層、中層、下層等)。
A3.指針には『小規模建築物の深層混合処理工法において、改良厚3m以下で、かつ改良対象層が同一地盤と見なせる場合は、深度コアの採取を省略して良い』という旨が記述されており、浅層混合処理工法におけるコア採取深さの取り決めも、これに従い、上層1m程度から採取した頭部コアで品質管理を行っても良いものと考えています。
地盤改良時の六価クロム対策としてセメントに代用できる添加材はありませんか
軟弱粘性土(分類CH、N値<2、自然含水比51%、液性限界61%、層厚H=3.5m程度)上に側道縦断BOX及び本線の盛土(盛土高H=8m程度)を構築する計画があります。通常であればセメント安定処理による表層混合改良を計画する範囲であると思われますが、六価クロムの関係でセメントを使用することができません(特殊土用も不可)。良質土による置換えにしようと思いますが、発生する粘性土を現場内で処理を行い盛土に転用する必要が生じ、工期等の問題があります。そこで、以下のことを教えて下さい。
- 参考までにセメント内の六価クロムの溶出過程と影響範囲。
- 地盤改良の場合、セメントに代用できる添加材等(石灰・石膏・高分子材料等)があれば、材料と得失。
- 発生土転用の場合、発生土の処理方法や固化処理の場合の添加材等。
1.六価クロムについて
(1)六価クロム
セメントはその製造過程で高温・酸化雰囲気となるため、天然の三価クロムの一部が毒性の高い六価クロムに変化します。六価クロムは水に対する溶解度が高いため、雨水等の地下浸透とともに地下に拡散することがあります。六価クロムは化学的に不安定で、酸性溶液中や有機物の存在下で容易に毒性のない三価クロムに還元されるため、各種還元剤が販売されています。
(2)溶出特性について
土のもつ酸化、還元雰囲気が六価クロムの溶出に影響します。火山灰質土(関東ローム、シラスなど)では普通ポルトランドセメントやセメント系固化材(特殊土用と呼ばれるもの)を使用すると環境基準を上回る例があります。粘性土・砂質土・腐植土では、還元性雰囲気にある地下水位以深より、酸化性雰囲気にある地下水位以浅の方が溶出しやすい傾向にあります。また、火山灰質系の土に代表されるやや赤い色調の土のほうが、地下水位以深にあるやや青い色調の土より溶出し易い傾向にあります。アルカリが高くても溶出濃度はあまり変化しませんが、pHが12付近を超えると溶出濃度が急激に増える可能性があります。
2.セメントに代用できる添加材
(1)六価クロムを抑えつつ盛土材としての必要な強度を得ることができる固化材を紹介します。
| 添加材 | 概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| 高炉セメント+溶出抑制剤 | 六価クロム(Cr+6)の溶出が少ない高炉セメントと溶出抑制剤を併用する | ○安価で強度発現が高い。 ●養生を数日以上必要とする ●攪拌を均一化させるためにプラント等の使用が必要 ●改良土は高アルカリになり、再利用時には覆土等の対策が必要な場合がある |
| 石灰系固化材 | 一般的に農地等に用いる消石灰と水和反応して水分を蒸発させる生石灰がある。アルカリ性を示す | ○養生により第4種以上の改良土に改質可能 ○生石灰の場合、発熱により強度発現が早い ●改良土は高アルカリになり、再利用時には覆土等の対策が必要な場合がある ●生石灰を使用する場合、水和反応により発熱するため材料の保管などは雨水対策を十分に行う必要がある |
| 石膏 | 中性で強度発現の早い石膏から弱アルカリで比較的安価な石膏と幅がある | ○短時間(3時間程度)で第4種以上の改良土に改質することができる ○アルカリ汚染の問題がない ○改良直後に運搬可能なため、仮置場の必要面積が削減できる ●他の固化材と比較して高価 |
(2)発生土を改質する添加剤として我が社で主に使用しているものを紹介します。
| 添加材 | 概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| 水溶性ポリマー | 土中の水分を凝集し、セメントとの併用により泥状から粒状に改質可能。改質直後よりハンドリングに優れる | ○安価で強度発現の高いセメントを使用できる。 ○配合や高分子材等の併用により第2種改良土以上にすることが可能。 ●養生を数日以上必要とし、初期の段階で降雨に曝されると再泥化の可能性あり。 ●攪拌を均一化させるためにプラント等の使用が必要。 ●改良土は高アルカリになり、再利用時には覆土等の対策が必要な場合がある。 ○改良直後に第4種改良土に改質でき、ダンプ運搬可能となる |
| 古紙 | 自身の約10倍の水分を吸収し、泥状の土のハンドリングを改質する。また古紙自身のせん断により初期強度が高くなる | ○改良直後に運搬可能なため、仮置場の必要面積が削減できる。 ○廃棄物(古紙)の有効利用を促進できる。 ●古紙の散布にあたっては、飛散対策を要する。 ●材料費が高コストになる可能性がある |
3.盛土材へリサイクルする処理方法
当社では高含水比の建設汚泥や浚渫土を2〜3分で粒状に改良する「建設汚泥リサイクルシステム」があります。本システムでは専用のプラントに泥状の土を投入後、水溶性ポリマーを加え汚泥の見かけの含水比を低下させた後、セメント等の固化材を加え攪拌し、造粒固化を行います。特徴としては、
- 脱水・乾燥の前処理を必要とせずに短時間で砂と同等の性状に変化。
- 早期運搬、利用が可能。
- 粒状になるため、多様な用途に利用可能。
概要は当社ホームページの保有技術でみることができます。
http://www.penta-ocean.co.jp/business/tech/environment/soil/dirt_recycle.html
その他、古紙による改良工法「吸水材混合処理工法」も保有しております。
DJM改良地盤上の盛土法尻付近に民家があるのですが
N値0〜O粘性土上に最大高さ12mの盛土計画があり、接民家への影響を考慮して盛土下にDDJM行います。FEM形解析で宅地の変状を抑制するために必要な改良柱体の変形係数((E50)求めました。また、盛土の支持という面から複合地盤として必要な柱体のquも求めました。このqu時の変形係数は宅地変状抑制に必要な変形係数よりも低いので設計上はquとE50の両方を満足するセメント系固化材添加量を設定しようと思うのですが、発注者は「変形係数で規定されるのは経験が無い、本を読んでも事例が無い」とのこと。私の考え方は間違っているのでしょうか。本当に変形係数がkeyとなるような事例はないのでしょうか。
軟弱地盤を深層混合処理工法の一つであるDJM工法で改良し、その上に12mの盛土を行う計画となっているが、盛土の法尻付近に民家があり、盛土による地盤変形の影響が懸念されるということですが、通常、深層混合処理による改良柱体の設計は、以下の手順で行います。
- 改良仕様の仮定(強度,範囲、深度、改良率)
- 円弧すべり検討 (2'. 側方変位検討(FEM解析)・・・・変位量に制約がある場合のみ)
- 支持力検討
- 沈下量検討
- 改良仕様の決定
参考文献:
『陸上工事における深層混合処理工法 設計・施工マニュアル、平成11年6月、(財)土木研究センター』
http://www.pwrc.or.jp/oldnews/wnew0108.html#010
FEM解析については、p99〜103を参照
ご質問の内容としては、
A.2'側方変位検討から必要となる変形係数を算出し、設計基準強度quを設定
B.3支持力検討から必要となる設計基準強度quを設定
上記A、Bの大きい方のquを設計基準強度として、Aを採用することにした。
ということですが、考え方は間違っていないと思います。
ところで、設計の必須項目である2円弧すべり検討は行ったのでしょうか?
地盤と構造物の相互作用は複雑であり、土質条件、境界条件、構成式、施工過程モデル化手法、メッシュの切り方等によって答えが変わるため、一般化されたFEM設計手法はなく、FEM解析を用いても信頼性のある結果が得られる保証は十分とは言い切れないのが現状です(未だ研究段階の点も多い)。しかし、より詳細な検討を行うためには、FEM解析が必要不可欠となります。
つまり、FEM解析は万能ではないことをよく認識することが大切です。この万能ではない部分を補うのが、観測施工や、過去の実測例や、実験結果等に基づく工学的判断であると考えています。
ご質問のケースは、盛土の法尻付近に民家があるという状況であるため、安全面から考えて、特に慎重に設計を行う必要があり、発注者がFEM解析結果を鵜呑みにできないことは納得できます。
FEM解析結果をそのまま設計に反映する際には、ぜひ、盛土を行う過程で地盤変形の観測を行い、早期に危険を察知し、対処できるような施工計画(観測施工)を立案することをお勧めします。
セメント(系固化材)の固化阻害成分について
セメント(系固化材)の固化阻害成分について教えてください。どのような土に含まれるのか。どうして阻害されるのか。難しく説明していただいても分からないと思いますので、簡単にお願いします。
セメント(系固化材)の固化阻害成分が、どのような土に含まれるか、ということですが、固化の阻害成分は「フミン酸」、「フルボ酸」、「タンニン酸」などの有機質分が代表的なものとして挙げられます。
これらは主として腐植の成分であり、「高有機質土」と呼ばれる、過去に植物の繁茂→枯死を繰り返して腐植を大量に含む土層(開墾地、休耕田の表層など)等に多く見られます。当然、寒冷地の泥炭(ピート)もこれの代表的なものです。
また、どうして阻害されるかということですが、上記のフミン酸などの有機分が多いと、これがセメント中のカルシウム分と反応して、不溶性の「フミン酸カルシウム」などを生成し、これが未反応のセメント粒子を覆ってしまうために、セメントの水和反応が阻害されることが原因であるといわれています。
このような土質に対しては、専用の「高有機質土(泥炭)用」のセメント系固化材が別途販売されていますが、このような固化材を使用するとしても、一概に必ず強度が発現するとは言えないため、事前に配合試験を行うことが賢明であると思います。
地盤改良の種類と概算工事費
地盤改良の種類とその概算工事費を教えて頂けないでしょうか?
一般的な地盤改良工法ですが、相手の土が粘性土の場合と砂質土の場合で、工法が大別されます。
緩い砂地盤の場合、通常の状態では、何ら問題がありませんが、地震時の液状化を防ぐ目的で改良します。
下記に、大まかな施工方法を示します。実際の施工では、各項目ごとに具体的な工法があります。
■軟弱な粘性土の場合
- ドレーン併用載荷盛り土工法
粘性土中にドレーン材を挿入して、盛り土します。
1m3当たり、300円〜1000円程度 - 固化処理工法
土中にセメントなどの固化材を入れて、攪拌します。
1m3当たり、10000円〜50000円程度 - 強制置換工法
粘性土中に砂杭等を圧入して、粘性土を砂に置換します。
1m3当たり、2000円〜4000円程度
■軟弱な砂質土の場合
- 強制締め固め工法
砂杭を強制的に砂質地盤中に押し込み/転圧する事で強固な地盤を造ります。
1m3当たり、2000円〜4000円程度 - 固化処理工法
土中にセメントなどの固化材を入れて攪拌します。粘性土の場合と同じ方法です。
1m3当たり、10000円〜50000円程度 - 排水工法
砂質土中にドレーン材を入れて、地震時の液状化の原因となる過剰間隙水を排水します。
1m3当たり、3000円〜6000円程度
各工法の価格は、必要な強度や施工方法、場所などいろいろな条件で異なります。あくまで参考程度にして下さい。また、地盤工学会などに『地盤改良』に関する参考図書がありますので、そちらを参考にされるのも良いと思います。
軟弱層中間までの地盤改良でL型擁壁の安定は保てますか
田畑部でL型擁壁を計画していますが、支持層(軟岩?)まで基礎底面から3.0 m程度あります。上層は平均N値8程度の砂質土です。支持層まで地盤改良するにはコストの面で問題があると判断し、軟弱層の中間まで地盤改良し、地中内の分散に期待する工法を選択しました。この考え方は強制置換工法にも適用できますか。
ご質問の件ですが、確かに支持層まで深い場合、応力の分散を考えて地盤改良を一定深度で止めることはあります。強制置換の場合も同じ考えが可能です。
このとき注意が必要なのは3点です。
1)改良底面での支持力のチェック
この場合、地盤改良の底面で十分な支持力が確保されることが条件となります。L型擁壁ですから、背面から土圧が作用し、地盤改良の底面の接地圧は、前側の方が後ろ側より大きくなるので注意が必要です。
2)地盤改良底面より下部での円弧滑りの検討
L型擁壁ですから、背面より土圧を受けるので円弧滑りによる安定検討が必要です。この時、地盤改良より下を通る滑り面について円弧滑り計算を行い、一定の安全率を確保していることが必要です。
強制置換を行う場合、上記の2つの方法で改良深さを決定します。
3)長期的な沈下
ご質問には明示されていませんが、仮に改良層より下が粘土層の場合には、L型擁壁の荷重は分散するとはいえ、長期的な沈下が発生します。L型擁壁の高さも重要ですが、この沈下がどの程度であり、構造物に影響を与えないことも確認する必要があります。
擁壁背後のセメント固化改良による土圧軽減効果について
傾斜地ある高さ2.5m程度の既設擁壁を改良する事になりました。背後の地盤はN値18〜 12の砂質土ですが、擁壁の端趾圧と地耐力を検討したところ、若干地耐力が足りません。対策として、あるメーカーは「背後地盤をセメント撹拌により改良して土圧軽減をはかるべし」と主張するのですが、セメント撹拌による背後地盤改良は内部摩擦角の向上や土圧係数の低減など、擁壁背後の土圧軽減に効果があるのでしょうか。
砂質土をセメント系地盤改良したとき、その改良土は、セメント改良による粘着力が付加されるとともに、原地盤が有していたせん断抵抗角も併せ持っている材料として評価することができます。
しかし、改良土のせん断抵抗角については、セメント改良後に増加する説とほとんど増加しない説とがあり、評価が分かれているのが現状です。
よって、内部摩擦角の向上は期待できませんが粘着力の増加による土圧係数の低減の効果はあるでしょう。
ただし、既設擁壁の背後をセメント攪拌したときに、固化前において地盤を攪拌することによる流動圧が擁壁に作用しますので、擁壁が前面にはらみ出すおそれがありますので、その検討を行う必要があると考えられます。
また、背後地盤の水平土圧低減によって端趾圧を抑え、地耐力を確保する方法は、どちらかというと二次的な対策方法であり、擁壁の地耐力が足りない場合において最も効果的な対策としては、擁壁背後の荷重の軽量化があげられます。擁壁背後の荷重の軽量化方法として、例えば、
- 軽量混合処理土
- 軽量モルタル
があげられます。
<1.軽量混合処理土>
現地発生土に安定剤と気泡または発泡ビーズを混合して軽量な地盤に置き換える工法であり、約10,000円/m3です。本工法の場合、プラントをもちいて軽量処理土を作成するので、処理土プラントを置くためのスペースの確保が必要となります。また、プラントの費用を考えると対象数量が大きい場合には適しているでしょう。
<2.軽量モルタル>
擁壁背後の地盤を軽量モルタルで置き換える工法であり、約10,000円/m3です。この場合プラントは不要ですが、現地盤を軽量モルタルと置き換えるために排土の処理が必要となります。
また、背後地盤のセメント攪拌のほかに擁壁背後の土圧低減する方法としては、掘削した発生土に固化材を添加して埋戻す方法があります。
浅層混合処理工法の最低改良厚さについて
地盤改良の厚さを計算する場合、一般に改良層下面で支持力計算を行うと思いますが、改良強度によっては計算上10cmの厚さでもよい場合があると思います。改良厚さの最低値について基準や計算等はあるのでしょうか?
ご質問の地盤改良は浅層混合処理工法と考えて回答を進めます。
浅層混合処理工法の改良仕様(範囲、厚さ、強度)は、単に設計計算で決定するのではなく、施工法(施工機械のトラフィカビリティは得られるか)、安定した品質が得られるか、構造物の重要度、工期に余裕はあるかなど様々な要因を考慮した上で比較検討を行い、最終的には最も経済的な改良仕様となるように決定します。
土質条件が現場ごとに千差万別のように、最適な改良仕様も現場ごとに異なります。
冒頭で改良仕様は「単に設計計算で決定するのではない」と述べましたが、「詳細に検討すれば、ほぼ設計計算から決定可能」と考えています。円弧すべり計算や改良地盤内部応力照査(圧縮、引張り、せん断応力)のみから改良仕様を決定しようとしても、改良強度を大きくすれば、改良厚さが小さくなるという反比例関係が得られるだけで、ご質問のように「強度を大きくすれば改良厚さは10cmでもよいのか」という疑問を抱くかもしれませんが、強度発現は可能か、改良地盤下面での支持力、沈下に問題はないかなどを検討することで改良厚さが決定される場合が大半であると考えています。原地盤が岩盤や十分に締まった砂礫層でもない限り、改良厚さが10cmでよいということにはならないのではないでしょうか。
なお、最低改良厚さの基準はないのではないかと考えています。
以下に設計、施工、強度の留意点および参考文献を示します。
■設計
1.支持力
a)極限設計法
一般に基礎底面からの荷重分散角30°を考慮して、鉛直荷重を分散し、改良地盤下面での支持力照査を行います。鉛直荷重の算定にはブーシネスクの地中応力算定公式を用いる場合もあります。改良地盤内部応力は一般にパンチング破壊(押抜きせん断)等で検討を行います。
b)地盤係数法
弾性床上の梁とも呼ばれる解析法です。改良地盤を弾性地盤に支持された梁部材と見なして、改良地盤内部応力の照査を行います。地盤が軟弱(例えば、粘着力c<1tf/m2)な場合や、改良厚さが薄い場合の改良強度は、せん断強さよりはむしろ曲げ強さで決定される場合が多いので、せん断応力、曲げ応力、沈下を同時に検討できる本解析法が一般に用いられています。また、詳細検討が必要な場合には有限要素法が用いられる場合もあります。
2.円弧すべり
擁壁や盛土などでは、改良範囲、厚さ、強度を変えながら円弧すべり破壊の検討を行う必要があります。
3.沈下
原地盤が粘性土の場合には、改良厚さを変えながら、圧密沈下量が許容値に収まるように検討を行う必要があります。
設計では上記1〜3の全てを満足する必要がありますが、明らかに地盤が良好な場合には検討を省略したり、地盤が粘性土で軟弱な場合には上記以外に側方変位の検討を要したりします。
■施工
- スタビライザ混合 改良厚さ 0.2〜2.0m
- バックホウ混合 改良厚さ 0.5〜3.0m
- ロータリー式混合 改良厚さ 0.5〜4.0m
- 柱状撹拌混合 改良厚さ 2.0〜6.0m(深層混合処理の場合は〜40m)
上記改良厚さは、あくまでも目安です。改良単価は、原地盤1m3当り2000〜7000円程度。
■強度
一般的な改良強度は一軸圧縮強さqu=100〜1000kN/m2程度で設定しますが、改良後に掘削や杭打ちなどを行う場合には500kN/m2以下に抑える場合もあります。また、原地盤が高有機質土や高含水土の場合には、セメントを添加しても十分な強度が得られない場合もあり注意が必要です。
■参考文献
- 『セメント系固化材による地盤改良マニュアル(第二版)、(社)セメント協会』
- 『建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針 −セメント系固化材を用いた深層・浅層混合処理工法−(財)日本建築センター』
建築工事においては、国土交通省より上記を参照することが勧められています。
セメント固化改良の材令7日強度から材令28日強度を推定できますか
高炉Bを用いて、室内配合試験を行い、材令7から材令28強度を推定しようと思います。粉体の場合とスラリーの場合について教えてください。
セメント系改良土についてのご質問と思いますが、室内配合試験でスラリー添加と粉体添加を行った場合、最終的な改良土内の土と水と固化材の構成が同じであり、十分に混練されているならば、材令7日と材令28日の強度比に添加方式の影響はないと思われます。
いろいろな文献を調べてみると、材令7日と材令28日の強度の関係については、
qu28=1.2〜2.3×qu7
と非常に幅があり、試験条件(セメント種、原料土の物性など)によって影響を受けると思われます。
(財)沿岸開発技術センターから発行されている「深層混合処理工法技術マニュアル」のp.133に、海底土を対象とした室内安定土の固化材の違いによる材令間の強度関係をまとめており、
- qu28=1.56×qu7(高炉B種を用いた場合)
- qu28=1.49×qu7(普通ポルトランドセメントを用いた場合)
と記載されていますが、バラツキの多いデータとなっております。
また、弊社で実際に浚渫粘土に高炉セメントB種をスラリー添加したセメント系改良土の室内配合試験結果からは、
qu28=1.6×qu7
という結果が得られております。
室内配合試験の材令規定について
基本的に室内配合試験の結果は、7日での配合試験結果だと聞いたのですが、どこかにそうゆう文献が存在するのでしょうか?
必ずしも材令7日が配合試験結果とは限りません。
深層混合処理工法などのセメント系固化材を用いた地盤改良工法では、一般的に材令7日と28日にて試験を行うことが多いですが、材令7日の時点では、まだ強度発現の途中なので、材令7日の強度は、材令28日の強度や、長期的な最終強度に比べて小さいことを考慮して評価する必要があります。
(財)沿岸開発技術研究センターから発行されている「深層混合処理工法技術マニュアル」では、室内配合試験の例として材令7日と28日が一般的であると記述してあります。
地盤改良において室内配合試験を行う際には、設計条件などから、室内配合試験の目標強度を設定しますが、使用する固化材の種類によって強度の発現性が異なりますので、目標強度と共に、地盤改良の用途や施工条件に応じて材令を設定し、配合試験を行うことが重要です。(例として、3日後に重機が載るなどの仮設としての地盤改良の場合などは材令3日で試験を行ったほうがよいなど。)
建設汚泥を造粒固化する際の溶出試験用試料採取について
杭工事等に伴う建設汚泥を、固化材を用いて造粒固化しようとした際に
Q1.杭工事では一般に掘削が深く、複数の土層(土質)を掘削する。その際の、配合設計の段階で実施する溶出試験用の試料は、事前にボーリング等でサンプリングしなければならないのか?
Q2.杭工事による添加物(ベントナイト)等が改良する土に混ざる場合に、配合設計の段階で実施する溶出試験用の試料はどうしたらいいのか?
以上2点について教えてください。
A1.理想的なケースでは、杭工事前の地盤調査や他の工事・工種より得た土を使用して事前に配合・溶出試験を行います。しかしそれができないケースでは土が発生すると同時に配合・溶出試験を行います。
仮置き場が確保できる場合は結果を確認してからプラントを整えますが、汚泥を早急に処理したい場合は、発注者に確認を取った上でプラントを持ち込み、改良物を溶出試験に出します。
溶出試験結果に不安がある場合(土が汚染されている可能性がある)は事前に試験をする必要があります。
A2.ベントナイトは環境に悪影響がないので別途検討する必要がありません。
弊社でも実績があり、また「建設汚泥リサイクル指針」にも同様のことが書かれています。
石炭灰による地盤改良の強度設定について
石炭灰を用いた地盤改良工事を予定しています。「セメント系固化材による地盤改良マニュアル」によると、「改良地盤系においては構造的に不連続となるため、改良層はできるだけ原地盤の工学的特性に近い土構造物とすることが望ましい。このため、改良土の強度をあまり大きくしないで、改良土のひずみレベルを未改良土のそれに近づけ、改良土から未改良土へできるだけ連続性をもたせた構造形式とすることが望ましい」とあります。
石炭灰有効利用の観点から、石炭灰の配合量はできるだけ多い方が望ましいのですが、石炭灰の配合量と強度は比例関係にあるので、多く混合するとそれだけ強度が大きくなり、前述の連続性を持たせることは困難となります。そこで、以下の2点について教えて頂きたいのですが、よろしくお願いします。
Q1.構造的に不連続(つまり、改良土と未改良土の強度に大きな差がある)となった場合、具体的にどのような事象が発生するか?
Q2.改良土の強度の上限はどの程度か?
ご質問のとおり、「セメント系固化材による地盤改良マニュアル」には、浅層改良設計の基本的な考え方として、改良土と未改良土の強度特性の連続性を極力保つことが望ましいと記述されています。
一般に、浅層混合処理地盤の設計断面は、改良土の曲げ強さで決まり、設計手法としては、せん断応力、曲げ応力、沈下を同時に検討できる地盤係数法がよく用いられています。
地盤係数法は弾性床上の梁とも呼ばれる解析法であり、改良地盤を弾性地盤に支持された梁部材と見なして、改良地盤内部応力の照査を行います。
改良地盤の厚さが異なっていても、構造的に同じ剛性(EI)の場合、例えば、
強度が大きくて(Eが大きくて)、改良厚が薄い(Iが小さい)場合と、
強度が小さくて(Eが小さくて)、改良厚が厚い(Iが大きい)場合には、
改良地盤に作用する、せん断力、曲げモーメント、沈下量は等しく算出されます。
改良地盤内部応力としては、前者の高強度で薄い改良の方が、後者よりも大きな、せん断応力度や曲げ応力度が発生します。
「地盤改良マニュアル」には、「同じ剛性(EI)であれば、改良土の変形係数(E)を小さくして、断面形状の厚い、断面二次モーメント(I)を大きくする設計がよい。」と記述されていますが、この背景には、地盤改良は物性のバラツキが大きな原地盤を対象としたものであるため、JIS規格のコンクリートなどと比較すれば、強度のバラツキも大きく、また、施工上の打継目によるクラックの発生なども考慮すると、強度に依存した薄い梁部材としての設計にはリスクが伴うという考えがあるものと思います。
さて、ご質問への回答ですが、
Q1.構造的に不連続となった場合、具体的にどのような事象が発生するか?
A1.改良土と未改良土の強度に大きな差がある場合には、以下の2通りの事象が考えられます。
(1) 剛性に余裕が小さい場合(高強度で薄い改良の場合)
改良地盤が割れると、梁部材としての曲げ剛性が急激に低下し、未改良土がクラックからうみ出してきたり、地表面が陥没したりする可能性があります。特に接地圧の大きな重機走行時に注意を要します。
(2) 剛性の余裕が大きい場合(高強度で厚い改良の場合)
支持力上は、特に問題は発生しないと考えられますが、未改良地盤が圧密未了地盤などで広域の沈下が発生する場合には、浅層改良地盤が沈下に追従しないことによって改良地盤下部に空洞が発生したり、改良地盤と未改良地盤をまたぐ構造物では不同沈下が問題となる可能性もあります
Q2.改良土の強度の上限はどの程度か?
A2.強度の上限規定は特に無いと思いますが、一般的な改良強度は一軸圧縮強さqu=100〜1000kN/m2程度で設定します。また、改良後に掘削や杭打ちなどを行う場合には、施工性を考えて、quを500kN/m2以下に抑える場合もあります。
石炭灰有効利用の観点から、石炭灰の配合量はできるだけ多くしたいということですが、繰り返しになりますが、後々、掘削や杭打ちなどを行なう予定が無く、広域沈下の心配のない場所であれば、大量の石炭灰で固めた剛性の高い地盤を造成しても問題は発生しないものと思います。
浅層改良下面での支持力照査に改良体の自重を考慮するべきか
擁壁およびボックスカルバートなどの基礎地盤に浅層改良を行う場合の設計についての質問です。改良の厚さを決定する場合、「道路土工 擁壁工指針P110〜112」に準じれば、『荷重による地中応力度が軟弱地盤の許容応力度以下となる深さまで軟弱層を改良する』とあり、地中鉛直応力の算出式も記載されておりますが、この式では改良体の自重は考慮されていません。改良体の自重は考慮しなくても良いのでしょうか?
直接基礎下部の軟弱地盤を浅層改良する際、軟弱地盤が厚く、支持層が深い場合には、荷重による地中応力度が軟弱地盤の許容支持力度以下となる深さまで改良を行います。
「浅層改良下面での支持力照査に改良体の自重を考慮するべきか」というご質問ですが、以下の2通りの考えがあると思います。
(a) 地中応力に改良体自重を考慮し、許容支持力に根入れDfを考慮する。
(b) 地中応力に改良体自重を無視し、許容支持力に根入れDfを考慮しない。
設計法が、根入れのある直接基礎の支持力照査と同様であることを考慮すれば、「(a)自重を考慮する」と考えるのが一般的ではないかと思います。改良体自重を考慮した設計例は、以下の指針にも記載されています。
『建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針−セメント系固化材を用いた深層・浅層混合処理工法− (財)日本建築センター』
「道路土工 擁壁工指針」には、基礎下面から分散角30°を標準として浅層改良下面までの荷重分散を考慮して地中鉛直応力度σzを算定する方法が紹介されていますが、このσz は基礎築造に伴う地中鉛直応力度の増加分であるため、(a)自重を考慮する場合には、改良体自重γ2・Dfを加味して、支持力照査は以下の通りとなります。
地中鉛直応力度q=σz+γ2・Df ≦ 許容支持力度qa
補足ですが、浅層改良のように改良前と改良後の土の単位体積重量γ2がほぼ等しく、地盤の内部摩擦角φが小さい場合には、(a)と(b)のどちらの検討方法を用いても検討結果に大差は生じません。 理由は以下の通りです。
極限支持力算定式において根入れDfが含まれる項は、上載圧項(Nq項)です。上載圧項は、φ=0°(粘性土など)の場合に、Nq=1であり、最も小さな値 γ2・Df・Nq=γ2・Df になります。
このγ2・Dfは、根入れ深さよりも上の土の重量に相当しますが、極限支持力の内、根入れ深さより上にある土の重量γ2・Dfは、もともと、その深さの地盤が支えていた重量であるため、安全率によらず確実に期待できる支持力と考えるのが一般的です。
もう少しわかり易く言えば、掘削した土をそのまま埋戻しても、埋戻土の重量で掘削底面が破壊することはなく確実に支持できるということです。この場合、支持力照査は以下の通りとなります。
地中鉛直応力度q=σz+γ2・Df ≦ 許容支持力度qa=1/Fs・(α・c・Nc)+γ2・Df
γ2・Dfを消去すると、以下の通りとなります。
σz ≦ 1/Fs・(α・c・Nc)
つまり、地中応力に改良体自重を無視し、許容支持力に根入れDfを考慮しない(b)の検討方法と等しくなります。
港湾、道路、鉄道、建築など各技術基準に示されている極限支持力算定式は、支持力係数の値が異なるなどの若干の違いはあるものの、本質的には変わりません。
ところが、極限支持力quから許容支持力qaを設定する場合の、安全率Fsの値や掛け方は、構造物重要度や耐用年数などの考え方の違いにより、各技術基準で異なっており、特に「道路橋示方書・同解説」では、確実に期待できる支持力であるはずの土の重量γ2・Dfにも安全率が掛けられている(つまり、許容支持力を小さく見積もっている)点は、前述の上載圧項の考え方と異なっているので気をつけて下さい。
護岸ブロック基礎部に厚さ4.3mの浅層混合処理を計画しています
護岸ブロックの背面及び基礎部に安定処理工(バックホウ)を計画しています。土質試験を行い、必要粘着力は30kN/m2という結果が出ました。浅層混合処理を行いたいのですが、(1)セメント系固化材のm3当り添加量の算出方法は?(2)高炉セメントの場合のm3当り添加量の算出方法は?(3)混合処理を行う厚さが4.3mなのですが浅層混合処理は適用できるのか?以上3つを教えてください。
- セメント系固化材のm3当り添加量の算出方法は?
- 高炉セメントの場合のm3当り添加量の算出方法は?
浅層混合を行う場合の固化材添加量は、改良対象土を用いた室内配合試験を行う必要があります。
室内配合試験では、一軸圧縮試験等を行い、必要強度を満たす固化材添加量を決めます。
供試体の作成方法は、地盤工学会基準「安定処理土の突固めによる供試体作成方法(JGS 811)」などを参考にしてください。
また、浅層混合を行う場合においては、室内試験における改良強度に対して施工機械、攪拌機械の混合効率を考慮に入れて固化材添加量を算出する必要があります。
現場での混合効率は、機械や土質条件によって異なります。現場と室内との強度の比については以下の表を参考にしてください。
なお、現場において均一な混合を行うためには、最低でも50kg/m3程度は固化材添加量が必要であるといわれています。
(現場/室内)強さの比
| 固化材添加方式 | 改良の対象 | 施工機械 | (現場/室内)強さの比 |
|---|---|---|---|
| 粉体 | 軟弱土 ヘドロ 高含水比有機質土 |
スタビライザー バックホウ クラムシェル バックホウ |
0.5〜0.8 0.3〜0.7 0.2〜0.5 0.2〜0.5 |
| スラリー | 軟弱土 ヘドロ 高含水比有機質土 |
スタビライザー バックホウ 処理船 泥上作業車 クラムシェル バックホウ |
0.5〜0.8 0.4〜0.7 0.5〜0.8 0.3〜0.7 0.3〜0.6 0.3〜0.6 |
今回の強度は、必要粘着力がC=30kN/m2なので一軸圧縮強さに換算するとqu=2×C=60kN/m2程度となり、現場の混合効率によって強度比約 0.5程度とすれば(現場配合強度)=60/0.5=約120kN/m2となります。よって、この強度を満たす固化材添加量が必要となります。
(3)混合処理を行う厚さが4.3mなのですが浅層混合処理は適用できるのか?
施工の面を考えるとバックホウにて4.3mの厚さを表層改良するのはかなり難しいと考えられます。(水中であれば、なお難しいとも思われます。)
詳細な条件がないので何ともいえませんが専用機械による鉛直方向に改良(深層混合)したほうが良いのように思われます。
施工厚さと表層改良については、「1m厚さの表層地盤改良工事として適切な方法は」
バックホウによる浅層改良については、「バックホウ混練によるセメント処理施工厚さについて」
もありますので参考にしてください。
深層混合処理における盛り上がり土の強度について
地盤改良施工を行い、発生した盛り上がり土を場外に出さずにその場所に盛り、施工が終了して、7m程度の掘削作業に入ったのですが、その盛り上がり土が非常に硬く、想像以上に費用がかかりました。そこで、役所に説明する為に、盛り上がり土は改良部の何%程度の強度が出るといったような文献等は無いでしょうか?(ちなみにセメント添加量は50kg/m3です。)
「盛り上がり土は改良部の何%程度の強度が出るといったような文献等は無いでしょうか?」というご質問ですが、何%というような定量的な評価を行っている文献等について心あたりはありません。大変申し訳ありません。
そもそも、「盛り上がり土=建設発生土」という取り扱いが大半であり、施工後撤去してしまうために、盛り上がり土の強度特性に関する事後調査が十分に行われていないのが現状ではないでしょうか。
参考になるかわかりませんが、以下に多少見解を述べます。
陸上工事および海上工事における深層混合処理工法の検討は、下記文献等に準じて行います。
文献1:陸上工事における深層混合処理工法 設計・施工マニュアル (財)土木研究センター
文献2:海上工事における深層混合処理工法 技術マニュアル (財)沿岸開発技術研究センター
文献3:セメント系固化材による地盤改良マニュアル (社)セメント協会
深層混合処理工法では、設計改良天端と地表面(または海底面)の間に無改良部を設けるのが一般的であり、高改良率の場合は、施工の進捗に伴い、地表面に大きな盛り上がりが発生し、施工後には設計改良天端上部に大量の無改良部(盛り上がり土)が残ります。
文献2によれば、盛り上がり土の強度は、海底地盤の土質にもよりますが、ある程度の強度を有し、海上工事における事例として、170〜210kg/m3のセメント添加量で、盛り上がり天端から40〜50cm下がったところの強度はqu=500〜2000kN/m2であったと報告されています。
一般に、深層混合処理の盛り上がり土の取り扱いは以下の通りです。
(1)地表面(または海底面)から設計改良天端までを掘削(床掘)し除去する。
(2)地表面(または海底面)近くまで改良し、表層部のみ掘削(床掘)し除去する。
(3)表層まで改良し、掘削(床掘)は行わない。
施工実積のほとんどは上記(1)の方法ですが、(2),(3)の事例もいくつか報告されています。
文献2には、関西国際空港の護岸下部地盤改良時の盛り上がり土有効利用として、深層混合処理施工前に敷砂を施工し、地盤高を計測しながら盛り上がり土天端までの改良を行なうことで、盛り上がり土床掘による建設発生土の抑制と、海底面の浮泥の舞い上がりを防止した事例が紹介されています。
「その盛り上がり土が非常に硬く、想像以上に費用がかかりました。」ということですが、文献1,2によると、通常、スラリー系深層混合では改良材添加量が少ないと、スラリー輸送時に脈動が生じて安定供給が困難となったり、改良材と地盤との混合効率が低下することによって、安定した品質の改良体を造成することができなくなるため、最低改良材添加量を70kg/m3としています。粉体系深層混合の場合は、最低改良材添加量をセメント系で100kg/m3、生石灰系で40kg/m3としています。また、文献3によると、浅層混合処理における最低改良材添加量を50kg/m3と考えています。
ご質問の条件は、改良材添加量50kg/m3ということなので、一般に考えられている最低改良材添加量程度であり、低強度改良となります。土質条件や施工方法にもよりますが、改良体の一軸圧縮強さは、バックホウによる掘削が可能なqu=500kN/m2程度以下ではないでしょうか。
この条件で「盛り上がり土が非常に硬く」なった原因としては、設計改良天端以上までセメントミルクを吐出して改良してしまった等の施工上の問題があったのではないかと推測されます。
ラップルコンクリートとセメント固化改良のどちらが安いのですか
河川敷に建物を計画中です。現況地盤から2.3m位までは埋立盛土してあり礫混じりの砂質土で、0.4mのシルト層を挟み、現況から2.8mで玉石混じりの砂礫になりN値50を超えます。傾斜地の為、現況地盤からまだ1.3m造成盛土する必要があるのですが、ラップルと地盤改良ではどちらが有利なのでしょうか?当初は砕石置換も考えていたみたいなのですが、建築では馴染みがないので、外しています。一般的にラップルと地盤改良、砕石置換などを比較した場合、ラップルと地盤改良ではどちらが安いのですか?また施工する際の長所、短所を教えてください。
玉石混じり砂礫土(N値50以上の支持地盤)の上にある、40cm厚のシルト層と、その上の2.3m厚の礫混じり砂質土を、ラップルコンクリート、セメント固化改良、砕石置換等で地盤改良するということですね。
現況地盤上に新たに施工する1.3mの造成盛土は、地盤改良不要な良質土を用いるものと考えて、現況地盤より下の地盤改良についてお答えします。
■ラップルコンクリート
| 施工方法 | 掘削 ⇒ コンクリート打設 ⇒ 残土処分 |
|---|---|
| 施工単価 | 15,000円/m3程度 (残土処分費を除けば10,000円/m3程度) |
| 特徴 |
|
■セメント固化改良(浅層)
| 施工方法 | 掘削 ⇒ セメント混合 ⇒ 埋戻し |
|---|---|
| 施工単価 | 3,500円/m3程度 |
| 特徴 |
|
■砕石置換
| 施工方法 | 掘削 ⇒ 砕石投入・転圧 ⇒ 残土処分 |
|---|---|
| 施工単価 | 12,000円/m3程度 (残土処分費を除けば7,000円/m3程度) |
| 特徴 |
|
上記を見ておわかりの通り、セメント固化改良が圧倒的に安いのではないかと思います。
では、なぜ建築での施工実積が少ないのかという疑問を抱かれると思いますが、この理由については下記文献に詳しく書かれています。
『建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針 −セメント系固化材を用いた深層・浅層混合処理工法− (財)日本建築センター』
以下は補足ですが、ご質問の条件において、本当に地盤改良が必要なのかという疑問が湧きます。40cm厚のシルト層を除けば、砂質土系の良質材料であり、建築物の荷重には十分耐えることが可能ではないでしょうか。もし、シルト層の沈下が心配という理由だけで全面的な地盤改良をお考えでしたら、まずはシルト層の沈下計算を行なうことをお勧めします。場合によっては地盤改良が不用かもしれません。
地盤改良が不用かもしれないと考える根拠は次の通りです。
40cm厚のシルト層は層厚が薄く、両面が排水層(砂礫層)であり、既に4tf/m2程度の鉛直荷重で圧密沈下が終了しているとすれば、新たに追加される1.3mの造成盛土荷重および建築荷重(合計で4tf/m2程度の荷重増加か?)による沈下は小さく、また、沈下が収まるまでの期間も短いものと考えられる。
適当な土質条件を設定してシルト層の沈計算を行なうと以下の通りです。
(注:あくまでも土質条件は"適当"です。)
- 全沈下量
d= H0・Cc/(1+e0)・log{(p+・p)/p}= 40・1.0/(1+1.8)・log{(4+4)/4}≒4cm - 沈下期間(沈下が90%まで完了する期間)
t= {(H0/2)^2}/Cv・Tv= {(40/2)^2}/20・0.848 ≒17日
上記計算結果では、新たな荷重が追加されても、半月程度放置すれば、沈下は90%程度まで収まり、残留沈下は4mm(=4cm×10%)程度とわずかになります。
縁切り矢板によるつれ込み沈下防止について
盛土工において周辺地盤のつれ込み沈下防止(縁切り)のために、盛土下部改良地盤の1メートル横に矢板を打つ計画をしています。圧密沈下計算を行なう際の盛土の荷重分散角は30度と考えて良いのでしょうか。また、盛土下部にセメント固化などの地盤改良が施工してあれば、盛土荷重による周辺地盤のつれ込み沈下や側方変位は防げるのでしょうか。
まずは、「盛土下部にセメント固化などの地盤改良が施工してあれば、盛土荷重による周辺地盤のつれ込み沈下や側方変位は防げるのでしょうか。」というご質問についてお答えします。
厚い軟弱地盤の表層部分のみを改良したのであれば、周辺地盤の変位を防止する効果は小さいものと考えられます。
盛土下部の軟弱地盤層厚に対して、セメント固化改良層厚が厚くなるに従って、セメント固化改良による周辺地盤のつれ込み沈下や側方変位の防止効果は大きくなます。当然ながら、軟弱地盤全層をセメント固化すれば、盛土による沈下も、周辺地盤への影響も(ほとんど)なくなります。
セメント固化を行なうことによって、周辺地盤の変位がどの程度低減されるかを算出するには、FEM解析などによる地盤の変形解析が必要となります。
沈下低減効果については以降で述べる簡易設計も可能ですが、側方変位については、FEM解析が必要不可欠であると考えています。この点についてはQ&A70も参考にして下さい。
ご質問では、周辺地盤のつれ込み沈下防止(縁切り)のために矢板を施工するということですが、矢板の剛性が十分であり、かつ、ある程度硬い層まで根入れされていれば、盛土による鉛直荷重は矢板で遮断され、周辺地盤のつれ込み沈下は発生しないものと考えられます。
矢板で遮断された内側(盛土側)の圧密沈下量を算出するには、一般に以下の方法を用いることが多いのではないかと思います。
(1) 盛土荷重が荷重分散角α(通常α=30°)で一様に分散するものと考えて、改良地盤下部での鉛直荷重を算出する。この方法をボストン・コード法と呼びます。ただし、セメント固化改良層厚が盛土載荷幅に対して十分に厚い場合には、荷重分散角を考えずに、盛土とセメント固化地盤を一体と考えて、全重量を改良地盤下部に一様に分散させます。
(2) 上記(1)で求めた鉛直荷重の軟弱地盤内の任意の地点への分散を求めるには、一般に、等方弾性半無限体中の応力分散解であるブーシネスクの地中応力算定公式を用います。この公式を用いて軟弱地盤の層中央での鉛直応力増分を算出します。
(3) 上記(2)で求めた軟弱地盤の層中央での鉛直応力増分を用いて圧密沈下量を算出します。
なお、矢板の内側(盛土側)での圧密沈下量が大きい場合には、矢板は周辺地盤を支える山留め(土留め)となるので、周辺地盤を変形させないためには、自立山留めとしての検討も行なっておく必要があります。
支持力に関する質問
小規模取水堰基礎地盤の改良工法
小規模な取水堰(川幅7m程度)の基礎地盤ですが、床付面より2〜3mの深さで軟弱層があり、これを地盤改良するに当たって置換工法を採用したいと思います。小範囲かつ簡素な浅層での地盤改良工法がありましたらお教え下さい。
一般的には置換工法が最も安くて確実ですが、残土処分費用によっては、費用が高くなるかも知れません。この様な場合、深層混合処理などのセメント固化系の処理が一番でしょう。ただし、陸上からの施工となりますので河川上に足場を確保する必要があると思います。この場合、足場はH綱製か盛土になるでしょうか。
また、この状況では、バックホウによる混合が、機械も一般的かと思います。この場合、処理手順として、以下のような流れになります。
施工範囲のドライアップ → パワーショベルによる粘土層の掘削撤去 → 粘土へのセメントの添加・混合 → 混合処理土の埋め戻し
ただし、2つの施工上の制約があります。
1)掘削域が矢板などで締め切られて、ドライアップ状態であること。
2)パワーショベルで掘削した土砂を仮置きして、セメント混合・撹拌する場所があること。
上記の条件が合えば、表層混合ではパワーショベルによる方法が一番安価であると思います。なお、セメント添加量は、土や目標改良強度によって異なります。有機分の多い(強熱減量の多い)粘土ほど、添加量は多くなります。
また、改良する深さ、数量などの条件にもよりますが、施工重機が施工位置まで入ることができれば、置換工法よりも、パワーブレンダー工法などによる現位置での固化処理工法の方が安価な場合もあります。(参考:パワーブレンダー工法協会:http://www.power-blender.com/)
建物底盤の半分が軟弱地盤に浮いた状態となる場合の沈下対策
ある地盤に建物を建てる際、表層から数メートルは軟弱地盤でその下層に支持地盤があるとします。建物は長辺方向で数十メートルの規模です。支持地盤は建物底盤に平行でなく、傾いています。施設の底盤はその長辺方向の距離で約半分は支持地盤に岩着するのですが、約半分は浮いた形となります。このとき、浮いた部分の置換や改良が考えられると思いますが、どのような手法がありますか。
この様な比較的浅い部分の改良ですから、何らかの材料による置換工法が最適だと思います。
置換する場合、以下の3つの方法があります。
- 良質土による置換:安価ですが、締め固めの管理が必要です。良質土の購入と掘削土の残土処分が必要となります。
- セメント混合処理土による置換:現位置土にセメント添加をすることにより堅固な地盤をつくります。均質なセメント添加を行う必要があります。セメント材料は10円/1kg程度ですので、m3当たり100-200kg
- コンクリート置換:最も堅固な地盤となります。コンクリート購入と残土処分が必要になります。施工価格に関しては、現地の物価(材料や残土搬出処分)と必要な強度によって大きく異なります。
土地の道路境界から5mの範囲で地耐力が不足しているのですが
先日、ある土地について地盤調査を行いましたが、道路から5m辺りまでの地盤が弱い事が判明しました。土地は、道路より1.5m高く、道路を造った段階で(購入した)土地側にも深く掘り込む事があるので、それが原因では無いか?との事です。
「硬化剤を混ぜた土を弱い部分にだけ混ぜて強度を持たせる方法でも、大丈夫だとは思うが、工学的保証が無く、長年の感でやるので、出来れば、筒を打ち、中に硬化剤を混ぜた土を入れる方法(鋼管工打設工法?)が、10年保証が付いているので良いでしょう」と勧められましたが、価格的には大きく違うと言われました。周りは30年近く前から開けてきた住宅街で、購入した場所は長い間空き地になっていた所です。
基礎はベタ基礎の予定なのですが、勧められている方法の方が、確実なのでしょうか?土地は40坪、1階建坪は22坪(駐車場含む)ですが、改良工法の値段はどれくらいの格差があるものなのでしょうか?また工法としてはこの2種類しか無いのでしょうか?
ご質問の件、お困りだろうと思います。
ご質問の内容は、道路境界から5mの範囲で、地盤の支持力が足りないことだと考えております。対策工法として、以下の二つをお考えなのですね。
1)砂と硬化剤の混合土による埋め戻し
2)鋼管工打設工法
お話から考えると、比較的安価な方法として、以下のことが考えられます。
地面から2〜3m程度の土が悪いのならば、
1)緩い土が砂のように粒状ならば、もう一度緩い部分を掘ってローラーで締め固める。
2)緩い土が粘土の場合、土を掘って、敷地の外に捨てて、再生砕石などの良質な石で置き換える。
3)土の処分費用が高価な場合、土にセメントを混ぜて重機を使って埋め戻す。
これらの方法でも、新築の家が2階建て程度でしたら、比較的安価に頑丈な地盤にすることができ、1立方m当たり1万円前後の費用ですむと思います。
もう少し情報を頂ければと思います。
- 支持力が足りない深さは地面からどのくらい下までか?
- 軟弱な土は、砂・粘土・ローム(オレンジ色の土)のいずれでしょうか?
- 建物は、平屋2階建て程度でしょうか?
また、業者の方とよく話し合うことをお勧めします。
木造平屋の栗石地業を砂利地業に変えることは可能か
木造平屋(小規模100m2程度)のべた基礎に用いる栗石地業についてですが、旧来の施工精度ほどの期待が難しくなっている。他に省力化が期待できる仕様(砂利地業)は考えられるのでしょうか教えてください。
建築物は『建築基準法』に従い建築されなければならないのは言うまでもありません。 『建築基準法施工令』には、地業について詳細な記述はありませんが、施工令が参照としている『住宅金融公庫木造住宅共通仕様書』には、下記の通り地業についての詳細な記述があります。
3.土工事
3.2 地業
3.2.1 割栗地業
割栗地業は次による。ただし、地盤が比較的良好な場合は、割栗によらず砕石による地業とする事ができる。また、地盤が特に良好な場合は、これを省略できる。
イ.割栗石は硬質なものを使用する。なお、割栗石の代用として玉石を使用する場合も同様とする。
ロ.目つぶし砂利は、切り込み砂利、切り込み砕石又は再生砕石とする。
ハ.割栗石は、原則として一層小端立とし、隙間のないようにはり込み、目つぶし砂利を充填する。
ニ.締め固めは、ランマー3回突き以上、ソイルコンパクター2回締め以上又は振動ローラー締めとし、凸凹部は、目つぶし砂利で上ならしする。
ご質問の割栗地業の省力化についてですが、上記仕様書に従えば、地盤が良好な場合には割栗地業を省力化または省略できることになります。地盤が良好か否かの判断基準として住宅金融公庫の考え方は下記の通りです。
- 比較的良好な場合:地耐力5〜10t/m2の場合には割栗を砕石に変更してもよい。
- 特に良好な場合:地耐力10t/m2以上の場合には省略してよい。
木造平屋のべた基礎ということなので、建築基準法に従えば地耐力2t/m2以上は確保されているものと思いますが、地耐力2〜5t/m2場合には割栗地業の省力化は不可能と考えて良いでしょう。なお、ほとんどの大手ハウスメーカーでは基礎の地業は砕石(40-0)となっているようですが、これは地耐力5t/m2という設定で標準的な家を設計していることが多いことと、原地盤の地耐力が5t/m2未満の場合にはセメント改良等による地盤強化を行うことを前提としているからだと思われます。原地盤の地耐力は場所ごとに結構バラツキがあるものなので、十分な地盤調査が必要であり、この結果を踏まえた上で割栗地業を省力化できるか否かの最終判断は設計士が行うことになります。
建築物基礎のラップルコンクリートを砕石で代用できるか(1)
建築物基礎のラップルコンクリート部を、砕石を用いて代用するというのは可能なのでしょうか。またこのような工法はあるのでしょうか。採用する場合の留意点等ございましたらお教え頂ければと思います。よろしくお願いいたします。
地盤の表層が軟弱な場合、または支持地盤が傾斜している場合には、支持地盤まで基礎下にラップルコンクリート(無筋低強度コンクリート)を打設するのが一般的です。
ラップルコンクリートの役割は以下の通りです。
[1]基礎から受ける鉛直荷重を確実に支持地盤に伝え沈下を発生させない。
[2]基礎から受ける地震力などの水平荷重に対して土中に埋め込まれたラップルコンクリートが受動土圧を受けるブロックとして抵抗する。
[3]ラップルコンクリートは低強度で良いため基礎厚を厚くするよりは経済的である。
「ラップルコンクリートを砕石で代用することは可能か?」というご質問ですが、例えば基礎下部2m程度までの軟弱層をラップルコンクリートと同一断面(基礎幅より若干大きい程度)の砕石に置き換えた場合の弊害について考えてみます。
[1]一層20〜30cm程度の数層に分けて砕石を十分に転圧しなければ基礎から受ける鉛直荷重に対して沈下が発生する。転圧回数および施工規模によっては施工に手間がかかり、かえって不経済になる可能性がある。
[2]砕石施工幅が基礎幅に対して十分に大きくなければ、基礎から受ける鉛直荷重、水平荷重によって砕石が軟弱層に横方向に食い込み、基礎が沈下する可能性がある。
以上のように、砕石で代用することが必ずしも経済的にメリットがあるとは限りません。基礎の平面規模が比較的大きく、大型転圧機械が使用できる程度に大きく、施工数量が多く、軟弱層厚が薄い場合、つまり、道路のような大規模施工の場合にはラップルコンクリートよりも安価になるものと考えられます。
ラップルコンクリートよりも安価で、残土も発生しない工法として、浅層地盤改良工法があります。この工法は表層2m程度までの不良な表層土を開削した後、セメント系や石灰系の固化材を添加して埋戻し転圧する工法です。軟弱土を版状の固結体に改良することができ地耐力の強化、沈下、滑り防止が謀れます。なお、支持地盤までが深い場合には現位置混合でセメント改良柱体をつくる深層混合処理工法が用いられています。
建築物基礎のラップルコンクリートを砕石で代用できるか(2)
回答ありがとうございました。どうしても砕石を使用したい場合、
1.砕石部の地盤としての安定性。
2.沈下量
3.支持力
以上の項目をクリアーしないといけないと認識したのですが、砕石または、これらに変わる良質土に置換しようとした場合、どのような方法で確認するのでしょうか。(たとえば、試験や数式等)
個人的には、ラップルコンクリートが確実と思っているのですが、クライアントがなかなか納得せずその説明に困っております。お忙しいところ申し訳ありませんが、お知恵をお貸しいただければと思います。
よろしくお願い致します。
どうしても砕石を使用したいということなので、考え方の一例を述べさせていただきます。砕石施工後は平板載荷試験を行い沈下量および支持力の算定を行えば良いものと考えられます。
1.砕石部の地盤としての安定性
砕石施工幅が基礎幅に対して十分に大きくなければ、基礎から受ける鉛直荷重、水平荷重によって砕石が軟弱層に横方向に食い込み、基礎が沈下する可能性があります。これを回避するための砕石施工幅は以下の通りと考えられます。
一般に、基礎底面から支持地盤に伝わる荷重は、基礎端部から鉛直面に対して30〜45°方向外側に分散するものと考えます。基礎底面と分散面と支持地盤に囲まれた台形範囲を荷重影響範囲と考え、その外側は基礎からの荷重が影響しないと考えます。安全のため分散角を45°と考えれば、基礎幅に対して砕石施工幅を砕石厚分だけ大きくすれば良いものと考えられます。つまり、基礎幅2m、砕石厚2mの場合には砕石施工幅を6mとすれば良い訳です(この場合はラップルコンクリート体積の約3倍の砕石が必要)。
2.沈下量
一層20〜30cm程度の数層に分けて砕石を十分に転圧しなければ基礎から受ける鉛直荷重に対して沈下が発生する可能性があります。
独立基礎や布基礎などの小規模な基礎については、砕石施工後に平板載荷試験を行うことによって、基礎築造後の沈下量を推定することが可能です。一般的な平板載荷試験は地盤上に直径30cmの平板を置き、平板への載荷応力に対する沈下量を読みとる試験です。平板載荷試験から得られる載荷応力〜沈下関係は、形状・寸法の異なる実際の基礎にそのまま適用することができないので形状・寸法の比例関係から換算式を導出します。詳しくは「建築基礎構造設計指針」等を参照して下さい。
3.支持力
平板載荷試験を行った場合には、その試験結果を用いて設計用支持力を算定することができます。平板載荷試験の最大接地圧から基礎の形状・寸法に応じて補正を行い極限支持力を算定します。詳しくは「建築基礎構造設計指針」等を参照して下さい。
補足ですが、以前の「建築基礎構造設計指針」では設計用支持力として長期許容支持力=極限支持力÷3としていましたが、2001年の同指針改定後は設計者の自主的判断を促すかたちとして安全率3を強制しないこととされました。理由としては、基礎の沈下計算を行うことを原則としているため、沈下量が要求性能を満足していれば、あえて安全率が低くても、その基礎は十分に機能する場合もあると判断したためと記載されています。基礎構造をより合理的に(経済的に) 設計するという視点と、今までの安全率3は過剰設計であるという見解に基づいています。
セメント系地盤改良の設計法について
セメント系地盤改良については、以下6つの質問です。
- 支持力について、「地盤改良マニュアル」(セメント協会)P109では、許容支持力を一軸圧縮強度から求めて、P262では、必要粘着力から一軸圧縮強度を求めているように思えます。セメント配合量は後者の考え方でよいのでしょうか?
- 砂質土に支持力は無視して1tfの粘着力をもたせたいとき、単にC=qu/2 、 qu=2kgf/cm2として配合量を決めればよいのですか?
- 薬注のように注入率(セメント配合量)による、原地盤の粘着力増加は考慮しないのでしょうか?(原地盤の粘着力は無視してしまうのですか?)
- 支持力公式のDfの考え方について、改良体の基礎底面下の支持力の検討では、本体工の根入れも含めて改良体深さをDfとし、本体工の基礎底面下の支持力の検討では、Dfを本体工の根入れとするのですか?
- 改良柱の径を決める際、土質、透水係数、一軸強度、N値、施工深度等から留意すべきことはあるのでしょうか?
- 地すべり防止に固化材による改良を行う際、その範囲は強度と範囲の2つを試行錯誤して決めるのでしょうか?
1.前者:Pmax ≦ qa(許容支持力度) = qu(一軸圧縮強度)・後者:Pmax ≦ qa(許容支持力度) = (1/3)αcNc(支持力公式)、qu=2c
「地盤改良マニュアル」(セメント協会)の支持力公式は、「建築基礎構造設計指針」に準じているので、後者の式で算定します。ただし、連続基礎(帯状基礎)では形状係数α=1、改良地盤の内部摩擦角φ=0°では支持力係数Nc=5.3、この場合、後者はqa=(1/3)・1・(1/2)qu・5.3= 0.88quであり、前者のqa=quとあまり差がありません。一般に、セメント系改良地盤はφ=0°として扱うので、概略設計の場合には前者のqa=quを用いても問題はないと考えられます。なお、支持力公式(テルツァーギ、プラントル、マイヤーホフなど、およびこれらの修正)や安全率の考え方は設計基準毎に若干異なるので、まず、どの設計基準書に準拠して設計を行うべきかを明確にする必要があります。私の知っている範囲では以下の通りです。
- 港湾基準:支持力公式;テルツァーギ修正 安全率;Fs≧2.5(重要構造物)
- 建築基礎設計指針:支持力公式;テルツァーギ修正 安全率;Fs=3(長期),1.5(短期)
- 道路橋示方書:支持力公式;プラントル,ソコロフスキー 安全率;Fs=3(常時),2(地震時)
2.通常の設計では地盤をc材(φ=0)またはφ材(c=0)のどちらかに分けて考えます。原地盤砂層が摩擦材料φ材(τf=σtanφ)でも、これにセメントを混ぜると拘束圧によって強度が変化しない粘性材料c材(τf=c)の特性になると考えます。この場合、前述1.後者の支持力公式を用いて改良強度qu(=2c)を求めます。
3.薬液注入の設計における改良地盤のせん断強度τfは、原地盤のc、φに薬液注入による粘着力Δcが付加されたと考えて算出します。改良強度が小さいため、改良地盤としてのせん断強度特性は、原地盤の強度特性に大きく依存しているという考えであり、算出式は以下の通りです。
τf = c+Δc+σtanφ = (1/2)qu・tan(45°-φ/2) +σtanφ
ここで、Δcは薬液注入による粘着力増加であり、ゲル強度と非排水せん断時の土骨格膨張に伴う負圧発生による見かけの粘着力の合計値です。
一方、セメント系地盤改良の設計における改良地盤のせん断強度τfは、原地盤のc、φによらず、セメント混合後の一軸圧縮強度quの1/2としています。 τf=(1/2)qu
セメント系地盤改良のせん断強度に、原地盤のc、φが関係しないのは、モルタルを練る場合に、使用している砂の内部摩擦角φを考慮しないのと同様です。
4.根入れDfは、常に地表面から検討面までの深さですが、Dfが大きくなるほど支持力が大きくなるので、より危険側の検討をするためにDfを考慮しない場合もあります(設計者判断)。
5.機械攪拌式混合の場合の改良柱の径は、現有施工機械の仕様から0.8〜1mが一般的です。高圧噴射式混合の場合の改良柱の径は、薬液注入の場合の改良径の考え方と同様に、ご質問の通り、原地盤の土質特性、施工深度などの他、使用する固化材、吐出圧、貫入・引抜き速度などによって異なります。
6.ご質問の項目の他、改良率(改良断面積/工事面積)も変化させて試行錯誤して決定します。土地の制約、配合試験結果(強度が出ない土質もある)、施工機械の特性、過去の工事実績などを参考にして、制約条件の厳しい項目から決定していきます。
軟弱層上における人間歩行可能の数値判定について
現在軟弱地盤の法面処理工法を検討しているところで、被覆を選定するため人間が歩行できる強度の判定基準があればとネット上を検索しておりました。以前の質問Q2に対するA2の中で“人間が歩行できる程度(粘着力c=1.0〜1.5tf/m2 程度)になると言われています。”と説明文がありますが、その出典元文献がお分かりでしたらご紹介ください。
また、軟弱地盤を掘り込む土構造を構築する場合の注意点がありましたらご指導ください。
人が歩ける程度の粘着力C=1〜1.5tf/m2の出典という話ですが、出典は特にありません。考え方は以下の通りです。
人の体重を60〜90kgf、片足の面積を長さ15cm(約30cmが歩く時に半分になる)、幅10cmの長方形と仮定しますと、地盤にかかる荷重はq= (60〜90)/(0.15×0.1)=4〜6tf/m2で、これに耐える地盤支持力が必要と言うことになります。
対象地盤を粘性土(c材、φ=0)とすると、短期の許容支持力はqa=2/3×(α×c×Nc)で与えられます。(日本建築学会、建築基礎構造設計基準)(α:形状係数、c:粘着力、Nc:支持力係数)αは長方形形状の場合α=1+0.3×B/L(=1+0.3×0.1/0.15=1.2)であり、支持力係数Nc=5.3(φ=0)となります。
従って、人が歩ける地盤支持力という観点から必要な粘着力cは、2/3×(1.2×c×5.3)=4〜6を解いて、
c=0.94〜1.42≒1〜1.5tf/m2ということになります。
それと軟弱地盤を掘り込む土構造構築における注意点ということですが、どのように掘り込むかが不明ですが、一般的にはしっかりした土留めを行う。特に掘削底面の盤ぶくれ(ヒービング)に注意する事と、使用重機のトラフィカビリティや支持力の確保、場所によっては嫌気性の雰囲気が卓越することによる酸欠、有害ガスの発生がないかということに注意して施工をする必要があります。
ラップルコンクリートの断面欠損とコンクリート打ち増しについて
ラップルコンクリートによる地盤補強について教えてください。
重量鉄骨造の住宅を建築中で、現在地盤補強のラップルコンクリートの打設が始められています。
図面上は地中梁のベース部分の寸法が1200角の所のラップルは1500角になっているのですが、実際の施工では基礎業者が1200角で型枠を用意してきてしまったとのことで、ベース部分と同じ寸法で打設が行われています。その点を住宅メーカーに言ってみたのですが、これが支持杭の場合だったらベース面積より小さいんだから、全然問題ないとの返答でした。
また、ラップル打設に関しては厳密に位置を出して行っているわけではないのでベースとずれる場合があるが、杭打ちの場合でも半分しか掛からないこともあるんだから・・・という事も言っていました。
この言い分は施主側にしてみれば、手抜き工事が当たり前に行われていると言われているようなもので、余計に不信感を強めることになりました。
その他、ベース寸法は1500角のところもあるのですが、そこついては型枠を寄せて打設し、枠を外した後ベース寸法に合わせて打ち増しするとのことでした。
この方法は、知識の無い者としてはラップル自体が一体化していなくて問題があるように感じてしまうのですが、実際はどうなのでしょうか?
ラップルコンクリートによる地盤補強の基本的な手法、手順、考え方等も教えていただけたらと思います。
地盤の表層が軟弱な場合、または支持地盤が傾斜している場合には、支持地盤まで基礎下にラップルコンクリート(無筋低強度コンクリート)を打設するのが一般的です。
ラップルコンクリートの役割は以下の通りです。
- 基礎から受ける鉛直荷重を確実に支持地盤に伝え沈下を発生させない。
- 基礎から受ける地震力などの水平荷重に対して土中に埋め込まれたラップルコンクリートが受動土圧を受 けるブロックとして抵抗する。
- ラップルコンクリートは低強度で良いため基礎厚を厚くするよりは経済的である。
以上の件については、この地盤改良質問箱のQ32,33も参考にして下さい。
ラップルコンクリートの設計基準についてですが、基準はないものと考えています。
設計例としては『実務から見た基礎構造設計、学会出版社』が非常に参考となります。
この書籍を参考に設計法を示すと以下の通りです。
- ラップルコンの一般的な規格:Fc=120〜135kg/cm2程度、スランプ12cm程度。
- ラップルコンの地耐力:Fc/3の長期地耐力がある地盤と考える。
- ラップルコンの寸法:基礎寸法に両端10cm以上の余裕を見込む。
- ラップルコンの安定性:幅b/厚さL≦0.84の場合には、地震時水平力に対する安定検討(転倒)が必要である。
ご質問の、「基礎寸法と同じ寸法でラップルコンを施工してしまった」件についてですが、上記・を満足していないことになります。また、b=1.2mということなので、厚さL≧1.4mの場合には、上記・の安定検討も必要となります。
ご質問の、「基礎寸法より小さい寸法でラップルコンを施工してしまったので、打ち増しを行う」件についてですが、基礎は全面積で荷重を受けるように設計されているので、ラップルコンが基礎寸法より小さいと、基礎に設計以上の荷重(応力)が作用したり、固いラップルコンと軟らかい表層地盤をまたぐように基礎が設置されると、不同沈下の原因となることも考えられるので、打ち増しは必要です。
「打ち増しを行うとラップルコンに鉛直打ち継ぎ目ができるが問題ないか」という件については、もちろん、打ち継ぎ目をはつったり、差し筋を行ったり、付着強度の高いコンクリートを用いたり、埋め戻し時の転圧を入念に行えばより安心ですが、最終的には設計者の判断にゆだねられます。
建築基準法改正に伴う軟弱地盤置換改良工法の支持力算定方法
建築基準法改正に伴う(国交通告1113)地盤の支持力算定に関して、軟弱地盤層の置き換え改良後の支持力の算定方法を教えてください。
国土交通省告示第1113号において地盤および改良地盤の許容応力度を定める方法は、第2〜第4項に示されています。
第2は【支持力係数、平板載荷試験、スウェーデン式サウンディング(SWS)による算定式を用いた地盤の許容応力度算定法】、第3は【セメント系固化材による改良体の許容応力度】、第4は【さまざまな改良地盤に対する許容応力度算定法】をそれぞれ規定したものです。
この改正のポイントとして、設計における支持力算定式などが場合に応じて具体的になり、詳細検討が必要となる事項が増えた反面、設計における自由度が増したということが挙げられます。
具体的には、従来の地盤応力度判定式が修正され、斜め荷重を考慮できるようになったことや、慣用的に使われていたスウェーデン式サウンディングなどの結果を用いたり、近年利用されることが増えてきたセメント系固化材による固化処理地盤に対する許容応力度の算定法などが規定されました。
今回のご質問が「軟弱地盤層の置き換え改良後の支持力の算定方法」ということで、掘削置換工法(全面置換・部分置換)による地盤改良における置換工法に対するものと判断すると、この告示中の第2、第3の方法により判定ができます。
第2項で規定された算定法は、(1)従来の許容応力度算定式に斜め荷重の概念が追加されたもの、(2)平板載荷試験の結果を用いるもの、(3)スウェーデン式サウンディング試験の結果を用いるものの3つが規定されています。数式を詳しく挙げることはしませんが、建築物の重要度に応じて、ボーリング調査と土質試験等の詳細な調査を行う場合は(1)式により、一般の住宅などの場合は簡易な平板載荷試験やスウェーデン式サウンディングを行って(2)または(3) 式によって許容応力度を算定します。
また、置換え土にセメント(石灰)安定処理土を用いる場合は、第3項の方法により、安定処理土の設計基準強度F(kN/m2)に、前述と同様の安全率を乗じて地盤の許容応力度を算定できます。
- 長期の許容支持力度:qa=1/3×F(安全率3をとる)
- 短期の 〃 :qa=2/3×F(安全率が長期の半分)
第4の方法は上記の方法に依らなくても、改良地盤において現地の実況に応じた状態で平板載荷試験もしくは載荷試験を行って極限応力度qb(kN/m2)を求めることができるのであれば、
長期:qa=1/3×qb、短期:qa=2/3×qbによって、地盤の許容応力度を算定できることになっています。
既設建築物の土間コン下部を地盤改良したいのですが(1)
すでに建っている鉄骨4階建ての1階土間コン下より水道水が漏れ(850m3)、1階土間コン下1mより下の地層がぬかるみ状態になっています。1階の内装等の修復を最小限に押える地盤改良の方法はありませんか?
メールの情報から推定し、現状を以下のように考えます。
- 粘土地盤がぬかるみ状態
- (おそらく杭基礎の)既設構造物
- 土間コン下の1mが泥濘化
上記の場合、施工機械を使った地盤改良はできないと思います。おそらく、建物の荷重は杭基礎で支えていることと思いますので、泥濘化により建物が変状する事は無いと考えます。この点を設計者にご確認ください。
人が歩く範囲の1階の土間が問題になると思います。
機械施工は不可能ですので、この範囲の土を取れる範囲で除去し、良質な土、できれば排水性のよい砕石などで置き換えるしかないと思います。
現地の土の状況にもよりますが、問題となっている箇所を50cm〜100cm程度置換すれば、人間の歩行などには差し支えなくなると思います。あまり深く掘削をすると土が流動して、事故にもつながりますので、この点は現地で検討が必要だと思います。
上記の対応でしたら、特殊な施工は必要ありませんので、一般的な建設業者で対応が可能だと思います。
既設建築物の土間コン下部を地盤改良したいのですが(2)
現状の詳細内容が解りましたので、もう一度分析をお願い致します。
- 地中梁基礎で、地盤改良、杭も施工してないようすです(住宅密集地で間口が狭い為、重機が入らない。)
- 土間コンt=150mmその下、表土850mm多少湿っている、その下、砂混じりシルトが泥濘状態。
- 現地、河川より100mの位置。
- 地質データ(現地より200m以内)
- 0 〜 0.3m 掘土
- 0.3 〜 0.6m 表土
- 0.6 〜 1.7m 砂混じりシルト N値3
- 1.7 〜 6.1m シルト N値3〜0
- 6.1 〜 7.7m シルト質細砂 N値1〜3
- 7.7 〜 8.5m シルト混じり細砂 N値3〜8
- 8.5 〜 11.5m 細砂 N値8〜25
- 11.5 〜 13.4m 微細砂 N値25〜50
- 築15年位
以上の事より、建物への影響は有りますか。非破壊で含水量など調べる方法は有りますか。
まず、調査方法ですが、建物への影響を知るためには、以下の点を調べる必要があります。
- 泥濘化している深さ、層厚と広がり。
- 泥濘化部分の強度、沈下特性
このため、方法としては、φ10cm程度のサンプリングによる方法が一番良いと考えます。
建物の大きさにもよりますが、4隅と中央部くらいで調査してはいかがでしょうか?
今回のデータから、泥濘部分は砂混じりのシルトのようですね。サンプリングした試料のコアを使って、一軸圧縮試験で強さを求めるのがよいでしょう。泥濘化部分とその下のシルト層だけで良いと思います。
また、沈下の程度を予測するためには、圧密試験を実施するのがよいと思います。一軸圧縮強さから、土の強度が、圧密試験から、沈下量が予測されます。
建物の荷重を考慮して、専門家の方に計算してもらうと、地震時の滑りや建物の転倒に対する安全性、将来的な沈下量が予測できます。
また、このような既設構造物の直下の粘性土を安価に地盤改良する方法はおそらく無いと思います。
検討結果を見て、長期的な沈下量に問題がなければ、表土部分をセメントを混ぜた土と置換するなどの方法が良いのではないでしょうか?
サンプリングを含む計測の結果から、専門家の方を交えて対策をする事をお勧めします。
浅層混合処理工法の最低改良厚さについて
地盤改良の厚さを計算する場合、一般に改良層下面で支持力計算を行うと思いますが、改良強度によっては計算上10cmの厚さでもよい場合があると思います。改良厚さの最低値について基準や計算等はあるのでしょうか?
ご質問の地盤改良は浅層混合処理工法と考えて回答を進めます。
浅層混合処理工法の改良仕様(範囲、厚さ、強度)は、単に設計計算で決定するのではなく、施工法(施工機械のトラフィカビリティは得られるか)、安定した品質が得られるか、構造物の重要度、工期に余裕はあるかなど様々な要因を考慮した上で比較検討を行い、最終的には最も経済的な改良仕様となるように決定します。
土質条件が現場ごとに千差万別のように、最適な改良仕様も現場ごとに異なります。
冒頭で改良仕様は「単に設計計算で決定するのではない」と述べましたが、「詳細に検討すれば、ほぼ設計計算から決定可能」と考えています。円弧すべり計算や改良地盤内部応力照査(圧縮、引張り、せん断応力)のみから改良仕様を決定しようとしても、改良強度を大きくすれば、改良厚さが小さくなるという反比例関係が得られるだけで、ご質問のように「強度を大きくすれば改良厚さは10cmでもよいのか」という疑問を抱くかもしれませんが、強度発現は可能か、改良地盤下面での支持力、沈下に問題はないかなどを検討することで改良厚さが決定される場合が大半であると考えています。原地盤が岩盤や十分に締まった砂礫層でもない限り、改良厚さが10cmでよいということにはならないのではないでしょうか。
なお、最低改良厚さの基準はないのではないかと考えています。
以下に設計、施工、強度の留意点および参考文献を示します。
■設計
1.支持力
a)極限設計法
一般に基礎底面からの荷重分散角30°を考慮して、鉛直荷重を分散し、改良地盤下面での支持力照査を行います。鉛直荷重の算定にはブーシネスクの地中応力算定公式を用いる場合もあります。改良地盤内部応力は一般にパンチング破壊(押抜きせん断)等で検討を行います。
b)地盤係数法
弾性床上の梁とも呼ばれる解析法です。改良地盤を弾性地盤に支持された梁部材と見なして、改良地盤内部応力の照査を行います。地盤が軟弱(例えば、粘着力c<1tf/m2)な場合や、改良厚さが薄い場合の改良強度は、せん断強さよりはむしろ曲げ強さで決定される場合が多いので、せん断応力、曲げ応力、沈下を同時に検討できる本解析法が一般に用いられています。また、詳細検討が必要な場合には有限要素法が用いられる場合もあります。
2.円弧すべり
擁壁や盛土などでは、改良範囲、厚さ、強度を変えながら円弧すべり破壊の検討を行う必要があります。
3.沈下
原地盤が粘性土の場合には、改良厚さを変えながら、圧密沈下量が許容値に収まるように検討を行う必要があります。
設計では上記1〜3の全てを満足する必要がありますが、明らかに地盤が良好な場合には検討を省略したり、地盤が粘性土で軟弱な場合には上記以外に側方変位の検討を要したりします。
■施工
- スタビライザ混合 改良厚さ 0.2〜2.0m
- バックホウ混合 改良厚さ 0.5〜3.0m
- ロータリー式混合 改良厚さ 0.5〜4.0m
- 柱状撹拌混合 改良厚さ 2.0〜6.0m(深層混合処理の場合は〜40m)
上記改良厚さは、あくまでも目安です。改良単価は、原地盤1m3当り2000〜7000円程度。
■強度
一般的な改良強度は一軸圧縮強さqu=100〜1000kN/m2程度で設定しますが、改良後に掘削や杭打ちなどを行う場合には500kN/m2以下に抑える場合もあります。また、原地盤が高有機質土や高含水土の場合には、セメントを添加しても十分な強度が得られない場合もあり注意が必要です。
■参考文献
- 『セメント系固化材による地盤改良マニュアル(第二版)、(社)セメント協会』
- 『建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針 −セメント系固化材を用いた深層・浅層混合処理工法−(財)日本建築センター』
建築工事においては、国土交通省より上記を参照することが勧められています。
N値1〜2の軟弱地盤上にボックスカルバートを布設する際の支持力対策
N値1〜2の軟弱地盤(シルト・粘土・砂)にBOX-C(3500×3000)を布設しようと計画しております。基礎地盤の許容鉛直支持力の検討において、平成14年3月発行の「道路橋示方書・同解説」の直接基礎の設計に基づいて計算しておりますが、基礎底面の置き換えをおこなっても十分な支持力が得られない結果となりました。
平成8年の道路橋示方書にはなかった「支持力係数の寸法効果に関する補正係数」が加わり、困惑しております。計算例などがあれば教えていただきたいのですが。
ご質問の通り、平成14年3月発行の「道路橋示方書・同解説 ・下部構造編」の直接基礎の支持力算定式には、平成8年の道路橋示方書にはなかった「支持力係数の寸法効果に関する補正係数」が加わりました。
N値1〜2の軟弱地盤(粘性土)の極限支持力度quは、内部摩擦角φ=0°とすると、Nr項が消去され、以下の通りとなります。
qu=α・κ・c・Nc・Sc+κ・q・Nq・Sq
Sc、Sqが寸法効果に関する補正係数です。この補正係数は、同一の地盤において、基礎の底面寸法が増加すると支持力係数Nc,Nq,Nrは減少するという最近の知見を反映したものであり、今後、各種基準で採用されるものと思われます。なお、「建築基礎構造設計指針(2001年版)」ではNrの補正のみが採用されています。
寸法効果に関する補正係数を除けば、以前の支持力算定式と同一であり、補正係数採用による影響度を、ご質問の条件を想定して算出すると以下の通りとなります。
- Sc=(c*)^(λ)=(c/c0)^(-1/3)=(10/10)^(-1/3)=1
- Sq=(q*)^(ν)=(q/q0)^(-1/3)=(γ2・Df/10)^(-1/3)=(3・5/10)^(-1/3)=0.9
補正係数は支持力算定上それほど大きく影響していないのではないでしょうか?
基礎底面の表層砂置換では十分な支持力が得られないという検討結果は、支持力算定式が変わったためではなく、地盤が悪すぎるためと考えられます。 ご質問の地盤はN値1〜2の軟弱地盤(粘性土)ということなので、N値から粘着力cを推定すると以下の通りであり、コンシステンシーとしては、「非常に柔らかい」と表現される地盤です。
c=(1/2)qu=(1/2)(N/8)=0.06〜0.13kgf/cm2≒6〜13kN/m2
※ここでのquは一軸圧縮強さです。
また、コーン指数qcは以下の通りであり、建設機械のトラフィカビリティとしては、超湿地ブルドーザでの施工が可能な程度となります。
qc=10c=0.6〜1.3kgf/cm2≒60〜130kN/m2
粘性土地盤では、N値2以下では「柔らかい」と表現されますが、N値4以上では「硬い」と表現されるほど、N値の微妙な変化で性質が大きく異なります。地盤強度に関するデータがN値しかないのであれば、N値から強度推定するのも一つの手段ですが、詳細な検討を行なうのであれば、ベーンせん断試験、コーン貫入試験、サンプリング後の一軸圧縮試験および圧密試験などを実施することをお勧めします。
ご質問のような軟弱地盤上にボックスカルバートを布設する場合には、一般に以下のような施工が行われます。
(1)トラフィカビリティ確保
| 工法: | 表層砂撒出し、ジオテキスタイル補強、表層固化、など |
(2)地盤改良(支持層まで、または、支持力が得られかつ沈下も問題ない深さまで)
| 工法: | 圧密改良(ペーパードレーン工法、サンドドレーン工法、など) |
| 固化改良(深層混合処理工法) 置換改良(サンドコンパクションパイル工法) |
詳細については「道路土工 軟弱地盤対策工指針」などを参考にして下さい。
なお、同指針には、道路を横断するカルバートでは、盛土荷重や交通荷重による路面の不同沈下を避けるために、支持層に達する深い基礎(杭基礎含む)を設けることはできるだけ避け、プレロードによる圧密改良が望ましいと記述されております。
浅層改良下面での支持力照査に改良体の自重を考慮するべきか
擁壁およびボックスカルバートなどの基礎地盤に浅層改良を行う場合の設計についての質問です。改良の厚さを決定する場合、「道路土工 擁壁工指針P110〜112」に準じれば、『荷重による地中応力度が軟弱地盤の許容応力度以下となる深さまで軟弱層を改良する』とあり、地中鉛直応力の算出式も記載されておりますが、この式では改良体の自重は考慮されていません。改良体の自重は考慮しなくても良いのでしょうか?
直接基礎下部の軟弱地盤を浅層改良する際、軟弱地盤が厚く、支持層が深い場合には、荷重による地中応力度が軟弱地盤の許容支持力度以下となる深さまで改良を行います。
「浅層改良下面での支持力照査に改良体の自重を考慮するべきか」というご質問ですが、以下の2通りの考えがあると思います。
(a) 地中応力に改良体自重を考慮し、許容支持力に根入れDfを考慮する。
(b) 地中応力に改良体自重を無視し、許容支持力に根入れDfを考慮しない。
設計法が、根入れのある直接基礎の支持力照査と同様であることを考慮すれば、「(a)自重を考慮する」と考えるのが一般的ではないかと思います。改良体自重を考慮した設計例は、以下の指針にも記載されています。
『建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針−セメント系固化材を用いた深層・浅層混合処理工法− (財)日本建築センター』
「道路土工 擁壁工指針」には、基礎下面から分散角30°を標準として浅層改良下面までの荷重分散を考慮して地中鉛直応力度σzを算定する方法が紹介されていますが、このσz は基礎築造に伴う地中鉛直応力度の増加分であるため、(a)自重を考慮する場合には、改良体自重γ2・Dfを加味して、支持力照査は以下の通りとなります。
地中鉛直応力度q=σz+γ2・Df ≦ 許容支持力度qa
補足ですが、浅層改良のように改良前と改良後の土の単位体積重量γ2がほぼ等しく、地盤の内部摩擦角φが小さい場合には、(a)と(b)のどちらの検討方法を用いても検討結果に大差は生じません。
理由は以下の通りです。
極限支持力算定式において根入れDfが含まれる項は、上載圧項(Nq項)です。上載圧項は、φ=0°(粘性土など)の場合に、Nq=1であり、最も小さな値 γ2・Df・Nq=γ2・Df になります。
このγ2・Dfは、根入れ深さよりも上の土の重量に相当しますが、極限支持力の内、根入れ深さより上にある土の重量γ2・Dfは、もともと、その深さの地盤が支えていた重量であるため、安全率によらず確実に期待できる支持力と考えるのが一般的です。
もう少しわかり易く言えば、掘削した土をそのまま埋戻しても、埋戻土の重量で掘削底面が破壊することはなく確実に支持できるということです。この場合、支持力照査は以下の通りとなります。
地中鉛直応力度q=σz+γ2・Df ≦ 許容支持力度qa=1/Fs・(α・c・Nc)+γ2・Df
γ2・Dfを消去すると、以下の通りとなります。
σz ≦ 1/Fs・(α・c・Nc)
つまり、地中応力に改良体自重を無視し、許容支持力に根入れDfを考慮しない(b)の検討方法と等しくなります。
港湾、道路、鉄道、建築など各技術基準に示されている極限支持力算定式は、支持力係数の値が異なるなどの若干の違いはあるものの、本質的には変わりません。
ところが、極限支持力quから許容支持力qaを設定する場合の、安全率Fsの値や掛け方は、構造物重要度や耐用年数などの考え方の違いにより、各技術基準で異なっており、特に「道路橋示方書・同解説」では、確実に期待できる支持力であるはずの土の重量γ2・Dfにも安全率が掛けられている(つまり、許容支持力を小さく見積もっている)点は、前述の上載圧項の考え方と異なっているので気をつけて下さい。
ラップルコンクリートとセメント固化改良のどちらが安いのですか
河川敷に建物を計画中です。現況地盤から2.3m位までは埋立盛土してあり礫混じりの砂質土で、0.4mのシルト層を挟み、現況から2.8mで玉石混じりの砂礫になりN値50を超えます。傾斜地の為、現況地盤からまだ1.3m造成盛土する必要があるのですが、ラップルと地盤改良ではどちらが有利なのでしょうか?当初は砕石置換も考えていたみたいなのですが、建築では馴染みがないので、外しています。一般的にラップルと地盤改良、砕石置換などを比較した場合、ラップルと地盤改良ではどちらが安いのですか?また施工する際の長所、短所を教えてください。
玉石混じり砂礫土(N値50以上の支持地盤)の上にある、40cm厚のシルト層と、その上の2.3m厚の礫混じり砂質土を、ラップルコンクリート、セメント固化改良、砕石置換等で地盤改良するということですね。
現況地盤上に新たに施工する1.3mの造成盛土は、地盤改良不要な良質土を用いるものと考えて、現況地盤より下の地盤改良についてお答えします。
■ラップルコンクリート
| 施工方法 | 掘削 ⇒ コンクリート打設 ⇒ 残土処分 |
|---|---|
| 施工単価 | 15,000円/m3程度 (残土処分費を除けば10,000円/m3程度) |
| 特徴 |
|
■セメント固化改良(浅層)
| 施工方法 | 掘削 ⇒ セメント混合 ⇒ 埋戻し |
|---|---|
| 施工単価 | 3,500円/m3程度 |
| 特徴 |
|
■砕石置換
| 施工方法 | 掘削 ⇒ 砕石投入・転圧 ⇒ 残土処分 |
|---|---|
| 施工単価 | 12,000円/m3程度 (残土処分費を除けば7,000円/m3程度) |
| 特徴 |
|
上記を見ておわかりの通り、セメント固化改良が圧倒的に安いのではないかと思います。
では、なぜ建築での施工実積が少ないのかという疑問を抱かれると思いますが、この理由については下記文献に詳しく書かれています。
『建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針 −セメント系固化材を用いた深層・浅層混合処理工法− (財)日本建築センター』
以下は補足ですが、ご質問の条件において、本当に地盤改良が必要なのかという疑問が湧きます。40cm厚のシルト層を除けば、砂質土系の良質材料であり、建築物の荷重には十分耐えることが可能ではないでしょうか。もし、シルト層の沈下が心配という理由だけで全面的な地盤改良をお考えでしたら、まずはシルト層の沈下計算を行なうことをお勧めします。場合によっては地盤改良が不要かもしれません。
地盤改良が不要かもしれないと考える根拠は次の通りです。
40cm厚のシルト層は層厚が薄く、両面が排水層(砂礫層)であり、既に4tf/m2程度の鉛直荷重で圧密沈下が終了しているとすれば、新たに追加される1.3mの造成盛土荷重および建築荷重(合計で4tf/m2程度の荷重増加か?)による沈下は小さく、また、沈下が収まるまでの期間も短いものと考えられる。
適当な土質条件を設定してシルト層の沈計算を行なうと以下の通りです。
- 全沈下量
d= H0・Cc/(1+e0)・log{(p+・p)/p}= 40・1.0/(1+1.8)・log{(4+4)/4}≒4cm - 沈下期間(沈下が90%まで完了する期間)
t= {(H0/2)^2}/Cv・Tv= {(40/2)^2}/20・0.848 ≒17日
上記計算結果では、新たな荷重が追加されても、半月程度放置すれば、沈下は90%程度まで収まり、残留沈下は4mm(=4cm×10%)程度とわずかになります。
砂地盤上の住宅基礎形式選定について
家を新築しようと思うのですが、地盤調査の結果を基に、どのような基礎を採用するべきかを教えて下さい。(地盤調査はスウェーデン式サウンディング試験。N値は換算N値(砂質土))
なお、家の前面より4.0m先は高さ3.0mの法面となっており(1:2程度)、擁壁設置に伴い家の前面近くまで掘削をします。
- 前面
- 深度0.00〜0.25m N値3.1
- 深度0.25〜1.00m N値18.5〜25.5
- 深度1.00〜4.00m N値2.5〜3.5
- 深度4.00〜 N値15以上
- 中央
- 深度0.00〜0.50m N値2.8〜4.1
- 深度0.50〜1.00m N値5.8〜7.9
- 深度1.00〜3.00m N値2.5〜3.5
- 深度3.00〜 N値15以上
- 後面
- 深度0.00〜1.00m N値2.8〜4.1
- 深度1.00〜1.50m N値4.1〜4.7
- 深度1.50〜1.75m N値3.1
- 深度1.75〜 N値15以上
ご質問の件ですが、地盤調査の結果を見ると、比較的良好な土地であると推定されます。
GL-1.0mから-4.0m程度までが、砂地盤としては若干ゆるい状態にありますが、家屋を造る程度でしたら、全く問題がないレベルだと思われます。
弱層のN値を2.5とすると、
地盤の砂の内部摩擦角=√(20×N)+15°=22°
となります。
この値を用いて、かなり、安全側に計算をすると、地盤支持力は、30kN/m2を若干下回りますので、基礎形状は、べた基礎(Q6参照)となります。
基礎形状をかなり安全側に仮定していますので、正確な値は、工務店の方と相談して下さい。
正確な支持力の計算で、十分な地耐力を確認でき、安全となりましたら、布基礎でも、施工は可能だと思います。
ただし、長期的には、地震などに備えて、べた基礎とすることもご検討下さい。
薬液注入処理に関する質問
シリカゾルの耐久性
民有地内の立坑の底盤改良に使用したいのですが、シリカゾルの耐久性について教えてください。
立抗ということですから、どのくらい期間の耐久性が必要なのかが問題になります。通常の水ガラス系の薬液(LWなど)でも6ヶ月間くらいは止水性・強度があります。以下は、それ以上の期間を想定した耐久性グラウトについての話となります。
・シリカゾルの耐久性について
シリカゾルによる改良地盤に関しては、16年前に改良した地盤から改良体を掘り出した実例があります。この事例では、地下水位の影響を受けた場所にも係わらず、16年前の施工当初と比べて改良土の劣化は認められませんでした(この時の改良強度は400kPa程度でした)。
・シリカゾルの耐久性がよい理由
水ガラス系の改良土の劣化は、水ガラス中に残存するNa+イオンが固化物のシリカと反応して固結物を溶かしてしまうため起こります。簡単に書きますと、シリカゾルではこのNa+イオンを化学的に中和することで除去しているため、劣化が生じないわけです。
下水道小口径推進工法の立坑からの水平薬注
下水道小口径推進工法の立坑から水平削孔による薬注を考えています。経済性から出来るだけ小さな鋼矢板立坑としたいのですが、ロッド長なども出来るだけ短いものを使ってコンパクトにした場合、最小スペースはどの程度必要でしょうか。また、現在立坑長を3.0mとしていますが、これで可能でしょうか。
施工機械に関しては、各施工方法によって異なるようです。一般的な話となりますが、通常の施工では1.5mの削孔ロッドを使いますので、余裕代を見込むと 3m×3mとなります。ただし、仕様は施工業者によって異なりますので、専門業者にご相談されてはいかがでしょうか?なお、水平注入に関する資料を捜しましたが、特に見つかりませんでした。最新の施工技術に関しては『最新地盤注入工法技術総覧』が(株)産業技術センターより出版されています。これは薬液注入工法に関して比較的新しい技術まで掲載されております。
泥水式シールドの逸泥防止薬液注入改良範囲
泥水式シールドが岸壁に接近しているため、逸泥防止の薬液注入を検討していますが、改良範囲について資料等がありましたら、お教えください。
『薬液注入工設計資料(平成12年度版) (社)日本薬液注入協会』によると、薬液注入改良範囲は下記1、2の大きい方を採用することを基本としています。
- 最小改良範囲(一般に複列注入が可能な厚み(1.5m以上))
- 改良地盤の粘着力cを考慮した地山の安定計算より求まる改良範囲
上記設計資料にはシールド工事の薬液注入範囲設計方法についての記載もあります。参考にされてはいかがでしょうか?設計施工実績としては、シールド側部の改良厚を1.5m〜D/2の範囲にすることが多いようです(Dはトンネル直径)。
その他、『シールド工法の実際 鹿島出版会』、『薬液注入工法の調査・設計から 施工まで 土質工学会』なども参考にされてはいかがでしょうか?
電車の軌道の下にトンネルを作る際の注意事項
電車の軌道の下にトンネルを作る際、注意しなければならないことは何ですか?
ご質問のトンネルが、盛土電車軌道の下に道路を通すのか、平地電車軌道の下にアンダーパスを通すのか、地下鉄の交差部なのかは不明ですが、いずれにしても『既設の電車軌道に地盤変形による悪影響を及ぼさない』ことが注意事項となります。地盤変形は、掘削による地盤の緩み、地下水位低下による沈下の他、シールドトンネルでは切羽への加圧が原因になることもあります。地盤変形を防止するためには、トンネルと地山間の空隙を早期に裏込めするなど地盤をゆるませないように確実な施工を行うことはもとより、近接施工に際する防護対策として、地盤固化、土留め、法面保護(シート、土嚢積みなど)などを適切に行いながら現場施工が進められています。
通常の施工では、軌道の防護工として円形断面のパイプを並べるパイプルーフ工法やハイビーム工法などが用いられます。近年は、より大きい荷重に耐えられる矩形の防護管を用いる工法が各種提案されています。参考文献:基礎工、2007、Vol.35、No.4など。
薬液注入工法のセメント系注入材の適用土質について
薬液注入工法の、セメント系注入材の適用土質について質問します。
- セメント系注入材が適用出来る土質を教えてください。
- セメント系注入材は懸濁型であり、その内の普通ポルトランドセメントは粒径が大きく、砂層には浸透注入が出来ないようですが、全く浸透出来ないのでしょうか(砂の粒径にもよると思いますが)。また、改良効果は期待出来ないのでしょうか。具体的な試験データのようなものがありましたら、いただけませんでしょうか。また、超微粒子セメントを使用すると砂層への浸透注入は可能でしょうか。この場合は改良効果を期待出来ますか。この場合の材料単価は1リットル当たりいくらくらいになりますでしょうか。
まず、セメント系の薬液の注入限界の件です。
これは私自身が実験で確認したことですので、それ以上でも以下でもありません。
私は、細粒分含有率(Fc)の異なる砂へ超微粒子セメントを注入してみました。その結果、Fc=0〜5%程度の荒い砂では、浸透注入させることができました。Fcがこれ以上大きくなると、割裂注入になり、均等な改良体はできませんでした。いろいろな会社がチャレンジしていますが、うまくいかないようです。
薬液の単価は、50円/L〜70円/L程度だと思います。直接工事費は、施工費込みで、80〜100円/L程度だと思います。
それほど強度がいらず、恒久性のみが必要な場合、弊社が開発した「浸透固化処理工法」をお勧めします。
qu=60〜100kPa
薬液単価 40円/L程度です。
施工実績も100件、32万m3くらいあります。
もう少し強度が欲しい場合、シリカライザ−という薬液があります。qu=400kPaくらいまで上がります。強酸性のため、コンクリート構造物へ若干の影響があります。
どちらも、Fcの適用限界は、20%です。適用限界は土によって変わります。
浸透固化処理工法については、以下のHPをご覧下さい。
http://www.penta-ocean.co.jp/business/tech/civil/ground/penetrate.html
矢板欠損部への薬液注入必要性を説明するための根拠データ
設計変更で矢板の欠損部に薬液注入工(水ガラス)を追加する必要性が出てきたのですが、その根拠として一般的にどのようなデータを提出すれば認められるのでしょうか? 掘削深は3.5m、地下水位はG.L-1.5m、シルトを含む砂質土、多量の湧水があり、N値は3です。ただし全体で40000リットル程度の量であり、工期もわずかな為、調査工等の手間をはぶきたいのですが。
湧水の多い地盤における土留め矢板欠損部への薬液注入は、止水と地山安定のために用いられます。『薬液注入工設計資料(平成12年度版) (社)日本薬液注入協会』によると、薬液注入改良範囲は、下記(1)(2)の大きい方を採用することを基本としています。
(1)最小改良範囲(一般に複列注入が可能な厚み(1.5m以上))
(2)改良地盤の粘着力cを考慮した地山の安定計算より求まる改良範囲
「矢板欠損部に薬液注入工を追加する必要性について、その根拠として一般的にどのようなデータを提出すれば認められるのでしょうか?」というご質問ですが、発注者の違い、工事規模、工事の危険性などによって提出する根拠データ(検討精度)にも差があるものと考えられます。
例えば、薬液注入の必要性を説明することだけで設計変更に結びつくのであれば、「試掘した結果、多量の湧水があり、地山崩壊の危険性から、施工に支障をきたす恐れがあり、仮設工として薬液注入を行いたい。」という旨を伝えれば良い訳ですが、設計計算書を添えなければ設計変更を認めてもらえないのであれば、薬液注入を行うことによって、止水と地山安定に問題がなくなることを発注者に理解してもらう必要があります。
通常、止水および地山安定を目的とした薬液注入工の設計には、最低限の土質調査として、N値と粒度分布が必要であり、以下の通り設計に活用しています。
- 粒度分布 → 注入薬液選定、注入工法選定
- N値 → 改良強度(改良後粘着力c)推定、原地盤の内部摩擦角φ推定
ご質問のケースでは、対象土がシルトを含む砂質土、多量の湧水ありということなので溶液型水ガラス系薬液注入を選定しているものと思います。
止水性については、薬液注入を行うことで地盤の透水係数がk=0.0001cm/sec程度になるので、厚さ1.5m以上を確保すれば、止水壁として問題がないことを、『薬液注入工設計資料』等を参考にして説明できます。
地山安定については、薬液注入部分の開削により、地山の主働破壊が発生しないように設計を行うのが一般的です。設計に必要な土質定数は、原地盤および改良地盤の内部摩擦角φ、粘着力cです。設計手法については『薬液注入工設計資料』等を参考にして下さい。
土質定数を詳細に求めるのであれば三軸圧縮試験を行う必要もありますが、「工期もわずかな為、調査工等の手間をはぶきたい」というなら、設計に必要な土質定数をN値から推定することもできます。ご質問のケースがN値=3の砂質地盤のということなので、設計に必要な土質定数は以下の程度ではないでしょうか。
- 原地盤:φ=25°程度、c=0
- 改良地盤:φ=25°程度、c=50kN/m2程度
その他、『薬液注入工法の調査・設計から施工まで』 地盤工学会なども参考にされてはいかがでしょうか?
崩壊斜面への薬液注入による止水効果
薬液注入及び地盤改良の止水効果について質問致します。崩壊した斜面の復旧工事を行っております。崩壊後、数ヶ月が経過しましたが斜面は一応安定しておりました。しかし、現状の安全率を1.03と仮定して、崩壊した土砂を除去しようとすると、安全率が0.87まで低下してしまいます。このため、再崩壊を防止する目的で崩壊した土砂に薬液注入工を施し、粘着力を増すことで地盤の強化を図ることを考えました。
薬液注入後に実施した標準貫入試験結果では、N値が向上しており、C=2/3Nの関係式から、目標とする粘着力が得れたことが確認できています。ここで質問ですが、崩壊した原因が、降雨による間隙水圧の増大と考えられるため、薬液注入された地盤内に降雨を浸透させたくないという思いがあり、注入後にどの程度止水効果が上がったのか、数値的に究明したいと思っております。透水試験では5.67×10(マイナス6乗)と、いわゆる「難透水層」であることが確認できております。しかし、発注者の意向としては、もっと具体的で明確な表現を求められています。具体的な方法がありましたら教えて下さい。
もう一つ質問ですが、崩壊して崩れ落ちた箇所については、「補強盛土工+地盤改良」によって復旧しました。この地盤改良を行った箇所での止水効果についても、上記同様、究明方法がありましたら、教えて下さい。最後になりましたが、最終の対策工法は、「コンクリート版+グラウンドアンカー工となっております。
ご質問の通り斜面崩壊の主原因は降雨であると考えられますが、降雨による斜面崩壊には以下のような様々なパターンが考えられます。
- 降雨により表層が浸食された。
- 降雨により土が水を含み土の重量が増したことによって斜面安定が保てなくなった。
- 降雨により斜面内に水の流れが発生し、間隙水圧上昇により有効応力が減少し斜面安定が保てなくなった。
- 斜面の透水性(排水性)が悪い場合には、降雨により斜面内部の地下水位が上昇し、水圧が斜面を押し出すために斜面が膨れあがり崩壊する。
ご質問の状況が上記のどれに当てはまるかは判りませんが、再崩壊を防止する目的で、崩壊した斜面に薬液注入を行い地盤の強化を謀るという対策は間違ってないと思います。
ただし、薬液注入を行うことで斜面は遮水壁となるので、例えば表層だけしか薬液注入を行わない場合には、上記4のような内水圧による崩壊を招くので注意が必要です。これを防止するためには、改良厚を十分にとり改良土の重量で、背面から受ける土圧と水圧に対抗できるように重力式擁壁として設計する。もしくは、改良厚が薄い場合には排水孔を設けるなどの圧抜き対策を行うことが大切だと思います。
前おきが長くなりましたが、ご質問の「地盤改良による止水効果の説明方法」についてお答えします。
一般的には「透水係数が10のマイナス6乗cm/s」というだけで難透水層と理解してもらえるのですが、正確には、「透水係数が小さい層が何mあるか」という「層厚」も考慮して難透水層かどうかを判断します。
例えば、『薬液注入工設計資料(平成12年度版) (社)日本薬液注入協会』を参照すると、仮設矢板欠損部の遮水工として薬液注入を行う場合の改良厚は、一般に複列注入が可能な厚み1.5m以上としているケースが多く見受けられます。これは、現場での湧水量などを反映した経験値であると考えられます。この場合、「薬液注入により透水係数が10のマイナス6 乗cm/sの層が1.5m以上複列注入してあるので十分に難透水層です。」と説明すれば良いものと考えられます。
例えば、『一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(1998年6月16日総理府、厚生省共同命令)』には遮水工の規定があり、「透水係数が10のマイナス5乗cm/sの層が5m以上存在する場合は遮水層と見なす」という旨が記されています。
浸透時間(水が遮水層を通り抜けるまでの時間)tは次式で表されます。
t=(L^2)/(k・h)
ここに、L:層厚、k:透水係数、h:遮水層両側の水位差
例えば、k=10^-5(cm/s)、L=500(cm)、h=50(cm)の場合には、t=500000000(sec)≒16(年)となり、層を水が通り抜けるのに16年近くかかります。従って、難透水層以上に止水性の高い遮水層と見なせるわけです。
ご質問の透水試験結果k=5.67×10^-6という条件をもとに、この基準と同等の遮水性能を有する層厚を算出すると、(L^2)/(5.67×10^ -6)=(500^2)/(10^-5)の関係からL=376(cm)となります。もしも改良厚が4m程度あるなら、「透水係数5.67×10のマイナス6乗cm/sの薬液注入を4m程度行っており、最終処分場の遮水工と同等の遮水性を有しています。」と説明すれば良いものと考えられます。
薬液注入工事における現場注入試験費用負担ついて
薬液注入工法における建設工事の施工に関する暫定指針によると、「設計どおりの薬液の注入が行われるか否かについて、調査を行うものとする。」とされていますが、その調査に要する費用負担は、一般的には業者側・発注側どのように考えられるでしょうか。
一般に、工事にかかる費用ですから、発注者の積算に計上されるべきものと考えております。
ただし、これまでの実績では、工事の規模などにより、異なることもあります。
水平方向へのダブルパッカー方式薬液注入時のセメントミルク逸脱防止方法
電車の軌道下に水平方向にダブルパッカー方式薬液注入を行います。シール注入時のセメントミルクの逸脱を防止するには、どのような口元処理が必要なのでしょうか。
水平方向へのダブルパッカー方式のシール材の逸脱防止としては、以下の二つの方法があります。
1)口元処理として、ウレタン材料、ゴムパッキン、エアーパッキン等を使用し、奥側から、セメントベントナイト等のシール材を注入し、口元から流出したところで、シール材注入完了とする。この方法が一般的に用いられている方法ですが、スリーブ(シール)の出来は良好ではありません。
2)シール材として、中結型(ゲルタイム5〜10分)の水ガラス系薬液を使用する。この方法は、比較的良好なスリーブ(シール)ができますが、シール材のコストが高価となります。
なお、詳細につきましては、薬液注入の専業社に問い合わせしていただければと思います。
薬液注入工法での底版の改良厚さの決め方について
薬液注入工法での底版の改良厚さの決め方について教えてください。
- 掘削底面下が砂礫土の場合
- 掘削底面下が粘性土の場合
- 掘削底面下が互層地盤の場合
- 互層地盤の場合、ヒービング、ボイリング、盤ぶくれのどのケースで検討をすればよいのでしょうか? 鋼矢板の根入れ先端の位置により決めるのでしょうか?
- 上記の1から4において改良厚さはどのように決めるのでしょうか?
ご質問は、土留めにおける掘削底版の薬液注入による改良に関してですが、原地盤が砂礫土である場合にはボイリング、粘性土または細粒分の多い砂質土である場合には盤ぶくれ、軟弱粘性土の場合にはヒービングが問題となります。
文献「薬液注入工法の調査・設計から施工まで 地盤工学会編」によると、改良厚さは、地下水位の深度や水頭により異なりますが、一般に2〜3mあればよいと記述されています。
ボイリング、盤ぶくれ、ヒービングの概要は以下の通りです。
詳しくは、文献「根切り工事と地下水 調査・設計から施工まで 地盤工学会編」などをご覧になって下さい。
- ボイリング
- 地盤状態
- 掘削底面付近が砂礫土で、掘削側と土留め背面側との水位差が大きい。
- 破壊現象
- 掘削底面に上向きの浸透流が発生し、この浸透圧が土の有効重量を超えると、沸騰したように沸き上がり、土がせん断抵抗を失います。
- 設計手法
- Terzaghi理論による方法と限界動水勾配を考える方法があります。
(詳しくは、上記文献をご覧になって下さい。)
- Terzaghi理論による方法と限界動水勾配を考える方法があります。
- 盤ぶくれ
- 地盤状態
- 掘削底面付近が不透水層(粘性土、細粒土)で、その下が水頭の高い透水層。
- 破壊現象
- 不透水層下面に上向きの水圧が作用し、これが上方の土の重さ以上となると、掘削底面が膨れ上がり、最終的には不透水層が突き破られ、ボイリング状の破壊となります。
- 設計手法
- 揚圧力(上向きの力)と抵抗力(下向きの力=自重)との平衡条件から算定できます。
盤ぶくれ対策として行なう薬液注入では、改良範囲の直上に未改良部分を残して、改良部と未改良部分を合わせた全重量を抵抗力としています。
- 揚圧力(上向きの力)と抵抗力(下向きの力=自重)との平衡条件から算定できます。
- ヒービング
- 地盤状態
- 掘削底面付近に軟弱粘性土が厚く堆積している。
- 破壊現象
- 土留め背面側の土の重量や上載荷重により、すべりが生じ、掘削底面の隆起、土留めのはらみや隆起、土留め背面地盤の沈下などが生じます。
- 設計手法
- eckの安定数Nb(=γH/Su)を計算し、その値によって詳細検討を加えるか判断します。Nbが5を超えると、ヒービングの危険性が高く、地盤改良等の対策を行なう事例が多くなっています。
砂礫土・粘性土の互層地盤の場合の検討方法についてですが、土留め矢板がどの層まで根入れしてあるかにより、ボイリングが生じやすいのか盤ぶくれが生じやすいのかという違いがあり、検討方法が異なります。 具体的には、掘削側の矢板の根入れ部分より上に不透水層が存在している場合には盤ぶくれ、矢板の根入れ部分より上に不透水層が存在していない場合にはボイリングを検討すればよいものと考えられます。
地盤沈下・液状化・地盤変形に関する質問
埋立地の天日乾燥によって表層処理なしで重機覆土可能か
グラブ浚渫土をバージアンローダ方式により埋め立て地に投入しました。覆土開始までに3年程度放置することが可能です。3年後には天日乾燥による強度発現によって表層処理なしでの重機覆土が可能となりますか?
天日乾燥が可能な地盤と書かれていますので、埋立て地盤の天端が地下水位(平均満潮位)よりも高く、かつ表面排水が継続的に行われていると仮定します。この仮定が成り立たない場合は、重機覆土ができないことは言うまでもありません。
日本道路協会の道路土工−施工指針によると、重機の走行に必要な地盤強度の目安は、以下の表−1のようになっています。したがって、埋立て地盤の表層1〜2mの部分が3年間の天日乾燥によって、これらの強度を上回っていれば重機による直接撒きだしが可能です。ただし、重機が複数回走行すると、練り返しにより地盤強度が低下するので注意が必要です。
埋立地盤上の表面排水を継続的に行うと天日乾燥によって表層に固い皮殻層が形成され、時間とともに厚さを増していきます。この部分の強度発現は埋立て粘性土の土質や現地の気象条件等によって異なるため一概に判断することは困難ですが、一般的には2〜3年程度の放置によって、この皮殻層は40〜50cm程度に発達し、人間が歩行できる程度(粘着力c=1.0〜1.5tf/m2程度)になると言われています。これをqc=10×cの関係を用いて、コーン指数 qcに換算すると、qc=10〜15tf/m2程度の強度が得られることになります。
| 建設機械の種類 | コーン指数qc (tf/m2){kN/m2} |
|---|---|
| 超湿地ブルドーザー | 20 {196}以上 |
| 湿地ブルドーザー | 30 {294} 〃 |
| 中型普通ブルドーザー | 50 {490} 〃 |
| 大型普通ブルドーザー | 70 {686} 〃 |
| スクレープドーザー | 60 {588} 〃 |
| 被牽引式スクレーパー | 70 {686} 〃 |
| モータースクレーパー | 100 {980} 〃 |
| ダンプトラック | 120 {1,176}〃 |
このコーン指数を表−1と比べると、最も接地圧の低い超湿地ブルドーザーでもqc=20tf/m2程度必要と言うことですので、地表面で重機を動かすには、地耐力が不足していると言えます。また、皮殻層下部の−0.5〜−2m程度の軟弱部分の強度はさらに低く一般に軟弱な状態を呈しており、重機の走行によって表層の皮殻層が割れるとその隙間からこの軟弱粘性土が噴出して、大きな破壊に至ることになります。したがって、仮に表層皮殻部の地耐力が重機の走行を満足するとしても、安全に施工を行うためには何らかの表層処理が必要であると言えます。
このような場合の表層処理としては、表層固化処理によって覆土材などの運搬路を碁盤の目状に施工し、その中をジオテキスタイル等によって補強してから覆土を行うという工法が一般的です。
ポンプ浚渫による埋立地盤高の予測方法
ポンプ浚渫した粘性土で埋立を行っていますが、埋立地盤高の予測はどのように行えばよいのでしょうか?
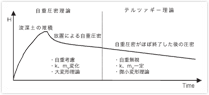
埋立地盤高(最終地盤高)の予測は、投入した時の含水比と物理試験、圧密試験の結果があれば予測することができます。投入土は放置期間を経て、土被り圧に応じた間隙比(含水比)に落ち着くため、投入時の含水比との差から地盤高を求めることができます。
圧密予測の理論ではテルツァーギの圧密理論が有名ですが、ご相談のポンプ浚渫などのやわらかくて沈下量が大きい場合には適用できません。浚渫土のような高含水比の粘性土が連続して投入される場合、変形量が大きくかつ粘性土の自重が荷重となるため、テルツァーギ理論は適用が難しく、自重圧密理論を用いる必要があります。
当社ではこのような地盤でも容易に解析を行える汎用性の高いプログラムを保有しています。このプログラムを用いることにより、埋立開始から放置期間に至るまでの任意の時刻における地盤高を求めることが可能になりますので、精度の高い埋立計画を立案することが可能となります。
柔構造において即時沈下を求める際の設計荷重
柔構造において即時沈下量を求める際、上載荷重(活荷重)を考慮しなくてよい場合とはどんな場合ですか?またある検討書では雪荷重を考慮しております。雪荷重は積載荷重であり、活荷重ではないと思います。圧密沈下ならともかく、即時の沈下に積雪を考慮する必要があるのか疑問です(現場は東北地方です)
構造物設計では荷重の組合せを考える場合、その構造物にもっとも不利になることを考えます。道路橋示方書では、雪荷重は主荷重ではなく、従荷重として示されています。道路では路面の雪荷重と活荷重(自動車荷重)が同時に載荷されることはありません。したがって雪で道路閉鎖時の積雪荷重か若干の圧雪の上の自動車荷重という表現であり、100kg/m2程度の死荷重として与えます。(しかも通常の設計での荷重の組み合わせには風等の荷重は有りますが雪荷重はなくなってしまうのです。)もちろん、構造物に鉛直軸力が有利に働く場合はカウントしません。また、トラス材等に雪がたくさん付着して本体に影響を与えるなら、当然荷重とするべきです。
さて、樋門等ではどのように考えるべきでしょうか。
今回の問題では即時沈下ですから雪荷重は死荷重扱いでよいと思います。結論は構造物に不利となる場合は実際を想定して載荷すべきと考えます。また、推測で申し訳ありませんが、柔構造樋門で活荷重としているのは、雪は死荷重ではない(常時はない)からその他の荷重(活荷重)としているのではないでしょうか。これも、推測ですが、樋門の場合なにか活荷重だと構造物に不利になる場合が想定できるのではないでしょうか。
軟弱シルト層上に擁壁を設置する際に沈下を考慮すべきか
h=10mの擁壁設置を計画していますが、下部地盤に軟弱シルト層が存在します。また支持層まで50m以上あることから、直接基礎を採用したいと考えています。上載荷重を15t/m2以下で抑えられるようベースの検討をしていますが、この場合沈下による影響は考えるべきでしょうか。
ご質問の件では、まず、シルト層の圧密に関する定数を的確に知る必要があります。以後の議論に対して、この定数が不明である場合、地盤改良自体が過大になる恐れがあります。
まず、圧密試験を実施して、各シルト層のCvやCc、e0といった値を求めます。擁壁の荷重15t/m2が圧密荷重になって生じる沈下がどの程度のものになるかは、圧密の諸定数が分かれば推定できます。この検討では、以下の3つの変形パターンの検討が必要です。
- 擁壁の沈下
- 擁壁の作成による側方流動
- 擁壁の沈下に伴う周辺地盤の連れ込み沈下
また、変形後の転倒検討や円弧滑りによる支持力検討も必要ですね。
有害な沈下・変形が生じる場合、対策が必要です。対策としては、以下の2つが考えられます。
- 上載荷重+ドレーン:安価 施工後3ヶ月程度放置が必要
- 固化工法:高価 短期間で有効
実際の施工機械などの検討が必要でしたら、ご連絡下さい。また、弊社では土質試験もできますので、お気軽にご相談下さい。
河川を埋め立てる際のヘドロに必要な試験内容と処理方法
現河川を埋め立てて道路利用する場合、ヘドロそのものに必要な試験内容および1試料当たりの金額はいくら位ですか。有害な重金属類が含まれているヘドロの処理方法にはどんなものがありますか。またヘドロを原位置で固化改良する時に必要な試験内容と、その単価について教えてください。
1.ヘドロそのものに必要な試験内容および1試料当たりの金額
ヘドロに限らず、土壌の特性を確認するためには物理特性試験を実施する必要があります。主な内容と金額は、右表のようです。
| 土粒子の密度試験 | 7,130 |
|---|---|
| 含水比試験 | 1,890 |
| 粒度試験 | 15,200 |
| 液性限界試験 | 8,820 |
| 塑性限界試験 | 4,200 |
| 強熱減量試験 | 9,600 |
| 合計 | 46,840 |
直接費
また重金属が含まれている場合は、環境省告示46号の溶出試験が必要です。土壌環境基準のうち重金属に相当するのは、カドミウム、シアン、鉛、六価クロム、ヒ素、水銀、セレン、フッ素、ホウ素であり、試験費用は1金属当たり5,000円程度です。ですから5種類試験した場合には、1試料当たり 25,000円となります。土壌中の重金属の含有量は場所により大きく異なるため、詳しく調査するためには25,000円×採取箇所が必要です。
2.有害な重金属類が含まれているヘドロの処理方法
汚染土壌の修復は、汚染物質を取り除く「浄化」が原則ですが、重金属汚染されたヘドロを安価に浄化する手段は今のところありません。そこで通常は、汚染物質を物理化学的に封じ込める「固化・不溶化」が採用されることが多いようです。固化不溶化処理方法は、重金属の種類により異なりますが、弊社では、カドミウム、鉛、水銀などはセメント系固化材による固化処理、ヒ素、六価クロムなどにはキレート剤、あるいは固化材と薬品を併用しています。また改良土を有効利用することを目的に、ヘドロの造粒固化不溶化処理することもあります。本工法によればヘドロが数分で砂状に改良できますので有効利用が容易になります。ただし汚染土壌を有効利用するためには、役所などの承認が必要となります。
3.ヘドロを原位置で固化改良する時に必要な試験内容、単価
ヘドロを原位置で固化処理する場合には、配合試験が必要となります。配合試験では、固化材の量を3種類程度変化し、それぞれの強度と不溶化効果を確認します。
- 配合試験
- 一軸圧縮試験(7日、28日)
- 溶出試験(7日材齢)
- pH試験
配合試験は一式でおよそ100万円程度になります。また固化処理土の利用用途に応じて、三軸圧縮試験、CBR試験などが必要になることもあります。
粘土の脱水ケーキによる埋立方法について
埋立時における施工厚に関して。
粘土の脱水ケーキを0.6 〜 1.8m層厚撒きだした後、覆砂を0.5m厚施工する予定です。
脱水ケーキを1層にて仕上げた後、覆砂すると必要天端高を確保するためには必要以上の砂の投入が必要となるので脱水ケーキを数層に分けて投入した後、覆砂を施工しようという設計案があります。
脱水ケーキ層の圧密を考慮し、余盛高を決定するのが筋だと思うのですが、脱水ケーキ層の圧密を設計上は考慮しないとした場合、上記のように数層に分けて施工する意味があるとお考えでしょうか?
海上工事における埋立(施工)厚に関して。
埋立材料の変動、円弧すべりおよび施工方法により埋立(施工)厚は決定されるかと思いますが、安定上問題なければ海上工事における一般的な埋立(施工)厚はどれ位なのでしょうか。
上記質問の返答においては土性や、施工方法、工期等絡むので返答に困られるかと思いますが、最大1.8mの埋立を段階施工する意味は少ないかと思うのですが、いかがでしょうか。なお、円弧すべり等の安定上の問題はありません。造成後、天端を車が走るということもありません。単なる人工干潟造成です。造成の目的上は天端高を確保しなければならないという必要性はないのですが。
粘土の脱水ケーキ(h=1.8m)層の上に覆砂(h=0.5m)を行い、人工干潟を造成するということですが、現地の状況が詳しくわからないので一般論としてお答えします。
Q1.脱水ケーキを1層にて仕上げた後、覆砂すると脱水ケーキの圧密沈下が大きく、余分に覆砂が必要となるため、脱水ケーキを数層に分けて投入し、圧密沈下量を低減できないか?
A1.沈下の検討には、まず、脱水ケーキの含水比を知る必要があります(どの程度過圧密となっているか知る必要があります)。脱水方法には真空脱水、遠心脱水、機械脱水など様々な方法があり、脱水効果は液性限界含水比wLの0.9〜1.1倍程度が目安となります。また、後者ほど脱水効果が高く脱水ケーキのハンドリング(トラックなどで運搬)が容易になります。粘土をハンドリング可能な含水比まで脱水するものと考えれば、脱水方法はフィルタープレスなどの機械脱水であると考えて回答を進めます。
標準的なフィルタープレスの給泥圧力は0.5〜0.7Mpa(50〜70tf/m2)程度であり、脱水ケーキの含水比は0.9wL程度以下になります。例えば、wL=80〜120%(間隙比e=2〜3.2)の粘土であれば、0.9wL=70〜110%(e=1.8〜3)になります。
土質データがないので「土質試験の方法と解説(第1回改定版),p374,(社)地盤工学会」のe-p関係を参照にすると含水比0.9wLの粘土は圧密圧力p=3〜5tf/m2程度で圧密が終了した状態に相当しています (この圧密圧力が圧密降伏応力pcとなります)。
さて、圧密降伏応力pc=3〜5tf/m2の脱水ケーキは覆砂(h=0.5m)で沈下するかを考えてみます。人工干潟を造成するということなので干潮時には覆砂の湿潤重量が圧密圧力として作用するものと考えると圧密圧力はp=γh=1.8×0.5=0.9tf/m2となります。p<pcであるため覆砂後の脱水ケーキは過圧密状態であり覆砂の荷重ではほとんど沈下しないものと考えられます。
また、脱水ケーキを数層に分けて投入したとしても、ほとんど沈下しないという状況は変わりません。
Q2.脱水ケーキによる一般的な埋立厚?
A2.現地の状況によって脱水ケーキ投入方法も異なるため、一般的な埋立厚について明言はできませんが、地盤の安定上問題がないのであれば、施工上は厚さ0.5m以上あれば問題なく施工できると考えられます(薄層に撒き出す方が難しい)。
なお、浅瀬への脱水ケーキ投入方法としては以下のような方法が考えられます。
- 脱水ケーキを台船で海上運搬する場合
- 浅瀬まで台船で運び台船上のペイローダで直投
- 浅瀬までベルコンスプレッダー付き台船で運び直投
- 沖の台船からフローティングコンベアで投入位置まで運ぶ
- 脱水ケーキをダンプトラックで陸上運搬する場合
- 陸上基地からフローティングコンベアで投入位置まで運ぶ
- 潮間をみてダンプトラックで直投
- 浅瀬に仮設桟橋、仮築堤を作りダンプトラックで直投
柔構造樋門においてプレロード後の即時沈下を考慮すべきか
「柔構造樋門 設計手引き」の即時沈下量の考えなのですが、”即時沈下量はプレロード等の事前載荷荷重の有無にかかわらず函体施工以降に行う床付け面より上の盛土の全荷重を用いて算出する。”とされています。実際、プレロード盛土の掘削→埋め戻しに対する即時沈下量は考慮するべきなのでしょうか。なお、現地での開削後のチェックボーリング調査は行わないということです。
従来、沈下が問題となる地盤上に樋門を建設する場合には、基礎構造を支持杭とするのが一般的でした。この場合には樋門と堤体の変形に差が生じるため、接触面に空隙が発生し易く、これが原因で漏水によるクイックサンド現象(液状化)や吸い出しなどが発生し、弱点となる可能性がありました。これを防止するためには鋼矢板などによる遮水壁を設けるという対策がとられていました。ご存知の通り、このような弱点を克服(変形に追従)するとともに、沈下をある程度許容することで基礎構造をスリム化し、コスト低減を謀った樋門形式が柔構造樋門です。国や地方公共団体は、コスト低減策として積極的に採用しようとしており、平成10年に(財)国土開発技術研究センターより発行された「柔構造樋門設計の手引き」に準じて設計を行っています。
事前に断っておきたいのですが、当社では樋門建設分野にはそれほど強くなく、「柔構造樋門設計の手引き」も蔵書してないのが現状です。しかし、即時沈下に関しては他分野の設計手法と共通の考えと思われるので、回答を進めたいと思います。
「実際、プレロード盛土の掘削→埋め戻しに対する即時沈下量は考慮するべきなのでしょうか。」というご質問ですが、設計書に「即時沈下量はプレロード等の事前載荷荷重の有無にかかわらず函体工以降に行う床付け面より上の盛土の全荷重を用いて算出する。」と書かれているなら、設計行為としてはこれに従い考慮すべきでしょう。そもそも、柔構造樋門は沈下が問題となる場所に採用されるものなので、最大に沈下する状況を想定して設計する必要があると思います。
沈下には、以下の3種類があり、これらを合計すると全沈下となります。
1.即時沈下:即時的なせん断変形による沈下
2.圧密沈下:長期間にわたる脱水による沈下
(3.クリープ沈下:脱水が事実上終了してもなお続く沈下)
上記の内どれを最も考慮して設計すべきかは、建設着手時の地盤の状況、樋門の重量によって異なり、例えば、建設後の圧密沈下が問題にならないのであれば、即時沈下のみを考慮すれば良いでしょう。しかし、建設後の圧密沈下が問題になるようなら即時沈下と圧密沈下の両方を考慮する必要があります。ただし、即時沈下は建設中に終了してしまう場合がほとんどであり、即時沈下より圧密沈下の方が大きいことを考慮すると圧密沈下のみを考慮して設計しても問題ないものと考えられます。
ご質問の中で重要なのが「実際」という一語です。ご質問の状況は前述した即時沈下のみを考慮すれば良い場合と判断して回答します。構造物を建設する場合、多かれ少なかれ”実際”に即時沈下は発生していると考えられます。他分野の設計手法でも共通ですが、即時沈下量は地盤を弾性体と仮定して算出され、同一荷重条件下では、地盤のヤング係数Eが小さいほど、沈下量は大きくなります。「実際、・・・・考慮すべきなのでしょうか。」というご質問の背景には、「プレロードにより既に砂地盤は締まっている、粘土地盤は圧密により強度増加しているはずであり、地盤のヤング係数Eは大きくなっているのに即時沈下を考慮する必要があるのか。」という考えがあると思いますが、これに対する私の見解は、「設計上は大きくなったEを用いて即時沈下を計算した方が良い、即時沈下を考慮すべきか否かはこの計算結果が構造物に対して無視して良いほど小さい値か否かにかかっている。実測結果はこの沈下量より小さくなる可能性が高いかもしれない。」ということです。非常にあいまいな表現で申し訳ありません。
「尚、現地での開削後のチェックボーリング調査は行わない」というなので、設計に用いるEを決定しにくいと思いますが、参考までに、『建築基礎構造設計指針』にはN値からEを換算する方法として、
- 正規圧密の砂:E=1.4N(MN/m2)
- 過圧密の砂:E=2.8N(MN/m2)
という式があり、プレロードによる効果を過圧密とみなし、プレロード後のヤング係数Eはプレロード前の2倍とする考え方もあります。
柔構造樋管の即時沈下算出時の荷重条件について
柔構造樋管の即時沈下算出方法については、道路土工指針同様に半無限長の沈下量算出方法で求めることとなっています。これは、載荷幅方向については低減される様な計算になっていますが、すでに築堤済みの箇所を掘削し樋管を設置するような場合は、奥行き方向の低減も考慮した有限長の沈下量算出方法をとる必要があるのではないでしょうか?またその必要がある場合は、計算方法についても教えてください。
ご質問に「すでに築堤済みの箇所を掘削し樋管を設置するような場合は・・・・」と書かれていますが、河川堤防を横断して設けられる樋門・樋管の大部分が、ご質問の条件に相当するため、基準書に従う一般的な設計が可能と考えられます。
柔構造樋門・樋管の設計は「柔構造樋門設計の手引き(財)国土開発技術研究センター」に従うものとされており、同書p83には、「地盤の沈下量は、砂質土では即時沈下量、粘性土では即時沈下量と圧密沈下量を考慮する。」その解説には、「即時沈下量Siは、プレロード等の事前載荷重の有無に関わらず、函体施工後に行う床付け面より上の盛土の全荷重を用いて算出する。」と書かれていることから、砂質地盤上の柔構造樋門・樋管の設計では、新設堤防、既設堤防によらず、函体床付け面より上の盛土の全荷重を用いて即時沈下を算出することになります。なお、粘性土地盤の圧密沈下量Scは、既設堤防からの地盤内鉛直応力増分を用いて算出します。
「既設堤防を開削して樋管を設置する場合には、帯状荷重ではなく、有限長の荷重(矩形荷重)を用いて沈下量を算出する必要があるのではないか」という質問に対しては、同書p84の即時沈下量の解説にある「堤体を等価な複数の帯状荷重に近似して沈下量を算出して良い」という記述に従えば、有限長の荷重を用いて沈下を算出する必要はないということになります。
設計基準というのは決めごとであり、厳密に考えれば学術的におかしな点があったとしても、これらの不具合や許容範囲を考慮した上で基準化されているため、設計書が取り扱っている範疇を外れない限り、基準に従えば良いものと考えています。なお、特殊・重要・大規模構造物では大学の先生を交えた検討委員会が発足されたり、3次元FEM解析などを用いた詳細検討が必要となったりします。
柔構造樋門・樋管のような新しい設計思想においては、施工事例、観測事例などを反映しながら、設計に不具合があれば、今後、順次改訂されていくものと認識しています。
河川頭首工エプロン基礎部の吸出し空洞補修方法
河川の頭首工の改修工事をしているのですが、改修部分のコンクリートを取り壊したら、改修計画のない、上流エプロン部の基礎部に空洞(約1m)および泥層(約1m)が確認されました(以前の災害復旧工事の施工時に吸い出しがあったらしい)。空洞部分は扉体30mの内の15mです。
扉体に影響が出ないように上流エプロン部を補修したいのですが、良い工法があれば教えてください。
なお、扉体下には止水矢板を打っており、扉体下の地盤は現在のところ空洞になっていません。
また、応急措置として、上流エプロンの前40cmのところに止水矢板を打ちました。
頭首工の上流側エプロン下が吸い出しを受けて空洞となり泥が溜まっている部分についての対策工とのことですが、改修工事の最中であって前面止水矢板が打設出来ているとすると、川替えが出来ておりドライ施工をしている状況であれば、空洞上部のエプロンに数点削孔をして、エア(水)抜孔を確保しながら(気泡) モルタルを充填していくのが一般的かと思います。
充填性を良くするためと、充填材を軽量なものにして下部泥層の沈下を抑えるという意味から、ただのモルタルではなく、気泡モルタルによる方が望ましいと思います。この時、比重が1を下回ると、エプロンに浮力が働いてしまうため、比重が1.1〜1.3となるように密度管理には若干留意が必要となります。
また、現地に利用できる発生土があれば、条件によっては「気泡混合処理土」工法も利用できるかと思います。これは発生土にセメント・水を混ぜてスラリー状にしてから気泡剤を混ぜて対象箇所に充填していく工法で、条件によっては気泡モルタルよりも安価になると思われます。気泡混合処理土については、(財)土木研究センターが発行している「発生土利用促進のための改良工法マニュアル」等をご参照下さい。
水替えをせずに水中で流れがあるままというのは、大変施工が難しいと思われます。現地の利水状況等によって、水替えが出来ない場合はエプロン前面に打設した止水矢板を利用して隙間を塞いでから中を充填という方法を採らざるを得ないと思います。
吸い出しを受けた箇所にシルトが溜まる、あるいは、災害復旧の施工時に吸い出されたというのが良く状況が分かりませんが、まず空洞が出来た原因と吸い出された場所(水みちとなった経路)・経緯などをきちんと特定することが再漏出を防止する上では非常に重要であると思います。
表層固化の近接施工
深さ3m(幅14m 長さ100m)の表層改良をロータリー式攪拌工法で計画しています。計画している位置から5m付近に鉄塔基礎(鋼管杭基礎)があるのですが、表層改良による影響(杭変位等)はあるのでしょうか?
また、基礎への影響がある場合、どういう検討が必要か教えて下さい。
軟弱地盤の表層固化処理時の近接施工についてのご質問ですが、過去の事例を調べても、表層固化処理で近接構造物に問題が発生したという事例はありませんでした。
深層混合処理で深い(20m程度)部分まで改良を行った場合に、7〜10cm程度の水平変位があり、いろいろと事前検討等を行った事例はあるようですが、表層固化深さ3m程度で固化材添加量が特別に多いのでなければ、それほど大きな変形は起こらないのではないかと思います。
近接施工ですので地盤変位の観測施工を行うことは必要です。改良範囲14m×100mを深さ3m改良というと、軟弱地盤上に道路等を作るための基礎部の表層固化のように思われますが、そうであれば、表層固化処理を行った後で、ドレーン打設や盛土の工程があると思われます。この場合、表層固化よりも、その後の工程における地盤変位の方が大きくなる可能性が高いため、十分に注意する必要があると思います。
表層固化処理時の周辺地盤の水平変位の事前の検討を行う手法は確立されておりませんが、例えば固化材の添加量をそのまま体積膨張量として水平変位に換算し、FEM上で強制変位として与える方法などが考えられます。どのような解析方法を使うにしても、地盤条件の設定は難しいため、観測施工のデータを用いて逆解析を行って地盤条件を補正しながら施工を進める必要があると思います。
また、施工計画に当たっても有害な変形を起こさないような施工手順を考慮することも有効であると思います。
例えば、固化をする順序を鉄塔側から始めてだんだんと離れる方に向かって施工することで鉄塔付近の施工時の逃げ道をなるべく多く残すようにしたり、事前に固化材を入れずに攪拌機のみで空堀をしてから施工することで変位が抑制できたという事例があります。(参考文献1)
最後になりましたが、参考までに、地盤改良工事における近接施工の計測事例について紹介します。
深層混合処理を行った場合、固化材の体積混入率が0.05程度で構造物の水平変位が3cm程度、体積混入率0.1を超えると水平変位が7〜10cm程度見られた事例や、構造物からの離隔と水平変位との関係では離隔2m以内では10cm程度の変位が見られることもあるが、距離が離れると水平変位が減衰して5m程度の離隔だと4〜7cm程度以下になったという事例があります。(参考文献2)この文献では他工法として生石灰パイルやサンドドレーン、既製杭打設と比較したデータが載っています。
【参考文献】
- 近接施工技術総覧 (株)産業技術サービスセンター発行
- 近接施工(土質基礎工学ライブラリーNo.34) 土質(地盤)工学会発行
砂粘土互層地盤の液状化について
砂質土と粘性土の細互層(層厚10〜30・程度)の場合、液状化の検討は必要なものでしょうか。
必要な場合は、各層それぞれの粒度試験及び換算N値を推定するのでしょうか。
ちなみにこの層はGL−5〜10m程度の深度に分布しています。N値は6〜10程度の沖積層です。
液状化の判定および予測に関しては、構造物等によって基準が若干異なります。
例えば、港湾構造物では、一般に、粒度とN値による簡易法を用います。また、この簡易法のみでは、判断出来ない場合は、繰返し三軸試験や地震応答解析を行い、液状化判定を実施します。
詳細は、以下の文献を参照願います。
港湾構造物では、
「埋立地の液状化対策ハンドブック(平成9年)」(財)沿岸開発技術研究センター
また、道路橋等では、粒度(平均粒径、細粒分含有率)とN値および設計水平震度から液状化抵抗率を算出し、液状化の判定を行うのが一般的です。
詳細は、以下の文献を参照願います。
道路橋等陸上構造物では、
「道路橋示方書・同解説 ・耐震設計編(平成14年)」(社)日本道路協会
ところで、以下の条件で液状化検討が必要かどうかについてですが、
- 砂質土と粘性土の細互層(層厚10〜30・程度)
- N値は6〜10程度の沖積層
- GL−5〜10m程度の深度
先ず、深度については、各基準でもGL-20mまでは液状化すると判断するのが一般的です。N値についても、液状化の可能性は高いと判断できると考えられます。ところが、対象土が砂質土と粘性土の細互層であることから、液状化の判定はかなり難しいと考えられます。
このような地盤の液状化判定は、構造物の重要度等を考慮し、地盤全体としての判定をする必要があります。一般的に、互層であるとは言え、例えば、砂質土層の中に不連続な独立した粘性土層が存在している場合のように、その層が地質学的に、沖積砂層が卓越すると判断される場合には、液状化すると判断するのが妥当であると考えます。
一方、反対に、沖積粘土層が卓越すると判断される場合は、液状化する可能性が低いと判断できると思います。
例えば、上記文献「埋立地の液状化対策ハンドブック」pp124によると、
「木造家屋などの小規模な構造物では、地下水位がGL−2.0mであり、最大加速度が200gal程度であれば、液状化層(砂質土層)が2m以下であれば、地盤全体としての液状化は発生しないものと判定される。」
「重力式護岸背後地盤の検討において、ほぼすべての土層で液状化しないと判定されるが、1m間隔で得られたN値のうち1ないし2点の深度において液状化すると判定される結果となった場合は、地盤全体として液状化しないと判定してもよい。しかし、重力式護岸直下の地盤のように、その構造物に支配的な影響を与える部分で液状化の恐れがある場合などでは、液状化層(砂質土層)が1mであっても、慎重な検討が必要となる。」
以上、設計者としての判断にゆだねられる部分も多いと思います。
縁切り矢板によるつれ込み沈下防止について
盛土工において周辺地盤のつれ込み沈下防止(縁切り)のために、盛土下部改良地盤の1メートル横に矢板を打つ計画をしています。圧密沈下計算を行なう際の盛土の荷重分散角は30度と考えて良いのでしょうか。
また、盛土下部にセメント固化などの地盤改良が施工してあれば、盛土荷重による周辺地盤のつれ込み沈下や側方変位は防げるのでしょうか。
まずは、「盛土下部にセメント固化などの地盤改良が施工してあれば、盛土荷重による周辺地盤のつれ込み沈下や側方変位は防げるのでしょうか。」というご質問についてお答えします。
厚い軟弱地盤の表層部分のみを改良したのであれば、周辺地盤の変位を防止する効果は小さいものと考えられます。
盛土下部の軟弱地盤層厚に対して、セメント固化改良層厚が厚くなるに従って、セメント固化改良による周辺地盤のつれ込み沈下や側方変位の防止効果は大きくなます。当然ながら、軟弱地盤全層をセメント固化すれば、盛土による沈下も、周辺地盤への影響も(ほとんど)なくなります。
セメント固化を行なうことによって、周辺地盤の変位がどの程度低減されるかを算出するには、FEM解析などによる地盤の変形解析が必要となります。
沈下低減効果については以降で述べる簡易設計も可能ですが、側方変位については、FEM解析が必要不可欠であると考えています。この点についてはQ&A70も参考にして下さい。
ご質問では、周辺地盤のつれ込み沈下防止(縁切り)のために矢板を施工するということですが、矢板の剛性が十分であり、かつ、ある程度硬い層まで根入れされていれば、盛土による鉛直荷重は矢板で遮断され、周辺地盤のつれ込み沈下は発生しないものと考えられます。
矢板で遮断された内側(盛土側)の圧密沈下量を算出するには、一般に以下の方法を用いることが多いのではないかと思います。
(1)盛土荷重が荷重分散角α(通常α=30°)で一様に分散するものと考えて、改良地盤下部での鉛直荷重を算出する。この方法をボストン・コード法と呼びます。
ただし、セメント固化改良層厚が盛土載荷幅に対して十分に厚い場合には、荷重分散角を考えずに、盛土とセメント固化地盤を一体と考えて、全重量を改良地盤下部に一様に分散させます。
(2)上記(1)で求めた鉛直荷重の軟弱地盤内の任意の地点への分散を求めるには、一般に、等方弾性半無限体中の応力分散解であるブーシネスクの地中応力算定公式を用います。この公式を用いて軟弱地盤の層中央での鉛直応力増分を算出します。
(3)上記(2)で求めた軟弱地盤の層中央での鉛直応力増分を用いて圧密沈下量を算出します。
なお、矢板の内側(盛土側)での圧密沈下量が大きい場合には、矢板は周辺地盤を支える山留め(土留め)となるので、周辺地盤を変形させないためには、自立山留めとしての検討も行なっておく必要があります。
擁壁・斜面安定に関する質問
サンドコンパクションの設計方法と適用可能な地盤
サンドコンパクションの設計、適応可能な地盤を教えてください。また砂地盤上に盛土の計画があるのですが、安定解析を行えば所定の安全率が満足されず、対策工が必要となります。砂地盤の取り扱いについてどう考えればよろしいのでしょうか?現実的にはすべらないと思いますが・・。
■サンドコンパクションの適応可能な地盤
まず、サンドコンパクションの適応可能な地盤についてですが、一般に砂質土地盤から粘性土地盤までいずれの軟弱な地盤に対しても適用可能です。ただし施工機械の自重を支持できる地盤であることが施工の条件となります。
■サンドコンパクションの一連の設計方法について
サンドコンパクションの設計ですが、砂質土地盤に適用する場合と粘性土地盤に適用する場合とで設計に対する考え方が異なります。
1.砂質土地盤に適用する場合:砂質土地盤に対する設計の基本概念は、ゆるい砂質土地盤にSCPを打設することにより砂質土の間隙比を小さくし、地盤の密度増大を図るものです。SCPの改良効果はN値により示されるが、改良後のN値は、改良前の原地盤のN値と置換率により支配されます。
設計手法としては、大きく分けて三つの手法、1)施工実績からまとめられた図表を元に置換率、改良後のN値を求める方法、2)Gibbs-HoltzのN-Dr-eの関係及び粒度と最大・最小間隙比の関係を用いる方法、3)基本的には(2)に同じだが、細粒分による改良効果の低減率を導入した方法、などがあります。
2.粘性土地盤に適用する場合:粘性土地盤に適用する場合は、砂杭と粘性土からなる複合地盤または改良地盤全体を一様な砂地盤として扱い、円弧すべり計算による安定性の検討、圧密沈下量および圧密速度の検討などが行われています。
■砂地盤の安定解析について
土を砂質土として取扱うか、粘性土として取扱うかは、設計を行う上で非常に重要です。一般に土は内部摩擦角φと粘着力cの両方に依存する性質を持っていますが、設計ではどちらかを無視して考える方法が多く用いられます。どちらの影響を無視するか、あるいは両方を考慮すべきかは土質試験の結果をよく判読して決定する必要があります。
つまり、土質データに信頼性がある(試験点数、試験方法が適切)場合には、設計定数としてcとφの両方を考慮して良いということです。ご質問に「安定解析を行った結果、所定の安全率を満足しないため対策工が必要となる」と書かれていますが、適切な土質定数および設計手法を用いての安定解析結果であるなら、たとえ「現実的には、すべらない」と考えられていても対策工が必要となります。対策工としては、盛土法面を緩勾配にする(カウンターウェイトを増やす)、SCP等で現地盤の強度増加を謀る、抑止杭または土木シートを用いてすべりに対する抵抗を増す等の方法が考えられます。
なお、気になりましたのは砂地盤で支持力が確保できないと言う点です。通常、φ=30度程度の砂地盤の円弧滑り等で持たないことはほとんどありません。近隣の同様な構造物で安定している断面があるのでしたら、そこの断面形状について、円弧滑り検討を実施し、安全率が1.1程度になるφとCの組み合わせを見つけてみてはいかがでしょうか?この方法は逆解析と言われます。この逆解析で得られたC、φと想定されているφとを比較して、想定しているφがとても小さければ、φをもう一度見直す必要があると思います。
軟弱シルト層上に擁壁を設置する際に沈下を考慮すべきか
h=10mの擁壁設置を計画していますが、下部地盤に軟弱シルト層が存在します。また支持層まで50m以上あることから、直接基礎を採用したいと考えています。上載荷重を15t/m2以下で抑えられるようベースの検討をしていますが、この場合沈下による影響は考えるべきでしょうか。
ご質問の件では、まず、シルト層の圧密に関する定数を的確に知る必要があります。以後の議論に対して、この定数が不明である場合、地盤改良自体が過大になる恐れがあります。
まず、圧密試験を実施して、各シルト層のCvやCc、e0といった値を求めます。擁壁の荷重15t/m2が圧密荷重になって生じる沈下がどの程度のものになるかは、圧密の諸定数が分かれば推定できます。この検討では、以下の3つの変形パターンの検討が必要です。
- 擁壁の沈下
- 擁壁の作成による側方流動
- 擁壁の沈下に伴う周辺地盤の連れ込み沈下
また、変形後の転倒検討や円弧滑りによる支持力検討も必要ですね。
有害な沈下・変形が生じる場合、対策が必要です。対策としては、以下の2つが考えられます。
- 上載荷重+ドレーン:安価 施工後3ヶ月程度放置が必要
- 固化工法:高価 短期間で有効
実際の施工機械などの検討が必要でしたら、ご連絡下さい。また、弊社では土質試験もできますので、お気軽にご相談下さい。
根入れ不足の親杭横矢板の親杭周り地盤改良方法
アンカー付きの親杭横矢板による垂直土留め壁(永久構造物)を工事しております。設計では親杭の下端を基岩へ1.5m貫入することになっていましたが、想定していた深度から基岩が出現せず、軟弱層への貫入で工事が完成してしまいました。親杭下端に支点を与えておかなければアンカーを支点とする片持ち梁の状態となるため、親杭(H-300)の剛性が満足できません。そこで、軟弱層を地盤改良しようと思うのですが、親杭の安全性を確保しながらの工法としてどのようなものがあるでしょうか。教えて下さい。
「想定していた深度から基岩が出現せず、軟弱層への貫入で工事が完成してしまいました。」ということですが、一般には「想定していた深度から基岩が出現せず」という段階で発注者に現場条件の違いを報告し、設計変更を行う必要があったものと考えられます。
ここで、取られる対策としては、以下の3つでしょう。
- 親杭を継ぎ足して深部の基岩まで打ち込む。
- アンカーを増やすなど土留め壁の構造変更を行う。
- 軟弱層を基岩相当の強度もしくは設計上安定が保てる強度まで地盤改良する。
ご質問の状況は工事が完了してしまったということなので、おそらく3.地盤改良のみが対策可能なのでしょう。
親杭に近接して地盤改良を行う際のポイントは以下の通りです。
- 軟弱層を基岩相当の強度もしくは設計上安定が保てる強度まで地盤改良する。
- 親杭の変形を拘束するためには親杭外周に密着した地盤改良が必要。
- 地盤が軟弱な場合には、地盤改良施工中に親杭が変形しないように側方変位の少ない地盤改良工法を選定することが重要。
ご質問の現場状況に合った“特殊な”地盤改良工法は無いと思われるので、一般的な地盤改良工法を紹介して回答を進めます。上記条件123を満足するためには、サンドコンパクションなどの密度増大締固め工法ではなく、セメントを高圧で噴射攪拌する固結工法が良いでしょう。高圧噴射攪拌工法は、ロッド先端吐出口からセメントスラリーを水平方向に高圧噴射して、地盤を切削しながら地盤改良するため親杭と改良体が密着します。また、排泥を行うため、比較的周辺地盤側方変位の影響が少ないと思われます。
詳しくは、高圧噴射攪拌工法メーカーに相談してみてはいかがでしょうか。
崩壊斜面への薬液注入による止水効果
薬液注入及び地盤改良の止水効果について質問致します。崩壊した斜面の復旧工事を行っております。崩壊後、数ヶ月が経過しましたが斜面は一応安定しておりました。しかし、現状の安全率を1.03と仮定して、崩壊した土砂を除去しようとすると、安全率が0.87まで低下してしまいます。このため、再崩壊を防止する目的で崩壊した土砂に薬液注入工を施し、粘着力を増すことで地盤の強化を図ることを考えました。
薬液注入後に実施した標準貫入試験結果では、N値が向上しており、C=2/3Nの関係式から、目標とする粘着力が得れたことが確認できています。ここで質問ですが、崩壊した原因が、降雨による間隙水圧の増大と考えられるため、薬液注入された地盤内に降雨を浸透させたくないという思いがあり、注入後にどの程度止水効果が上がったのか、数値的に究明したいと思っております。透水試験では5.67×10(マイナス6乗)と、いわゆる「難透水層」であることが確認できております。しかし、発注者の意向としては、もっと具体的で明確な表現を求められています。具体的な方法がありましたら教えて下さい。
もう一つ質問ですが、崩壊して崩れ落ちた箇所については、「補強盛土工+地盤改良」によって復旧しました。この地盤改良を行った箇所での止水効果についても、上記同様、究明方法がありましたら、教えて下さい。最後になりましたが、最終の対策工法は、「コンクリート版+グラウンドアンカー工となっております。
ご質問の通り斜面崩壊の主原因は降雨であると考えられますが、降雨による斜面崩壊には以下のような様々なパターンが考えられます。
- 降雨により表層が浸食された。
- 降雨により土が水を含み土の重量が増したことによって斜面安定が保てなくなった。
- 降雨により斜面内に水の流れが発生し、間隙水圧上昇により有効応力が減少し斜面安定が保てなくなった。
- 斜面の透水性(排水性)が悪い場合には、降雨により斜面内部の地下水位が上昇し、水圧が斜面を押し出すために斜面が膨れあがり崩壊する。
ご質問の状況が上記のどれに当てはまるかは判りませんが、再崩壊を防止する目的で、崩壊した斜面に薬液注入を行い地盤の強化を謀るという対策は間違ってないと思います。
ただし、薬液注入を行うことで斜面は遮水壁となるので、例えば表層だけしか薬液注入を行わない場合には、上記4のような内水圧による崩壊を招くので注意が必要です。これを防止するためには、改良厚を十分にとり改良土の重量で、背面から受ける土圧と水圧に対抗できるように重力式擁壁として設計する。もしくは、改良厚が薄い場合には排水孔を設けるなどの圧抜き対策を行うことが大切だと思います。
前おきが長くなりましたが、ご質問の「地盤改良による止水効果の説明方法」についてお答えします。
一般的には「透水係数が10のマイナス6乗cm/s」というだけで難透水層と理解してもらえるのですが、正確には、「透水係数が小さい層が何mあるか」という「層厚」も考慮して難透水層かどうかを判断します。
例えば、『薬液注入工設計資料(平成12年度版) (社)日本薬液注入協会』を参照すると、仮設矢板欠損部の遮水工として薬液注入を行う場合の改良厚は、一般に複列注入が可能な厚み1.5m以上としているケースが多く見受けられます。これは、現場での湧水量などを反映した経験値であると考えられます。この場合、「薬液注入により透水係数が10のマイナス6 乗cm/sの層が1.5m以上複列注入してあるので十分に難透水層です。」と説明すれば良いものと考えられます。
例えば、『一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(1998年6月16日総理府、厚生省共同命令)』には遮水工の規定があり、「透水係数が10のマイナス5乗cm/sの層が5m以上存在する場合は遮水層と見なす」という旨が記されています。
浸透時間(水が遮水層を通り抜けるまでの時間)tは次式で表されます。
t=(L^2)/(k・h)
ここに、L:層厚、k:透水係数、h:遮水層両側の水位差
例えば、k=10^-5(cm/s)、L=500(cm)、h=50(cm)の場合には、t=500000000(sec)≒16(年)となり、層を水が通り抜けるのに16年近くかかります。従って、難透水層以上に止水性の高い遮水層と見なせるわけです。
ご質問の透水試験結果k=5.67×10^-6という条件をもとに、この基準と同等の遮水性能を有する層厚を算出すると、(L^2)/(5.67×10^ -6)=(500^2)/(10^-5)の関係からL=376(cm)となります。もしも改良厚が4m程度あるなら、「透水係数5.67×10のマイナス6乗cm/sの薬液注入を4m程度行っており、最終処分場の遮水工と同等の遮水性を有しています。」と説明すれば良いものと考えられます。
N値から地盤支持力を求めたい
重力式擁壁を計画しています。N値から地盤支持力を求めたいのですが、何か手法はありませんでしょうか。
具体的にはN値が6の砂質土地盤で100kN/・の地盤反力度を確認したいです。どのような手立てがあるかお伺いします。
N値から砂質土地盤の許容地耐力qaを求めたいとのことですが、簡単な経験式として以下のものがあります。
砂層 qa = N (qaの単位はtf/m2)
参考文献:「N値およびc・φ −考え方と利用法−」 発行:(社)地盤工学会
従って、今回の場合N値が6であれば、許容地耐力qa=6tf/m2≒60kN/m2となりますので、100kN/m2には若干及ばないことになります。
もう一つは、砂の内部摩擦角φをφ=√(20N)+15 (°)として求め、地盤の長期許容支持力度qaを
qa=1/3(αcNc+βγ1BNr+γ2DfNq)
から求めるというものです。この方法についての参考文献は、前述のものにも記述してありますし、他にもたくさんあると思いますが、例えば、鹿島出版会から出されている、「土木設計の要点」シリーズの「1.設計の基本知識」、および「3.基礎構造物/地中構造物」が参考になります。
いずれにしても、砂質地盤でN値が6ですと微妙ですが、一般的には緩めの地盤であると思いますので、慎重に設計することが必要であるように思います。
宅地造成地擁壁背面の地盤改良必要性
高さ5メートルの無筋コンクリート擁壁(傾斜あり)上の土地に、木造2階建てを新築しようとしています。元々小高い丘だったところを地元の信頼できる業者が造成した住宅団地の端にあります。造成後4年間空き地でした。土地の形状から、擁壁に接する位置にまで建物が来ます。大手住宅メーカー2社がスウェーデン式サウンディングで調査した結果、1社は補強の必要あり、他社は必要なしでした。“N値”は前者で擁壁側のポイントのいくつかの深さのところに2.8-3.0の部分がありますが、概ね4-5以上の値です。後者ではN値はすべてのポイントで5以上でした。非常に硬い層は擁壁側で深さ約7メートルにあり、道側(擁壁と反対側)では深さ1-2メートルにあります。私が契約しようとしているメーカーは後者で、設計士(1級建築士で私の友人)の方が“必要ありません”と断言されます。地盤には20年保証がついています。
太鼓判を押されてもなお不安を感じますので、そのことを相談しましたら、“どうしても不安なら安心のために行っておいてもよい。しかし杭までは必要ないので、地盤改良がよい。そのほうが安くすむ。”と勧められました。本当は必要ないのだが、というニュアンスです。私の疑問・質問は以下の通りです。
・スウェーデン式サウンディングの信頼性。
・スウェーデン式サウンディングが信頼できるとして、本当に補強の必要がないのか。比較的軟らかい層の厚さが大きく異なっているので、常識的に考えれば擁壁側に傾く可能性は否定できないのではないか。
・もし地盤補強をするなら表層の地盤改良のみで効果があるのか。
宅地造成を行う際に、盛土高さが1mを越える場合は、”宅地造成等規制法”の定めに従って擁壁を設計し、都道府県知事または市長の許可を得る必要があります。この検査に合格しているなら、住宅程度の建物が載っても大丈夫なように擁壁は設計されています。また、平成7年の兵庫県南部地震における斜面崩壊の教訓から、擁壁の耐震性についても十分照査することを推奨するようになっています。
ご質問の土地のように、高さ5mの擁壁上の土地であっても、住宅程度の建物が載っても大丈夫なように設計されているものと考えられます。いかがでしょうか、少しは不安が解消されたでしょうか?
さて、ご質問の回答をいたします。
●スウェーデン式サウンディングの信頼性
スウェーデン式サウンディングは現在使用されている土質調査法の中で最も歴史が古く、小規模住宅では最も多く使われている調査法であり、この調査結果を基に多くの住宅が建てられ、問題が発生していないことから、実用上ある程度の信頼性があるものと考えています。
●傾斜地盤に比較的軟らかい層を盛土した土地だが地盤補強の必要はないのか
・盛土全体の安定と擁壁の安定
擁壁から道路までを20mとすると、基盤層の傾斜角は15°(勾配1:4)です。傾斜角が30°近い急斜面なら建物が盛土ごと滑ることも考えられますが、傾斜角15°では盛土崩壊の危険はまずないでしょう。
擁壁近くまで建物が来るとのことですが、前述の通り宅地造成の検査に合格しているなら擁壁崩壊の危険もないと考えられます。
・地耐力と不同沈下
「常識的に考えれば擁壁側に傾く可能性は否定できないのではないか」とお考えですが、締固め不足の地盤なら層が厚い擁壁側ほど沈下が多く発生し、建物が擁壁側へ傾くことも考えられます。
地盤調査のN値が概ね5以上であるとのことですが、このN値はスウェーデン式サウンディングから得られるNswとWswから、"N=0.02Wsw+ 0.067Nsw"などで換算した標準貫入試験のN値と考えて良いのでしょうか?もしN値が5以上であるなら、締固め不足による不同沈下の心配はないと思います。ただし、擁壁のすぐ背面は他の場所より締固めにくいので、この場所に独立基礎などの小さな基礎が配置された設計となっているなら、沈下に問題がないか再度ハウスメーカーに確認すると良いでしょう。
また、簡単な経験式から、砂層の許容地耐力qa=N=5tf/m2であり、木造2階建ての重量1tf/m2程度なら十分支持できます。
●もし地盤補強をするなら表層の地盤のみで効果があるのか
表層のみの改良でも、建物荷重を均等分散し不同沈下を抑制する効果と、擁壁への土圧を低減し擁壁の安定性を高める効果があります。しかし、現状でも安全だとしたら、過剰に安全にすることになるだけです。
地盤改良必要性の判断は、地盤調査結果だけを見て判断できるものではなく、土地造成方法や放置期間(降雨により地盤は締まる)、同種建物の基礎構造、地域性(地震、豪雨)などを考慮して総合判断するものです。経験豊富な大手住宅メーカーの設計士が判断したことなら十分信頼できると思います。さらに、地盤が問題で家屋にトラブルが発生した場合に20年間の保証があるなら何も心配する必要はないのではないでしょうか。
軟弱地盤における側方変位抑止矢板設計手法について
軟弱地盤で側方地盤に矢板を打設して、地盤の側方変位を減じる工法の矢板の計算方法を教えてください。
軟弱地盤における側方変位(側方流動)抑止矢板は、主に以下の状況で用いられます。
- 盛土や斜面安定のための地盤補強
- 近接施工時の周辺構造物や地下埋設物の保護
- 通常の土留め掘削
ご質問の状況が上記のどれに相当するかはわかりませんが、一般に、抑止矢板必要性を検討した後、簡易設計手法(弾性床上の梁)または詳細設計手法 (FEM解析)を行い、地盤安定必要安全率や許容変位量を考慮して、矢板の諸元を決定します。
簡易設計手法と詳細設計手法の使い分けは、詳細変形検討必要性、構造物重要度、施工規模、解析モデル複雑さ、施工時圧密沈下や地盤強度増加の有無等を勘案して決定しますが、最近では、・のFEM解析を行うケースが多くなってきています。
■抑止矢板必要性の検討
抑止矢板を用いない場合の、近接影響範囲や円弧すべり計算等による地盤の安定検討から、抑止矢板の必要性を明確にする。近接影響範囲については、発注者、工事内容、現場状況等によって考え方が違います。
【参考文献:近接施工技術総覧、⑭産業技術サービスセンター】
水平地盤の側方流動が生じる限界荷重(帯状荷重)qcrとしては、以下の3つの提案式が目安となります。
- qcr=4Cu・・・・主働土圧と受働土圧がつり合っている状態
- qcr=(B/(2H)+π/2)Cu・・・・マイヤホフ提案式
- qcr=Cu/(F・H) ・・・・日本道路公団提案式
ここに、
- Cu:地盤の非排水せん断強度
- B:帯状荷重の載荷幅
- H:軟弱層厚
- F:側方流動の生じ安さを示す係数で、通常F=0.04を目安とする。
側方流動の生じる限界荷重は、地盤の非排水せん断強度Cuの値に大きく左右され、圧密促進工法や緩速施工等により地盤の強度増加を図ることによって、限界荷重も大きくなります。
【参考文献:土質工学ライブラリー38地盤の側方流動,土質工学会】
■抑止矢板の簡易設計手法(弾性床上の梁)
矢板を水平方向弾性地盤に支持された杭と見なして設計する手法であり、弾性床上の梁、または、弾性地盤反力法と呼ばれています。この設計手法で最も有名なのがチャンの式であり、地盤を線形弾性体として導出されています。また、港湾構造物の設計では、地盤を非線形弾性体とする港研方式が多く用いられています。
矢板への外力は、すべり土塊を止めるために必要となる抑止力を作用させる、または、流動土塊による側方流動土圧(分布荷重)を集中荷重に置き換えて作用させるという2手法があり、設計手法の詳細については、それぞれ、以下の文献等を参考にして下さい。
- すべり土塊抑止矢板としての設計(抑止杭としての設計)
- 【参考文献:地すべり鋼管杭設計要領,(社)地すべり対策技術協会】・・・詳細に記述されています。
- 【参考文献:道路土工−のり面工・斜面安定工指針,(社)日本道路協会】
- 側方流動土圧抵抗矢板としての設計(自立土留め矢板としての設計)
- 【参考文献:港湾の施設の技術上の基準・同解説(下巻)第17章 自立矢板式係船岸、(社)日本港湾協会】
■抑止矢板の詳細設計手法(FEM解析)
地盤と構造物の相互作用は複雑であり、土質条件、境界条件、構成式、施工過程モデル化手法、メッシュの切り方等によって答えが変わるため、一般化されたFEM設計手法はなく、FEM解析を用いても信頼性のある結果が得られる保証は十分とは言い切れないのが現状です(未だ研究段階の点も多い)。しかし、より詳細な検討を行うためには、FEM解析が必要不可欠となります。
側方流動を受ける杭(受働杭)の二次元FEM解析事例については、下記文献にも紹介されています。
【参考文献:土質工学ライブラリー38地盤の側方流動,土質工学会】
また、FEM解析事例は、最近の学会論文集や講習会にも多数発表されているので参照して下さい。実際の地盤と構造物の変形挙動を解析的に求めることは非常に難しいことであり、私たちも解析手法の確立に向けて、日々努力しております。
DJM改良地盤上の盛土法尻付近に民家があるのですが
N値0〜O粘性土上に最大高さ12mの盛土計画があり、、接民家への影響を考慮して盛土下にDDJM行います。FEM形解析で宅地の変状を抑制するために必要な改良柱体の変形係数((E50)求めました。また、盛土の支持という面から複合地盤として必要な柱体のquも求めました。このqu時の変形係数は宅地変状抑制に必要な変形係数よりも低いので設計上はquとE50の両方を満足するセメント系固化材添加量を設定しようと思うのですが、発注者は「変形係数で規定されるのは経験が無い、本を読んでも事例が無い」とのこと。私の考え方は間違っているのでしょうか。本当に変形係数がkeyとなるような事例はないのでしょうか。
軟弱地盤を深層混合処理工法の一つであるDJM工法で改良し、その上に12mの盛土を行う計画となっているが、盛土の法尻付近に民家があり、盛土による地盤変形の影響が懸念されるということですが、通常、深層混合処理による改良柱体の設計は、以下の手順で行います。
- 改良仕様の仮定(強度,範囲、深度、改良率)
- 円弧すべり検討 (2'.側方変位検討(FEM解析)・・・・変位量に制約がある場合のみ)
- 支持力検討
- 沈下量検討
- 改良仕様の決定
参考文献:
『陸上工事における深層混合処理工法 設計・施工マニュアル、平成11年6月、(財)土木研究センター』
http://www.pwrc.or.jp/oldnews/wnew0108.html#010
FEM解析については、p99〜103を参照
ご質問の内容としては、
A.2'側方変位検討から必要となる変形係数を算出し、設計基準強度quを設定
B.3支持力検討から必要となる設計基準強度quを設定
上記A、Bの大きい方のquを設計基準強度として、Aを採用することにした。
ということですが、考え方は間違っていないと思います。
ところで、設計の必須項目である2円弧すべり検討は行ったのでしょうか?
地盤と構造物の相互作用は複雑であり、土質条件、境界条件、構成式、施工過程モデル化手法、メッシュの切り方等によって答えが変わるため、一般化されたFEM設計手法はなく、FEM解析を用いても信頼性のある結果が得られる保証は十分とは言い切れないのが現状です(未だ研究段階の点も多い)。しかし、より詳細な検討を行うためには、FEM解析が必要不可欠となります。
つまり、FEM解析は万能ではないことをよく認識することが大切です。この万能ではない部分を補うのが、観測施工や、過去の実測例や、実験結果等に基づく工学的判断であると考えています。
ご質問のケースは、盛土の法尻付近に民家があるという状況であるため、安全面から考えて、特に慎重に設計を行う必要があり、発注者がFEM解析結果を鵜呑みにできないことは納得できます。
FEM解析結果をそのまま設計に反映する際には、ぜひ、盛土を行う過程で地盤変形の観測を行い、早期に危険を察知し、対処できるような施工計画(観測施工)を立案することをお勧めします。
軟弱層中間までの地盤改良でL型擁壁の安定は保てますか
田畑部でL型擁壁を計画していますが、支持層(軟岩?)まで基礎底面から3.0 m程度あります。上層は平均N値8程度の砂質土です。支持層まで地盤改良するにはコストの面で問題があると判断し、軟弱層の中間まで地盤改良し、地中内の分散に期待する工法を選択しました。この考え方は強制置換工法にも適用できますか。
ご質問の件ですが、確かに支持層まで深い場合、応力の分散を考えて地盤改良を一定深度で止めることはあります。強制置換の場合も同じ考えが可能です。このとき注意が必要なのは3点です。
1)改良底面での支持力のチェック
この場合、地盤改良の底面で十分な支持力が確保されることが条件となります。L型擁壁ですから、背面から土圧が作用し、地盤改良の底面の接地圧は、前側の方が後ろ側より大きくなるので注意が必要です。
2)地盤改良底面より下部での円弧滑りの検討
L型擁壁ですから、背面より土圧を受けるので円弧滑りによる安定検討が必要です。この時、地盤改良より下を通る滑り面について円弧滑り計算を行い、一定の安全率を確保していることが必要です。
強制置換を行う場合、上記の2つの方法で改良深さを決定します。
3)長期的な沈下
ご質問には明示されていませんが、仮に改良層より下が粘土層の場合には、L型擁壁の荷重は分散するとはいえ、長期的な沈下が発生します。L型擁壁の高さも重要ですが、この沈下がどの程度であり、構造物に影響を与えないことも確認する必要があります。
擁壁背後のセメント固化改良による土圧軽減効果について
傾斜地ある高さ2.5m程度の既設擁壁を改良する事になりました。背後の地盤はN値18〜 12の砂質土ですが、擁壁の端趾圧と地耐力を検討したところ、若干地耐力が足りません。対策として、あるメーカーは「背後地盤をセメント撹拌により改良して土圧軽減をはかるべし」と主張するのですが、セメント撹拌による背後地盤改良は内部摩擦角の向上や土圧係数の低減など、擁壁背後の土圧軽減に効果があるのでしょうか。
砂質土をセメント系地盤改良したとき、その改良土は、セメント改良による粘着力が付加されるとともに、原地盤が有していたせん断抵抗角も併せ持っている材料として評価することができます。
しかし、改良土のせん断抵抗角については、セメント改良後に増加する説とほとんど増加しない説とがあり、評価が分かれているのが現状です。
よって、内部摩擦角の向上は期待できませんが粘着力の増加による土圧係数の低減の効果はあるでしょう。
ただし、既設擁壁の背後をセメント攪拌したときに、固化前において地盤を攪拌することによる流動圧が擁壁に作用しますので、擁壁が前面にはらみ出すおそれがありますので、その検討を行う必要があると考えられます。
また、背後地盤の水平土圧低減によって端趾圧を抑え、地耐力を確保する方法は、どちらかというと二次的な対策方法であり、擁壁の地耐力が足りない場合において最も効果的な対策としては、擁壁背後の荷重の軽量化があげられます。擁壁背後の荷重の軽量化方法として、例えば、
- 軽量混合処理土
- 軽量モルタル
があげられます。
<1.軽量混合処理土>
現地発生土に安定剤と気泡または発泡ビーズを混合して軽量な地盤に置き換える工法であり、約10,000円/m3です。本工法の場合、プラントをもちいて軽量処理土を作成するので、処理土プラントを置くためのスペースの確保が必要となります。また、プラントの費用を考えると対象数量が大きい場合には適しているでしょう。
<2.軽量モルタル>
擁壁背後の地盤を軽量モルタルで置き換える工法であり、約10,000円/m3です。この場合プラントは不要ですが、現地盤を軽量モルタルと置き換えるために排土の処理が必要となります。
また、背後地盤のセメント攪拌のほかに擁壁背後の土圧低減する方法としては、掘削した発生土に固化材を添加して埋戻す方法があります。
ブロック塀の高さについて
田を買って現在宅地造成をしています。3方が田のためφ13の鉄筋を入れて15cmブロックを6段積んでいます。GLを道路より70cmほどあげたいのですが、これ以上ブロックを積んでも危険ではないのでしょうか。聞いたところ宅造規制区域ではないので問題ないとのことでしたが、ふつうは5段以上は積まないと言われました。本当なら何かいい方法はありますか?
ブロック塀の高さ・厚さと基礎の構造に関しては、日本建築学会基準として、壁式構造関係設計規準集・同解説(メーソンリー編)に記載されています。
通常はこれに準拠し、ブロック塀の高さや基礎の形状、外圧(土圧)の条件が標準的であれば、構造計算を省略することができます。標準的な条件を満足しない場合には、造成することができないというわけではなく、構造計算により基礎や塀の仕様を決めることにより可能となります。
以下は、非常に参考になるHPです。
http://news-sv.aij.or.jp/zairyou/s2/index.html
規準に記載されている標準的な条件は以下の通りです。
■ブロック塀の高さと基礎形状
地盤の性質が普通土(土や砂など)である場合、「ブロック塀の高さ(塀の外の地盤面からブロック天端まで)」は、I型基礎で120cm、T型・L型基礎で160cmとすることができます。I型基礎においても、基礎の根入れを標準(40cm)より10cm増せば160cmとすることができます。ただし、地盤が軟弱土(粘土など)の場合には、いずれの基礎においても高さは上記値から20cm以上減じるとされています。
■外圧(土圧)
ブロック塀背面盛土の影響として、ブロックが土に接する部分40cm以下の場合には標準的な仕様によることで計算を省略することができます。
以上を踏まえた上で、質問の『15cmのブロック』=『B15cm×H19cm×L39cmの標準型建築用ブロック』と判断して、ご回答いたします。
■ブロック塀の高さについて
宅地造成方法および塀の設置位置・構造にもよりますが、基礎が田んぼの土に直に設置してある場合、または、基礎の埋戻しに悪質な土を用いている場合には、規準における軟弱土の分類にあてはまる可能性があります。この場合、基礎形状に応じて、ブロック塀の高さは100〜140cm以内となります。
ご質問のブロック塀の高さは、20cm×6段=120cmであり、規準における標準的な条件を満足しない場合も考えられ、構造計算が必要となる可能性があります。
安全策として、20cm×5段=100cm以上積まないというは正解と思います。
宅造規制区域でないということですが、まずは、基礎の形状、地盤状況を確認して下さい。状況により、基礎寸法を大きくする必要があろうかと考えます。
■外圧(土圧)について
ご質問の盛土は70cmということなので、構造計算不要な盛土40cm以下という条件を満足していません。したがって、地震時の土圧の影響などを考慮し、計算により鉄筋量を決める必要があります。
また、土に接する部分に使用するブロックはC種防水ブロックか型枠ブロックとし、空洞部にはすべてモルタルを充填するといったことも必要です。
現状の鉄筋がD13ということで、おそらくD13を800mmピッチで配筋する仕様になっているかと思われます。詳細な計算はしていないため、あくまでも参考として頂きたいのですが、D10を800mmピッチでD13の間に配筋(つまりD13とD10を400mmピッチで交互配筋)して鉄筋量を増やせば良いかと考えます。
また、盛土の締固めもふくめ地盤状況が悪い場合には、D13を400mmピッチで配筋する必要があるものと考えます。
■既にブロック塀の基礎部分が構築されてしまっている場合の対策
控え壁(塀直角方向に設けた倒れ止めの壁)による補強、基礎の増強、地盤改良など様々な対策が可能ですが、構造計算が必要となります。
ボックスカルバート縦方向設計時の境界条件について
ボックスカルバ−トの縦方向の検討についての質問です。文献の柔構造樋門に「直接基礎の本体は、「弾性床上の梁」としてモデル化する。(p150)」「v)境界条件 樋門本体の両端の境界条件は、一般には両端ともフリ−と考えられる場合が多い。(p152)」と記載されています。また、道路土工指針「カルバ−ト工指針」においては縦方向の検討について「縦方向の設計は原則として「弾性床上のはり」として解析するものとする(p58)」と記載されています。よって、道路土工指針に準拠したボックスの縦方向の検討では両端の境界条件として自由、自由で検討を行ってもいいのでしょうか?
ご質問の通り、「柔構造樋門設計の手引き」も「道路土工・カルバート工指針」も、本体ボックスカルバート縦方向の設計については、「地盤変位の影響を考慮した弾性床上の梁」として解くことを原則としています。設計方法が同様であるため、道路土工指針に準拠した設計においても、「柔構造樋門設計の手引き」に記載されている通り、「樋門本体の両端の境界条件は、一般には両端ともフリーと考えられる場合が多い。」を流用して良いものと考えられます。
解析において、両端がフリーか固定かという境界条件は、たとえ基準書に書かれていなくても、設計対象物の両端接続条件、支持条件に応じて、設計者が適切に設定する必要があると思います。
接続条件としては、例えば片端が吐出水槽に連結してある場合などで、スパンの結合条件と同様に、可とう性継手ならフリー、カラー継手ならヒンジ、弾性継手ならバネというふうに使用する継手の特性に合わせて境界条件を設定します。
支持条件としては、端部に支持杭や地盤改良が施されている場合などで、端部固定や端部の地盤剛性を大きくするなど支持条件の特性に合わせて境界条件を設定します。
擁壁設計の概略土質定数について
現在、擁壁の検討を行っている地盤が、山間の谷部で田畑となっています。土質調査を行わないため、想定で検討するしかないのですが、経験が無いため、どの程度に設定して良いか悩んでいます。
概略でいいのでN値、c、φ、γの数値を教えて頂けませんか。宜しくお願いします。
田畑の概略の土質定数とのことですが、残念ながら、これは一概にいくらと決めることは出来ません。現実には周辺で同様の擁壁を設計したことのある方は、その時の経験に基づいて何とか値を設定しているという状況かと思いますが、土質調査結果も無く、その周辺の様子も全く分からないのでは、設計は出来ません。
粘性土か砂質土かという判別がついていて、N値程度が分かっていれば(推測できれば)、一応設計計算は出来ないこともありません。小規模な工事では、このような設計がされることもあるようですが、当然誤差は大きく、現地の状況(地質、地形や成り立ち、水位)などを適切に判断出来るか、周辺の同様の構造物の形状等から、土質を逆算で推定してみるなど、いろいろな観点から慎重に検討をしなければなりません。
従って、あまりおすすめは出来ないのですが、一応参考になりそうな事柄をまとめてみました。
(1)砂質地盤の場合
砂質地盤であれば擁壁に作用する土圧計算には、湿潤単位体積重量γ=18kN/m3(≒1.8tf/m3)程度、粘着力c=0kN/m2と考えて良いため、あとは内部摩擦角φが分かれば土圧が算定できます。この内部摩擦角φは、N値から推定することが出来ます。推定式は対象となる設計指針毎に異なり以下の通りです。
| 指針 | 推定式 |
|---|---|
| 道路橋下部 | φ=√(15N)+15≦45° |
| 道路公団 | φ=√(20N)+15(土工) |
| 建築基礎 | φ=√(20N)+15 |
| 鉄道構造物 | φ=1.85×(N/(σ'z+0.7))^0.6+26 (σ'z:土被り圧) |
| 港湾構造物 | φ:ペック・マイヤホフのN-φ関係、またはダナムの式 |
あとはN値が分かれば良い訳ですが、かなりおおざっぱな推定法として以下の様なものがあります。※1)
| N値 | 相対密度 | 現場判別法 |
|---|---|---|
| 0〜4 | 非常に緩い | φ13mmの鉄筋が容易に手で貫入する |
| 4〜10 | 緩い | ショベル(スコップ)で掘削できる |
| 10〜30 | 中位な | φ13mmの鉄筋を5ポンド(2.27kg)のハンマで 容易に打ち込める |
| 30〜50 | 密な | 同上で30cmくらい入る |
| >50 | 非常に密な | 同上でも5〜6cmしか入らない。掘削につるはしが必要 |
乾いた砂の内部摩擦角φの代表的な値は以下の通りです。
均一な粒土で丸い粒子(緩い28.5°,密な35°)、粒度の良い角張った粒子(緩い34°,密な46°)。
(2)粘性土地盤の場合
粘性土地盤であれば、単位体積重量γ=14〜18kN/m3(≒1.4〜1.8tf/m3)、内部摩擦角φ=0°として良いため、あとは粘着力cが分かれば土圧が算定できることになります。粘着力cはc=qu/2(qu:一軸圧縮強さ)で算定できますが、cやquについてもN値からの推定式が対象となる設計指針毎に出されています。
| 指針 | 推定式 |
|---|---|
| 道路土工 | qu=(1/8〜1/2)N (kgf/cm2) |
| 道路橋下部 | c=(0.6〜1.0)N(kgf/cm2) |
| 道路公団 | c=(0.6〜1.0)N(kgf/cm2) (橋梁下部) |
| 鉄道構造物 | c=N/16(kgf/cm2) (斜面の概略安定計算) |
| 港湾構造物 | φ:ペック・マイヤホフのN-φ関係、またはダナムの式 |
又、quとN値および現場の状況の関係も前述と同じ文献に示されています。※1)
| N値 | コンシステンシー | 現場判別法 | 一軸圧縮強さqu(kgf/cm2) | |
|---|---|---|---|---|
| Terzaghi-Peck | 大崎 | |||
| 0〜2 | 非常に柔らかい | こぶしが容易に 10数センチ入る |
0.25以下 | 0.60以下 |
| 2〜4 | 柔らかい | 親指が容易に 10数センチ入る |
0.25〜0.5 | 0.25〜0.90 |
| 4〜8 | 中位 | 努力すれば親指が 10数センチ入る |
0.5〜1.0 | 0.35〜1.00 |
| 8〜15 | 硬い | 親指で凹ませられるが、 つっこむことは大変である |
1.0〜2.0 | 0.70〜1.25 |
| 15〜30 | 非常に硬い | つめでしるしがつけられる | 2.0〜4.0 | − |
| 30以上 | 固結 | つめでしるしをつけるのが難しい | 4.0以上 | − |
また、N値とquの関係は次式のようなものもあります。
Terzaghi-Peck:qu=N/8 (kgf/cm2) 、大崎: qu=0.4+N/20 (kgf/cm2)
【参考文献】
※1)「N値とc・φの活用法」、(社)地盤工学会 発行。
埋戻し部の土砂浸食防止について
木造2階建ての住宅の地盤についてご相談します。
砂質地盤の敷地です。東側と南側に道路(道幅は狭いのですが交通量は多い)があり、道路に沿って間知石積みの擁壁(築造年月日は不明ですが何箇所か亀裂が見られます)があります。
道路から宅地までの高さは約3.5mです。その高さを利用して間知石積みの一部を壊して、RCの地下車庫・擁壁を築造し、その上に木造2階建ての住宅を建築しました。
現在、車庫・擁壁の埋め戻し部分と思われる箇所が数箇所、砂が逃げてしまい穴が開いています。
建築当時から、水みちがあり、透水管をいれて排水した経緯もあり、敷地に降る雨や地下水が作用しての事と思いますが、どのような改良を施せばいいかご教示ください。
尚、建物の沈下はありません。テラスが一部沈下している程度です。
擁壁の埋戻し部が雨水により浸食されていて、土砂が漏出するのを防止したいとのことですが、対策としては、
1)ベントナイト等止水材料による埋め戻し
空洞底部に土にベントナイトやセメントと水を混ぜて流動状にしたものを打設して止水を図った後、通常の土で埋め戻す。
2)防砂シート敷設
漏出箇所中心に織布もしくは不織布(透水性があるが砂は通さない)を敷設して通常の土で埋め戻す。
3)薬液注入
地表面からボーリングマシンによって削孔し、固結性の薬液を注入する。
などが考えられます。(漏出箇所が石積みとコンクリート擁壁の境目などとはっきり分かっていて、止水モルタル目地などで簡単に対策できるものは除く。)
規模に依りますが、木造2階建ての一戸建ての規模であれば、施工金額は1)≦2)<3)となると思います。
上記のどれを使うかは現地の条件によって変わりますが、
- 土砂の漏出箇所をある程度限定できるか。
- 限定できる場合、その箇所まで掘削は可能か。
- 限定できない場合、現在の空洞が未だにだんだん大きくなっているか。
などを判断する必要があります。
漏出箇所が限定できる場合、最も安価と思われる対策は、1)止水材料による埋め戻しだと思います。だんだん空洞が大きくなっている場合は、最初に止水性を持つベントナイトなどの材料を泥水状にして地中に散布・浸透させたのち、土にベントナイトを混ぜたもの、もしくはソイルモルタル(土にセメントと水を混ぜて流動状にしたもの)を数十センチ程度の厚さで施工して遮水層を作ってから、通常の土で埋め戻すという方法が良いのでは無いかと思います。この場合、流亡経路(水みち)が大きいか小さいかで最初に散布するベントナイト泥水の濃度を調整したり、場合によってはベントナイトにおがくずを混ぜたりすると効果が上がる場合もあります。
この方法を採る場合、雨水・地下水の浸透経路を確保するために、遮水層上部に透水管等による排水工を施工する必要があります。
また、漏出箇所が限定できて、その箇所まで簡単に掘削が可能である、もしくは掘削が必要無いのであれば「2)防砂シート敷設」による対策も効果的です。この場合、漏水個所を確実に覆うことと、シートの端部処理をきちんと施工することが重要になります。
ピンポイントで場所が特定できても1)、2)の施工が困難な場合や、漏出箇所が全く分からない場合は、改良範囲を大きめに設定して薬液注入工法を行うしかなくなります。薬液注入工法の場合、細粒分含有率が大きい(一般に細粒分含有率Fc>5〜10%以上)場合、削孔を密に行って注入しなければならず施工費が高くなってしまいます。また、注入圧が高すぎると、擁壁がはらんだり車庫の壁にクラックが入る危険性もありますので、きちんとした業者を選んで適切な管理をする事が重要になると思います。また、この方法でも施工範囲上部の雨水、地下水の排水工に留意する必要があると思います。
その他改良技術に関する質問
サンドコンパクションパイル工法について
サンドコンパクションパイルによる地盤改良に関して教えてください。
- どの程度まで改善できるものでしょうか?
- またその改良率は?
- 粘土層・砂層の互層の地盤改良をおこなった場合、その取り扱いは?
サンドコンパクションパイル工法は地盤中に締め固めた砂杭を造成し、地盤の安定を図る工法であり、現在ではもっとも広範囲に使われている地盤改良工法の一つであります。改良目的としては、地盤安定、沈下対策、液状化対策などが挙げられます。
1.どの程度まで改善できるものでしょうか?
陸上では35m程度、海上で水面下60m程度の深度まで施工実績があります。
2.またその改良率との関係は、どの様になっておるのでしょうか?
一概には言えませんが、大きく分けると砂か粘土かで考え方が変わります。
砂の場合:
改良域に対するコンパクションパイルの面積を置換率と言います。砂の場合、置換率は0.1〜0.2程度が用いられ、この時のN値の増加は10〜20程度です。
粘土の場合:
非常に大まかですが、置換率が0.7以下の場合、砂杭と粘土の複合的な地盤として取り扱います。N値で言うと、砂杭間のN値の増加は0から最大でも10程度です。置換率が0.7以上の場合、砂置換と考えてφ30°の砂地盤として取り扱います。
3.粘土層と砂層の互層地盤の改良をおこなった場合のその取り扱い。
杭の大きさと改良率(砂杭の打設間隔)を改良仕様と言い、設計で決めます。通常、N値で管理しますので、N値の増加率の低い粘土層のN値の増加で、砂杭の改良仕様が決まると考えられます
粘土の脱水ケーキによる埋立方法について
埋立時における施工厚に関して。
粘土の脱水ケーキを0.6〜1.8m層厚撒きだした後、覆砂を0.5m厚施工する予定です。
脱水ケーキを1層にて仕上げた後、覆砂すると必要天端高を確保するためには必要以上の砂の投入が必要となるので脱水ケーキを数層に分けて投入した後、覆砂を施工しようという設計案があります。
脱水ケーキ層の圧密を考慮し、余盛高を決定するのが筋だと思うのですが、脱水ケーキ層の圧密を設計上は考慮しないとした場合、上記のように数層に分けて施工する意味があるとお考えでしょうか?
海上工事における埋立(施工)厚に関して。
埋立材料の変動、円弧すべりおよび施工方法により埋立(施工)厚は決定されるかと思いますが、安定上問題なければ海上工事における一般的な埋立(施工)厚はどれ位なのでしょうか。
上記質問の返答においては土性や、施工方法、工期等絡むので返答に困られるかと思いますが、最大1.8mの埋立を段階施工する意味は少ないかと思うのですが、いかがでしょうか。なお、円弧すべり等の安定上の問題はありません。造成後、天端を車が走るということもありません。単なる人工干潟造成です。造成の目的上は天端高を確保しなければならないという必要性はないのですが。
粘土の脱水ケーキ(h=1.8m)層の上に覆砂(h=0.5m)を行い、人工干潟を造成するということですが、現地の状況が詳しくわからないので一般論としてお答えします。
Q1.脱水ケーキを1層にて仕上げた後、覆砂すると脱水ケーキの圧密沈下が大きく、余分に覆砂が必要となるため、脱水ケーキを数層に分けて投入し、圧密沈下量を低減できないか?
A1.沈下の検討には、まず、脱水ケーキの含水比を知る必要があります(どの程度過圧密となっているか知る必要があります)。脱水方法には真空脱水、遠心脱水、機械脱水など様々な方法があり、脱水効果は液性限界含水比wLの0.9〜1.1倍程度が目安となります。また、後者ほど脱水効果が高く脱水ケーキのハンドリング(トラックなどで運搬)が容易になります。粘土をハンドリング可能な含水比まで脱水するものと考えれば、脱水方法はフィルタープレスなどの機械脱水であると考えて回答を進めます。
標準的なフィルタープレスの給泥圧力は0.5〜0.7Mpa(50〜70tf/m2)程度であり、脱水ケーキの含水比は0.9wL程度以下になります。例えば、wL=80〜120%(間隙比e=2〜3.2)の粘土であれば、0.9wL=70〜110%(e=1.8〜3)になります。
土質データがないので「土質試験の方法と解説(第1回改定版),p374,(社)地盤工学会」のe-p関係を参照にすると含水比0.9wLの粘土は圧密圧力p=3〜5tf/m2程度で圧密が終了した状態に相当しています(この圧密圧力が圧密降伏応力pcとなります)。
さて、圧密降伏応力pc=3〜5tf/m2の脱水ケーキは覆砂(h=0.5m)で沈下するかを考えてみます。人工干潟を造成するということなので干潮時には覆砂の湿潤重量が圧密圧力として作用するものと考えると圧密圧力はp=γh=1.8×0.5=0.9tf/m2となります。p<pcであるため覆砂後の脱水ケーキは過圧密状態であり覆砂の荷重ではほとんど沈下しないものと考えられます。 また、脱水ケーキを数層に分けて投入したとしても、ほとんど沈下しないという状況は変わりません。
Q2.脱水ケーキによる一般的な埋立厚?
A2.現地の状況によって脱水ケーキ投入方法も異なるため、一般的な埋立厚について明言はできませんが、地盤の安定上問題がないのであれば、施工上は厚さ 0.5m以上あれば問題なく施工できると考えられます(薄層に撒き出す方が難しい)。
なお、浅瀬への脱水ケーキ投入方法としては以下のような方法が考えられます。
- 脱水ケーキを台船で海上運搬する場合
- 浅瀬まで台船で運び台船上のペイローダで直投
- 浅瀬までベルコンスプレッダー付き台船で運び直投
- 沖の台船からフローティングコンベアで投入位置まで運ぶ
- 脱水ケーキをダンプトラックで陸上運搬する場合
- 陸上基地からフローティングコンベアで投入位置まで運ぶ
- 潮間をみてダンプトラックで直投
- 浅瀬に仮設桟橋、仮築堤を作りダンプトラックで直投

