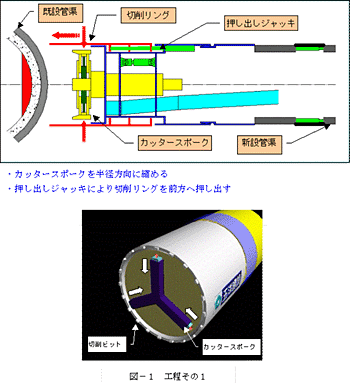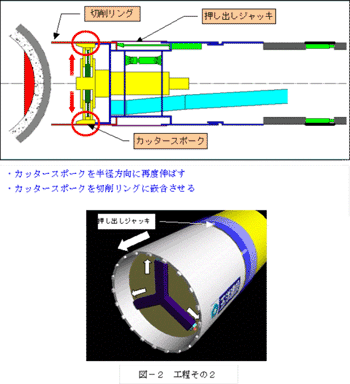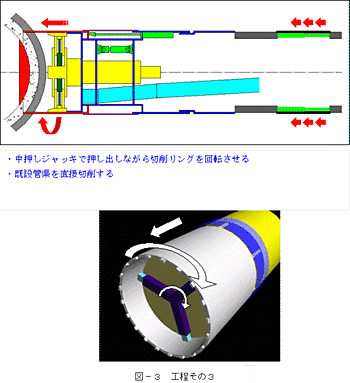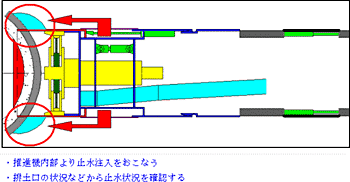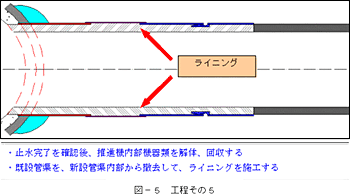このページは、ホーム![]() What's New
What's New![]() 2004年
2004年![]() 下水道管渠などの合流部構築工法を開発のページです。
下水道管渠などの合流部構築工法を開発のページです。
What's New
下水道管渠などの合流部構築工法を開発
2004年07月14日
五洋建設(社長:加藤 秀明)、協和エクシオ(社長:高島 征二)、アルファシビルエンジニアリング(社長:酒井 栄治、本社:福岡県福岡市博多区、TEL092-482-6311)の3社は、中小口径の推進工法を使った下水道などの新設管渠と既設管渠の側面を地中接合するにあたり、切羽作業や大規模な地盤改良を行なわずに、既設管渠を機械的に直接切削して合流部を構築できる 「MELIT工法(MEchanical LInking a pipe jacking Tunnel to underground structure)」 を共同開発しました。
従来、既設管渠側面に新設管渠を地中接合する場合、(1)既設管渠近傍を高圧噴射攪拌杭工法などによって地盤改良する工法、(2)近傍に到達立坑を構築する工法などが伴なっていました。しかし、(1)においては地盤改良費が大幅に増することや、地下埋設物などによって施工性が劣るという問題が指摘されており、(2)は立坑築造で工費増大を招き、到達立坑構築後も立坑と既設管渠の間に新たな管渠を設けるため、工期が多大となる課題が生じていました。
新たに開発した「MELIT工法」は、鋼製ならびにRC製などの既設管渠を切削することができる自生刃ビットを先端に設けた切削リング一体の推進機により、新設管渠を構築した後に切削リングを掘進方向前方に押し出し、既設管渠側面を直接切削して合流部を完成させる工法です。
施工手順は以下のとおりです。
- まず、新設管渠を敷設しながら既設管渠近傍まで推進します。
- 続いて、推進機のカッタースポークを半径方向に縮めて、切削リングを推進機に内蔵した押し出しジャッキにより前方に押し出します(図―1)。
- その後、カッタースポークを半径方向に再度伸ばして、その先端を切削リング内側に嵌合させます(図―2)。この状態でカッタースポークの回転駆動力を切削リングに伝達することが可能となります。
- 嵌合が完了した後、切削リングを回転させて既設管渠を直接切削します(図―3)。
- 切削部周辺の止水注入をおこない止水状況を確認した後、推進機内部を解体・撤去します(図−4)。
- その後、内部ライニングなど仕上げをおこない合流部を構築します(図−5)。
本工法の特長は以下の通りです。
- 既設管渠を直接切削する際に、切削リングが山留代わりとなるため、接合時の切羽作業が不要となり、安全な施工が可能となります。
- 既設管渠を直接切削することにより、立坑築造が不要となるため工期・工費短縮が可能となります。
- 本工法における補助工法は、推進機内部から接合部への止水注入が主たるものとなるため、地上から接合部周辺への地盤改良が不要となります。
- 推進機駆動部などを解体・撤去した後は、推進機内部からの既設管渠覆工撤去、接続部仕上げをおこなうことにより、新設管渠内部からの作業が主たるものとなるので、新設管渠と既設管渠の両方で作業をする場合に比べ、作業効率が向上します。
本工法は「T字接合シールド工法」※1の内、推進工法における地中接合工法としてメニュー化され、新設する推進トンネルの内径1,200mm以上に対応が可能です。
本工法は、既設管渠の分岐合流部構築をはじめとする水路施設のネットワーク化など様々な社会基盤整備に対して貢献することが可能で、今後事業者などに積極的に提案してまいります。
なお、本工法は7月27日(火)〜30日(金)に横浜市・パシフィコ横浜で開催される下水道展(主催:社団法人日本下水道協会)にて紹介する予定です。
※1)T字接合シールド工法(T−BOSS工法)
T字接合シールド工法は、東京都下水道サービス(株)、(株)熊谷組、五洋建設(株)、清水建設(株)、東急建設(株)、西松建設(株)、(株)間組、ジオスター(株)、日立造船(株)、三菱重工業(株)の10社で研究開発し、実用化した工法です。